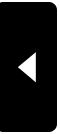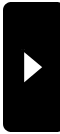痛み ・・・・イタミ・・・・
たった一回しか会ったことがない人を愛おしく想うことがあります。
ボクの大好きな「カマル」おばぁちゃんに会ったのは、彼女が88歳の米寿を迎えた年でした。
カマルさんは、本部半島の緑深い小さな集落に住む元気なおばぁちゃんで、年季の入った赤瓦屋に一人暮らしをしていました。
沖縄では、戦前、パナマ帽子の生産が盛んで、基幹産業品として海外へ輸出されるほどでした。
戦後、パナマ帽子産業は、すっかり廃れてしまい、時が経つにごとに当時を知る人も少なく
なっていました。そんな中、知人の紹介でパナマ帽子の編み手さんだったカマルさんを訪ねたのでした。
・・・・小雨の降りしきる、あいにくの空模様でした・・・・
「昔はね、どこの家も若い娘(こ)は、みんな(パナマ帽子を)編みよったですよ。どこかの家に集まって、みんなで編んだんです。工房ゆうてね。朝から晩まで作業はきつかったけど、お友達とのおしゃべりは楽しかったですね。ぺちゃくちゃして」
カマルさんは、まるで昨日のことのように、よどみなく、楽しげに話すのでした。
初対面のボクに、ホントのおばぁちゃんのような素直な優しい語り口でした。
パナマ帽子製造のお話を一通り教えていただき、ひと段落のお茶をいただいていたとき、カマルさんは庭先に視線をやり、少し間をおいて溜息をつくのでした。
・・・・小雨は音も立てずに、庭の花壇を濡らしています・・・・
「小さい子供が二人いたんですよ、私。三歳の女の子と、生まれて間もない男の子。下の子は、まだ乳飲み子でした。(パナマ)帽子作業のときは、子供をまとめてあずかってくれる所があって、そこにあずけて・・・」
またひとつ、小さな溜息をついて、カマルさんは静かに話しはじめました。
「・・・その時は・・・疲れていたんでしょうかね・・・忙しい時期でした。毎日、朝早くから夜遅くまで帽子作業が続いていました。納期に間に合わないゆうて・・・」
さっきの明るいカマルさんと違い、淋しげな口調でした。
「・・・その日も、夜遅くまで作業して、子供迎えて、家に戻ったときは真っ暗でした。・・・疲れていたんでしょうねぇ・・・とっても眠くて・・・下の子がグズるんで、横になって、おっぱいあげながらウトウトしていたんです。女の子は背中にひっつくように、一緒に横になって・・・」
・・・・雨脚が一瞬強くなり、垣根の月桃の葉を揺らしています・・・・
「しばらく、おっぱいやりながらウトウトしていたんでしょうね。・・・背中越しに女の子が言うんですよ。『お母ちゃん、こっち向いて』って。『怖いよぉ、怖いよぉ』して。下の子におっぱいふくませているから、振り返られないから・・・こう、片手で、女の子の背中トントンして・・・『大丈夫よぉ、すぐ、そっち向くよお』って言ってね。・・・でも、女の子は『早くこっち向いてぇ。怖いよぉ、怖いよぉ』して」
「・・・疲れていたんでしょうかねぇ・・・そのうち、眠ってしまって」
「・・・朝、目が覚めたら、女の子が冷たくなっていて。・・・どこも、なんともないのに、眠ったように・・・冷たくなっていて・・・」
カマルさんの目から、大粒の涙があふれています。
「・・・あんな、小さな子・・・三歳の子に怖い思いをさせてしまって・・・淋しい思いをさせてしまって。どうして・・・あのとき・・・ちょっとでも振り向いてやれなかったのか・・・悔しくて・・・悲しくて、悲しくて・・・。今でも、朝起きるたび、夢だったらいいのに、って思うんですよ」
ボクは、かえす言葉が見つからず、ただただ、黙って泣いているだけでした。
時が経っても消えない、切なさ。毎朝繰り返す心の痛み。そんな日常に生きている人もいるのです。
2011年10月12日 16:50
灯
はじめに断っておきたいのですが、ボクはユタでもカミンチュ(神人)でもありません。
ましてやセジ(霊力)が高いわけでもサーダカンマリ(生まれ)でもありません。
こんな霊能力ゼロのボクですが、奇妙なモノを目撃したことがあります。
小学校三年のときの出来事ですから、今から数十年前になります。
その日ボクは、クリスマスに親からおこずかいをもらいました。
クリスマスなのにプレゼントではなくおこずかい・・・というのもヘンな話ですが、
たまたまおこずかいをもらったのが、クリスマスの日だった、ということです。
当時はクリスマスのプレゼントどころか、クリスマスパーティを開くことも珍しい時代でした。
とにかく、おこずかいをもらったボクは、その金をにぎりしめ、早速、近所の「一銭マチヤ」(駄菓子屋)に走りました。
その一銭マチヤでは、いつもおばぁちゃんが独りチョコンと座って店番をしていて、その日もおばぁちゃんが店頭にいました。いつものように、にこにこと笑っていました。
ボクは、クジ引きにしようか美味しそうに並んでいる駄菓子にしようか、悩みに悩みながら商品棚を覗き込んでいました。
なかなか決まらなくて、ふと、おばぁちゃんの顔を仰ぎ見たとき、一点に目が釘付けになりました。
にこにこ微笑んでいるおばぁちゃんの頭の上に、なにかがユラユラ揺れているのが見えるのです。
青白い炎のようなものでした。
さっき店に走り込んできたときにはまったく気づかなかったのですが、おばぁちゃんの頭の上に青白い炎のようなものが揺れているのです。
正確にいいますと、おばぁちゃんの頭頂部の上5センチくらい離れてブルーの靄のようなもの見えるのです。
それは、コンビニなどで加湿器から出したばかりの肉まんの上部にブワッと湯気が立ち、収束され、中空に立ち登る感じなのですが、収束された部分が炎のように揺れ、しかも青白いのです。瞬間ではなく、そこにあり続けているのでした。
あまりの突然のことで、ボクはびっくりし、そのまま何も買わずに店を飛び出しました。
店を出たボクは、自分がおかしくなったのだと思い、道ゆく人、すれ違う人、すべての人の頭の上を凝視しました。
しかし、あの青い炎が頭にある人なんて、ほかに誰もいません。普段の、当たり前の日常の景色が広がっているだけでした。青い炎は、見間違いだと自分に言い聞かせ、納得するようにしました。
ただ、怖くて、その日は一銭マチヤには行きませんでした。
翌日・・・・
ボクは友だちと遊ぶために、近所の空き地へ向かいました。
空き地へは、一銭マチヤの前を通らなければならないので、ちょっとイヤでした。
店の前を通るときは、できるだけ店内を見ないようにしよう・・・などと考えながら歩を進めました。
幸か不幸か、店は閉まっていて、店の雨戸に「臨時休業」の紙が貼られていました。理由は知るよしもありません。
内心ホッとしながら店を通り過ぎたとき、前方から小柄なおばぁちゃんが歩いて来るのが見えました。
一銭マチヤのおばぁちゃんでした。けっして幽霊(ボクには幽霊は見えません)などではなく、間違いなく、実在する、生きている一銭マチヤのおばぁちゃんでした。
・・・・・道ゆく他の人には無いのに・・・やっぱり・・・そのおばぁちゃんの頭の上には・・・まだ・・・青白い炎がありました。
・・・・・目を強く閉じ、再び開けて見ても・・・・やっぱりあります。
・・・・・目をこすって、見直しても・・・・青い炎は消えません。
・・・・・それどころか昨日よりはっきり燃えている感じさえしました。
ボクは、何も言えず、何も見えなかったそぶりで、おばぁちゃんとすれ違いました。
・・・・その翌日・・・・おばぁちゃんが、急逝したことを知りました。死の直前まで、歩けるほど元気だった、とも聞きました。
おばぁちゃんの「死」に対して、不思議とボクの中で驚きの感情は湧きませんでした。
ボクが見た青い炎と「死」というものが、因果関係あるのかさえボクには分かりません。
でも、なんかしらの関連がないともいいきれない感覚がありました。
最近話題になったオーラなのかも知れませんが、ボクにはオーラは見えません。
・・・・・何十年と生きてきて、青い炎を見たのは、後にも先にも、その一度きりでした・・・ついこの間までは。
・・・・・正直、青い炎のことなど、すっかり記憶から消えていました。幼いころの夢か幻なのだろう、とさえ思い始めていました・・・・先月までは。
そう、先月、ボクは帰宅途中の車の中から「青い炎」を、また見てしまいました。
一気に記憶が「あの時」にフラッシュバックしました。
帰宅ラッシュの渋滞の車列でした。まだ陽は沈んでなく、明るい街中でした。
交差点の信号待ちで、ボクの車の前に停まったワゴンタイプの黒い軽自動車の中です。
若い小柄な女性がハンドルを握っていました。一人でした。
後ろのウインドウ越しに、はっきりと運転手の横顔と後頭部が見えました。すぐ前の車ですから、距離も離れていません。
さりげなく視線をやったその若い女性の頭の上、中空に、あの青い炎が見えたのです。一銭マチヤのおばぁちゃんの炎と、まったく同じでした。
信号が変わり、黒いワゴン車は発車したのですが、ボクの目は、その青い炎に吸いつけられたままでした。
後ろに並んだ車のクラクションで急かされるまで、ボクの視線は、唖然と青い炎を追い続けていました。
ワゴン車は、次の交差点を右折するようで、ウインカーを点け車線を変更しています。ボクは直進です。
ワゴン車を追っかけて、「青い炎」のことを告げるべきか、正直、迷いました。
話したって、信じる訳がないか・・・まてよ・・・死ぬなんてことはないにしても、「気をつけて運転した方がいい」なんて、余計なアドバイスをしたほうがいいか、などとも考えました。いや死ぬと決まったわけじゃあるまいし・・・いやいや、こんな話、誰も信じないどころか、明らかにヘンな人扱いされるだろうな、とも思いました。なんの根拠もない不吉な話で、他人を余計な不安に陥れるのは人間としてどうなんだろう・・・とも。
・・・でも・・・
結局、ボクは、また「気のせい、気のせい・・・」と呪文のように、自分に言い聞かせて、渋滞の車列に並んだのでした。
・・・でも・・・また、あの、青い炎の呪縛に、しばらくは、からめとられそうなのです。
ましてやセジ(霊力)が高いわけでもサーダカンマリ(生まれ)でもありません。
こんな霊能力ゼロのボクですが、奇妙なモノを目撃したことがあります。
小学校三年のときの出来事ですから、今から数十年前になります。
その日ボクは、クリスマスに親からおこずかいをもらいました。
クリスマスなのにプレゼントではなくおこずかい・・・というのもヘンな話ですが、
たまたまおこずかいをもらったのが、クリスマスの日だった、ということです。
当時はクリスマスのプレゼントどころか、クリスマスパーティを開くことも珍しい時代でした。
とにかく、おこずかいをもらったボクは、その金をにぎりしめ、早速、近所の「一銭マチヤ」(駄菓子屋)に走りました。
その一銭マチヤでは、いつもおばぁちゃんが独りチョコンと座って店番をしていて、その日もおばぁちゃんが店頭にいました。いつものように、にこにこと笑っていました。
ボクは、クジ引きにしようか美味しそうに並んでいる駄菓子にしようか、悩みに悩みながら商品棚を覗き込んでいました。
なかなか決まらなくて、ふと、おばぁちゃんの顔を仰ぎ見たとき、一点に目が釘付けになりました。
にこにこ微笑んでいるおばぁちゃんの頭の上に、なにかがユラユラ揺れているのが見えるのです。
青白い炎のようなものでした。
さっき店に走り込んできたときにはまったく気づかなかったのですが、おばぁちゃんの頭の上に青白い炎のようなものが揺れているのです。
正確にいいますと、おばぁちゃんの頭頂部の上5センチくらい離れてブルーの靄のようなもの見えるのです。
それは、コンビニなどで加湿器から出したばかりの肉まんの上部にブワッと湯気が立ち、収束され、中空に立ち登る感じなのですが、収束された部分が炎のように揺れ、しかも青白いのです。瞬間ではなく、そこにあり続けているのでした。
あまりの突然のことで、ボクはびっくりし、そのまま何も買わずに店を飛び出しました。
店を出たボクは、自分がおかしくなったのだと思い、道ゆく人、すれ違う人、すべての人の頭の上を凝視しました。
しかし、あの青い炎が頭にある人なんて、ほかに誰もいません。普段の、当たり前の日常の景色が広がっているだけでした。青い炎は、見間違いだと自分に言い聞かせ、納得するようにしました。
ただ、怖くて、その日は一銭マチヤには行きませんでした。
翌日・・・・
ボクは友だちと遊ぶために、近所の空き地へ向かいました。
空き地へは、一銭マチヤの前を通らなければならないので、ちょっとイヤでした。
店の前を通るときは、できるだけ店内を見ないようにしよう・・・などと考えながら歩を進めました。
幸か不幸か、店は閉まっていて、店の雨戸に「臨時休業」の紙が貼られていました。理由は知るよしもありません。
内心ホッとしながら店を通り過ぎたとき、前方から小柄なおばぁちゃんが歩いて来るのが見えました。
一銭マチヤのおばぁちゃんでした。けっして幽霊(ボクには幽霊は見えません)などではなく、間違いなく、実在する、生きている一銭マチヤのおばぁちゃんでした。
・・・・・道ゆく他の人には無いのに・・・やっぱり・・・そのおばぁちゃんの頭の上には・・・まだ・・・青白い炎がありました。
・・・・・目を強く閉じ、再び開けて見ても・・・・やっぱりあります。
・・・・・目をこすって、見直しても・・・・青い炎は消えません。
・・・・・それどころか昨日よりはっきり燃えている感じさえしました。
ボクは、何も言えず、何も見えなかったそぶりで、おばぁちゃんとすれ違いました。
・・・・その翌日・・・・おばぁちゃんが、急逝したことを知りました。死の直前まで、歩けるほど元気だった、とも聞きました。
おばぁちゃんの「死」に対して、不思議とボクの中で驚きの感情は湧きませんでした。
ボクが見た青い炎と「死」というものが、因果関係あるのかさえボクには分かりません。
でも、なんかしらの関連がないともいいきれない感覚がありました。
最近話題になったオーラなのかも知れませんが、ボクにはオーラは見えません。
・・・・・何十年と生きてきて、青い炎を見たのは、後にも先にも、その一度きりでした・・・ついこの間までは。
・・・・・正直、青い炎のことなど、すっかり記憶から消えていました。幼いころの夢か幻なのだろう、とさえ思い始めていました・・・・先月までは。
そう、先月、ボクは帰宅途中の車の中から「青い炎」を、また見てしまいました。
一気に記憶が「あの時」にフラッシュバックしました。
帰宅ラッシュの渋滞の車列でした。まだ陽は沈んでなく、明るい街中でした。
交差点の信号待ちで、ボクの車の前に停まったワゴンタイプの黒い軽自動車の中です。
若い小柄な女性がハンドルを握っていました。一人でした。
後ろのウインドウ越しに、はっきりと運転手の横顔と後頭部が見えました。すぐ前の車ですから、距離も離れていません。
さりげなく視線をやったその若い女性の頭の上、中空に、あの青い炎が見えたのです。一銭マチヤのおばぁちゃんの炎と、まったく同じでした。
信号が変わり、黒いワゴン車は発車したのですが、ボクの目は、その青い炎に吸いつけられたままでした。
後ろに並んだ車のクラクションで急かされるまで、ボクの視線は、唖然と青い炎を追い続けていました。
ワゴン車は、次の交差点を右折するようで、ウインカーを点け車線を変更しています。ボクは直進です。
ワゴン車を追っかけて、「青い炎」のことを告げるべきか、正直、迷いました。
話したって、信じる訳がないか・・・まてよ・・・死ぬなんてことはないにしても、「気をつけて運転した方がいい」なんて、余計なアドバイスをしたほうがいいか、などとも考えました。いや死ぬと決まったわけじゃあるまいし・・・いやいや、こんな話、誰も信じないどころか、明らかにヘンな人扱いされるだろうな、とも思いました。なんの根拠もない不吉な話で、他人を余計な不安に陥れるのは人間としてどうなんだろう・・・とも。
・・・でも・・・
結局、ボクは、また「気のせい、気のせい・・・」と呪文のように、自分に言い聞かせて、渋滞の車列に並んだのでした。
・・・でも・・・また、あの、青い炎の呪縛に、しばらくは、からめとられそうなのです。
2011年10月04日 22:52
稀人 --- まれびと ---
今でもあるのか定かではないのですが、ボクの故郷では「あの世の人々」が集い遊ぶ日時と場所が決まっていました。
「ヒューイ」と呼ばれる年に数回の特別な日々で、その日は「生きている人間」は、そこへ近づいてはいけない、と厳格に決まっていました。古くから伝わる暗黙の掟みたいなもので、子供が禁を破ると親に激しく怒られ、中には許しを乞うために豚をつぶして神拝みをする家もありました。だから、子供はもとより大人もけっして近づくことはありませんでした。
ヒューイの場所は、ウタキや古井戸などの拝所や神女が修行する聖域であったりしました。時として磯の一角や浜辺、あるいはムラ外れの畑のときもありました。どういう経緯で誰が決めるのか分かりませんが、ヒューイが決まるとシマンチュ全員に伝達され、皆が知っていました。
ある年の秋。
ヒューイの場所がボクがよく磯遊びをする浜辺にあたりました。
アダンが生い茂る切り立った崖の下の浜で、岩場と砂浜がなだらかに広がっていました。イノープール(礁池)もいくつかあり、サンゴ礁がよく発達していました。浅いわりに貝類や熱帯魚が多く、絶好のシュノーケリングポイントで、とにかくお気に入りの場所でした。
土曜の午後でした。学校から帰宅したボクは、親に隠れ、すぐさま浜辺に向かいました。
快晴の日でした。大潮の干潮時のイノーはそれはそれは美しく、そこで遊ぶ誘惑がヒューイより勝っていました。何より黙っていればバレないと思っていました。ヒューイは迷信だとも思いはじめていました。
崖下の浜辺へは、集落の北の岬を回り込み、海に突き出た天然の岩のトンネルを通り抜けて行きます。
薄暗いトンネルを抜けると、眩むような陽光が降り注いでいました。薄目を開けると、右手の切り立った崖のアダン葉の照り返しと正面の白い砂浜が夏の名残りを感じさせていました。そして、左手の海は午後の太陽を存分に吸収しながら水平線いっぱいに光っていました。
普段の大潮なら、砂浜やイノーの周辺などで磯遊びする人が多いはずですが、人影はまったくありませんでした。人っ子一人いないのです。快晴の浜辺に誰もいないのです。見渡す限りの沈黙でした。
人気のない浜辺で一人遊ぶのは、ちょっと怖いものがありました。人の姿が見えないこともありましたが、人の声や自動車の音、遠くの船や飛行機の音さえ聞こえません・・・人工的な音がすべて消え去ったようで、余計に恐ろしさを増幅させていました。そして、いつしか繰り返す波の音や風に揺れる葉擦れの音に敏感になっていました。
2、30分ほど磯をウロウロしたでしょうか。唐突に「人工的な音」が聞こえてきました。かすかにですが、崖の上から音が響き、徐々にはっきり聞こえるようになりました。横笛や太鼓の調べのようでした。
「あれ、お祝いでもしているのかな?」
ボクは、聴き耳を立てました。音はどうやら、お祝いというよりお祭りの音楽のようでした。。
沖縄の旋律ではなく、本土の夏祭りなどで流れるピーヒャラピーヒャラといった感じです。時折、和太鼓のリズムがドンドンと響きます。
祭りの音楽は、ますます大きくなり、人のざわめきも混じるようになってきました。お祭りの雑踏の、あのざわめきです。たくさんの人がお祭りを楽しんでいるようでした。
・・・次の瞬間、ボクはいきなり恐怖に襲われました。「ヒューイ」のことが頭をよぎったのです。足がすくみ、全身が硬直した感じで動けませんでした。
と、ピーッと甲高い横笛の音が響いたかと思ったら、すべての音が一瞬で止みました。
立ちすくんだまま、崖の上を見ました。
崖上で何かが動いたように見えた瞬間、大きな岩が崩れ落ち、ボクの横に転げ落ちてきました。
我に返ったボクは、来たトンネルを通り抜け、岬を駆け抜け、一目散に逃げ帰りました。
その後、そこでの出来ごとは、親にも友人にも話せませんでした。
・・・・今ではヒューイが、あるのか無くなったのかさえ分かりません。ただ、あの時のあの瞬間、稀人(マレビト)の存在を感じたのだけは確かなのです・・・・
「ヒューイ」と呼ばれる年に数回の特別な日々で、その日は「生きている人間」は、そこへ近づいてはいけない、と厳格に決まっていました。古くから伝わる暗黙の掟みたいなもので、子供が禁を破ると親に激しく怒られ、中には許しを乞うために豚をつぶして神拝みをする家もありました。だから、子供はもとより大人もけっして近づくことはありませんでした。
ヒューイの場所は、ウタキや古井戸などの拝所や神女が修行する聖域であったりしました。時として磯の一角や浜辺、あるいはムラ外れの畑のときもありました。どういう経緯で誰が決めるのか分かりませんが、ヒューイが決まるとシマンチュ全員に伝達され、皆が知っていました。
ある年の秋。
ヒューイの場所がボクがよく磯遊びをする浜辺にあたりました。
アダンが生い茂る切り立った崖の下の浜で、岩場と砂浜がなだらかに広がっていました。イノープール(礁池)もいくつかあり、サンゴ礁がよく発達していました。浅いわりに貝類や熱帯魚が多く、絶好のシュノーケリングポイントで、とにかくお気に入りの場所でした。
土曜の午後でした。学校から帰宅したボクは、親に隠れ、すぐさま浜辺に向かいました。
快晴の日でした。大潮の干潮時のイノーはそれはそれは美しく、そこで遊ぶ誘惑がヒューイより勝っていました。何より黙っていればバレないと思っていました。ヒューイは迷信だとも思いはじめていました。
崖下の浜辺へは、集落の北の岬を回り込み、海に突き出た天然の岩のトンネルを通り抜けて行きます。
薄暗いトンネルを抜けると、眩むような陽光が降り注いでいました。薄目を開けると、右手の切り立った崖のアダン葉の照り返しと正面の白い砂浜が夏の名残りを感じさせていました。そして、左手の海は午後の太陽を存分に吸収しながら水平線いっぱいに光っていました。
普段の大潮なら、砂浜やイノーの周辺などで磯遊びする人が多いはずですが、人影はまったくありませんでした。人っ子一人いないのです。快晴の浜辺に誰もいないのです。見渡す限りの沈黙でした。
人気のない浜辺で一人遊ぶのは、ちょっと怖いものがありました。人の姿が見えないこともありましたが、人の声や自動車の音、遠くの船や飛行機の音さえ聞こえません・・・人工的な音がすべて消え去ったようで、余計に恐ろしさを増幅させていました。そして、いつしか繰り返す波の音や風に揺れる葉擦れの音に敏感になっていました。
2、30分ほど磯をウロウロしたでしょうか。唐突に「人工的な音」が聞こえてきました。かすかにですが、崖の上から音が響き、徐々にはっきり聞こえるようになりました。横笛や太鼓の調べのようでした。
「あれ、お祝いでもしているのかな?」
ボクは、聴き耳を立てました。音はどうやら、お祝いというよりお祭りの音楽のようでした。。
沖縄の旋律ではなく、本土の夏祭りなどで流れるピーヒャラピーヒャラといった感じです。時折、和太鼓のリズムがドンドンと響きます。
祭りの音楽は、ますます大きくなり、人のざわめきも混じるようになってきました。お祭りの雑踏の、あのざわめきです。たくさんの人がお祭りを楽しんでいるようでした。
・・・次の瞬間、ボクはいきなり恐怖に襲われました。「ヒューイ」のことが頭をよぎったのです。足がすくみ、全身が硬直した感じで動けませんでした。
と、ピーッと甲高い横笛の音が響いたかと思ったら、すべての音が一瞬で止みました。
立ちすくんだまま、崖の上を見ました。
崖上で何かが動いたように見えた瞬間、大きな岩が崩れ落ち、ボクの横に転げ落ちてきました。
我に返ったボクは、来たトンネルを通り抜け、岬を駆け抜け、一目散に逃げ帰りました。
その後、そこでの出来ごとは、親にも友人にも話せませんでした。
・・・・今ではヒューイが、あるのか無くなったのかさえ分かりません。ただ、あの時のあの瞬間、稀人(マレビト)の存在を感じたのだけは確かなのです・・・・
2011年09月28日 15:09
言霊 ---ことだま---
古の日本では口から発せられた「言葉」に摩訶不思議な力が秘められている、と信じられてきたそうです。特に平安の時代には「言霊」と呼び、魂が宿るもう一つの生きモノとしてとらえていたようです。それだけに、人の言葉には大切なモノが込められてきたと思います。もちろん、沖縄でもそうでした。
時代が経ち、言葉の力はかなり薄れてきて、最近では政(まつりごと)を司る人の言葉でさえ随分と軽く、薄っぺらなモノになってきた感じさえします。
・・・「言霊」とは、少し違うとは思いますが、こんな経験をしたことがあります。
平成に入って間もなくの年でした。
ボクは、那覇からヤンバルの東海岸にある小さな集落に向かっていました。なだらかな傾斜が海に向かって広がった地域で、広大な赤土の畑いっぱいにパイナップルが植えられていました。これから訪ねるのは、その集落のはずれのKさん宅で、ご高齢のKさんに戦前の集落の話をお聞きするのが目的でした。
Kさんは、つい先日ご主人に先立たれ、お子さんたちもそれぞれに独立なされて、独り暮らしをしているおばあちゃんでした。ただ、隣の集落にお嫁に行った娘さんが毎日訪ねて来てくれるとのことで、生活は悠々自適そのもの。日課の畑仕事が楽しみな元気な方、ということを事前に集落の区長さんから教えてもらっていました。
ボクは、区長さんがハガキに書いて送ってくれた地図を頼りに、Kさん宅を探しました。しかし、なかなか見つけることが出来ません。土地勘がないこともありましたが、人口の少ない割にとても広い集落で、広いパイナップル畑にポツンポツンと家屋が点在し、細い農道で繋がれていました。
なにより集落内にほとんど目印らしい目印が無く、肝心のKさん宅はさらに集落はずれの一軒家ということで隣家も無く、人通りどころか、さっきから車一台も通らない有様でした。ボクは途方に暮れていました。Kさんと会う約束の時間は迫っていました。
「まずいな・・・どうしようか・・・」
焦りはピークに達していました。
「そうだ!」
ボクは、区長さんからもらったハガキの隅っこに鉛筆でKさん宅の電話番号が書いてあることを思い出しました。
急いで鉛筆の電話番号に手持ちのPHSから電話しました。
「もしもし、道に迷ってしまって・・・」
ボクは焦りながら切り出しました。
「・・・・」
返答はありませんでした。ザーッザーッとノイズだけが聞こえます。
「ん?圏外かな?混線?」と思いつつ、PHSに耳を強く押しつけます。
と、ノイズの中でかすかな声が聞こえました。男性の声です。年配者のようでした。
電話の小さなかすれた声は、Kさん宅で娘さんと待っていると言い、家までの道順を丁寧にとつとつと教えてくれました。
・・・・電話の声に導かれながら、ボクはようやくKさん宅にたどり着くことができ、車から降りながら、お礼を伝え受話器を切りました。
お宅では、Kさんと娘さんが待っていてくれました。
「電話で助かりました。どなたですかね? 男の人のようでしたけど、区長さんがいらしているのですか?」
娘さんはちょっと怪訝そうな顔をしましたがすぐに首を振りました。傍らでちょこんと正座しているKさんは静かに微笑んでいます。
その日、区長さんは那覇に所用で出かけているそうで、もちろんKさん宅には来ていません。おかしなことに、Kさん宅の電話は、先日旦那さんが亡くなってから解約し、使えない状態だということでした。
「・・・さっき、たった今、電話で道教えてもらったんですよ。男の人に。あれ? なんで?」
ボクは一瞬狐につままれた感じになりました。
娘さんは戸惑いと困惑した表情でボクを見ています。一方のKさんは、指先を擦りながら伏し目がちにうつむいています。はにかんでいるようにも見えました。それ以上、ボクは何も聞かず詮索はしませんでした。
・・・・夕暮れが近かったので、急いで要件を済ませ、暇乞いをし、Kさん宅を後にしました。
陽がすっかり落ちた58号を南下し帰路につきました。恩納村の熱田あたりだと思います。胸ポケットのPHSが鳴りました。車を路肩に停め、電話に出ました。
「・・・・ありがとう・・・」
低い電波ノイズの中、その一言だけ聴きとれたかと思ったら、電話は切れました。あの道を教えてくれた声と似ていました。
・・・電話の声の主は誰だったのか、いまだに分かりません。後日、区長さんにも確認しましたが区長さんでもありませんでした。ボクの勘違いか、たまたま間違い電話だったかもしれません。ただ、ボクは亡くなったKさんのご主人の「言霊」ではなかったのかと、思います。いや、むしろそうであってほしいとさえ思っているのです・・・・
時代が経ち、言葉の力はかなり薄れてきて、最近では政(まつりごと)を司る人の言葉でさえ随分と軽く、薄っぺらなモノになってきた感じさえします。
・・・「言霊」とは、少し違うとは思いますが、こんな経験をしたことがあります。
平成に入って間もなくの年でした。
ボクは、那覇からヤンバルの東海岸にある小さな集落に向かっていました。なだらかな傾斜が海に向かって広がった地域で、広大な赤土の畑いっぱいにパイナップルが植えられていました。これから訪ねるのは、その集落のはずれのKさん宅で、ご高齢のKさんに戦前の集落の話をお聞きするのが目的でした。
Kさんは、つい先日ご主人に先立たれ、お子さんたちもそれぞれに独立なされて、独り暮らしをしているおばあちゃんでした。ただ、隣の集落にお嫁に行った娘さんが毎日訪ねて来てくれるとのことで、生活は悠々自適そのもの。日課の畑仕事が楽しみな元気な方、ということを事前に集落の区長さんから教えてもらっていました。
ボクは、区長さんがハガキに書いて送ってくれた地図を頼りに、Kさん宅を探しました。しかし、なかなか見つけることが出来ません。土地勘がないこともありましたが、人口の少ない割にとても広い集落で、広いパイナップル畑にポツンポツンと家屋が点在し、細い農道で繋がれていました。
なにより集落内にほとんど目印らしい目印が無く、肝心のKさん宅はさらに集落はずれの一軒家ということで隣家も無く、人通りどころか、さっきから車一台も通らない有様でした。ボクは途方に暮れていました。Kさんと会う約束の時間は迫っていました。
「まずいな・・・どうしようか・・・」
焦りはピークに達していました。
「そうだ!」
ボクは、区長さんからもらったハガキの隅っこに鉛筆でKさん宅の電話番号が書いてあることを思い出しました。
急いで鉛筆の電話番号に手持ちのPHSから電話しました。
「もしもし、道に迷ってしまって・・・」
ボクは焦りながら切り出しました。
「・・・・」
返答はありませんでした。ザーッザーッとノイズだけが聞こえます。
「ん?圏外かな?混線?」と思いつつ、PHSに耳を強く押しつけます。
と、ノイズの中でかすかな声が聞こえました。男性の声です。年配者のようでした。
電話の小さなかすれた声は、Kさん宅で娘さんと待っていると言い、家までの道順を丁寧にとつとつと教えてくれました。
・・・・電話の声に導かれながら、ボクはようやくKさん宅にたどり着くことができ、車から降りながら、お礼を伝え受話器を切りました。
お宅では、Kさんと娘さんが待っていてくれました。
「電話で助かりました。どなたですかね? 男の人のようでしたけど、区長さんがいらしているのですか?」
娘さんはちょっと怪訝そうな顔をしましたがすぐに首を振りました。傍らでちょこんと正座しているKさんは静かに微笑んでいます。
その日、区長さんは那覇に所用で出かけているそうで、もちろんKさん宅には来ていません。おかしなことに、Kさん宅の電話は、先日旦那さんが亡くなってから解約し、使えない状態だということでした。
「・・・さっき、たった今、電話で道教えてもらったんですよ。男の人に。あれ? なんで?」
ボクは一瞬狐につままれた感じになりました。
娘さんは戸惑いと困惑した表情でボクを見ています。一方のKさんは、指先を擦りながら伏し目がちにうつむいています。はにかんでいるようにも見えました。それ以上、ボクは何も聞かず詮索はしませんでした。
・・・・夕暮れが近かったので、急いで要件を済ませ、暇乞いをし、Kさん宅を後にしました。
陽がすっかり落ちた58号を南下し帰路につきました。恩納村の熱田あたりだと思います。胸ポケットのPHSが鳴りました。車を路肩に停め、電話に出ました。
「・・・・ありがとう・・・」
低い電波ノイズの中、その一言だけ聴きとれたかと思ったら、電話は切れました。あの道を教えてくれた声と似ていました。
・・・電話の声の主は誰だったのか、いまだに分かりません。後日、区長さんにも確認しましたが区長さんでもありませんでした。ボクの勘違いか、たまたま間違い電話だったかもしれません。ただ、ボクは亡くなったKさんのご主人の「言霊」ではなかったのかと、思います。いや、むしろそうであってほしいとさえ思っているのです・・・・
2011年09月21日 12:03
人工衛星ウォッチャー
ボクたちの住む地球のはるか上空には、3000とも6000ともいわれる人工衛星が回っているそうです。
その中には、今流行りのGPSのための衛星や気象衛星、放送用のBS衛星などもあり、ボクらの生活に役立っていることは確かでしょう。
ただ、時々、人工衛星がほんとにすべて必要なものかどうか、ふと考えることがあります。
それには、こんな理由があります・・・・・
数年前、ボクは那覇市の波の上近くのファストフード店でちょっと遅い昼食をとっていました。
夏の暑い日でした。
ホットドッグとルートビアの軽い食事を済ませ、時間潰しにファストフード店前のビーチへ下りてみることにしました。仕事着のスーツでしたが、店の駐車場から直接ビーチへ下りる階段があり、ゆっくり歩けば、革靴に砂が入ることはないとビーチへ向かいました。
ビーチへは、階段から砂地を右に折れ、湾岸道路(道路橋)の下を抜けて行くことができたと記憶しています。
平日の昼下がり。ちょっと先の波の上ビーチからは若い歓声が風に乗って聞こえます。海水浴に興じる観光客も多いようでした。
クーラーのよくきいた店内から急に炎天下に出たせいなのか、さっき飲んだルートビアのためなのか、駐車場の階段を下りたときには一気に汗が噴き出していました。汗だくの上、白い砂地の照り返しもきつく、ボクは道路橋下の日陰へ避難することにしました。
ビーチの喧騒とは裏腹に、橋の下には一人の男いるだけでした。痩身の若い男で、タンクトップに短パンにシマゾウリ、真っ黒に日焼けしていました。なぜか立ちつくし、直射日光から隠れるようにして、上空を仰いでいました。
「暑いですね」
ボクは軽く会釈し、ハンカチで汗を拭き拭き言いました。
男はじっと黙ったままで、上空を仰いでいます。
橋下の日陰は海風もあって、涼しく、ボクは汗の引くのを待っていました。ちょっと気まずい空気が漂っていました。
と、唐突に男が話掛けてきました。
「ほら、あれ、見える?」
男は、上空を右手で指差し、左手は日差しを遮るように額の上に乗せたまま、頭だけ振り向いて言います。
上空には、群青の空と白い雲しか見えません。
「橋の三つめの欄干の横から、あの雪だるまみたいな雲・・・ちょうど耳みたいになっているところ?見える?耳のすぐ脇の青空のとこ」
ボクは、男に言われるまま目をこらして、雪だるま雲の耳あたりを凝視しました。
「ね、見えるでしょ?銀色のまぁるい玉。小さいけど」
えっ!と思いつつ、ボクは雲の耳あたりをさらに凝視しました。
驚いたことに、確かに小さいのですが銀色の球体が目視できました。青空にぽつんと銀色の一点が静止しているのです。
「見えます。見えます。何ですか、あれは?まさかUFO?」
ボクは男に聞き返しました。
「ずっと一時間以上動かないから人工衛星だと思うよ。人工衛星だよ。昼間でも結構見つけることできるんだよね」
男は左手で敬礼するように陽を遮りながら見続けています。
「でもさ、アイツらそうやって、いつも監視しているんだよ。俺もそうだけど、みんなをだよ。軍事用のスパイ衛星っていっているけどさ、あんなもの何機も配置して・・・監視されているんだよ、沖縄は。俺が朝から見つけただけで、5機はいるよ5機。ここの上空だけでさ。昨日は7機見つけた。見張られているんだよ。だから俺は、監視の目が届かない橋の下から探すんだよ。見張られるのってイヤだよな・・・」
男がとつとつと語る話は、信ぴょう性があるようで無いようで・・・具体性があるようで無いようで・・・科学的であるようで、無いようで・・・ボクには判断がつきませんでした。
人工衛星ウォッチャーは、那覇から国頭まで移動しながら衛星をチェックし、発見した日時場所を詳細にノートに記して持ち歩いているそうで、ちょっとだけそのノートを見せてもらいました。ボクには読み取れない記号がたくさん記載されていました。ただ、ボクには彼の行動を笑うことができませんでした。
最近は便利さの反面、目に見えない監視社会に不安や疑問が大きくなっていく感じさえします。
・・・・今でも、男は、沖縄の、どこか橋の下、人工衛星の監視の網をくぐりながら、ウォッチしているのでしょうか・・・・・
その中には、今流行りのGPSのための衛星や気象衛星、放送用のBS衛星などもあり、ボクらの生活に役立っていることは確かでしょう。
ただ、時々、人工衛星がほんとにすべて必要なものかどうか、ふと考えることがあります。
それには、こんな理由があります・・・・・
数年前、ボクは那覇市の波の上近くのファストフード店でちょっと遅い昼食をとっていました。
夏の暑い日でした。
ホットドッグとルートビアの軽い食事を済ませ、時間潰しにファストフード店前のビーチへ下りてみることにしました。仕事着のスーツでしたが、店の駐車場から直接ビーチへ下りる階段があり、ゆっくり歩けば、革靴に砂が入ることはないとビーチへ向かいました。
ビーチへは、階段から砂地を右に折れ、湾岸道路(道路橋)の下を抜けて行くことができたと記憶しています。
平日の昼下がり。ちょっと先の波の上ビーチからは若い歓声が風に乗って聞こえます。海水浴に興じる観光客も多いようでした。
クーラーのよくきいた店内から急に炎天下に出たせいなのか、さっき飲んだルートビアのためなのか、駐車場の階段を下りたときには一気に汗が噴き出していました。汗だくの上、白い砂地の照り返しもきつく、ボクは道路橋下の日陰へ避難することにしました。
ビーチの喧騒とは裏腹に、橋の下には一人の男いるだけでした。痩身の若い男で、タンクトップに短パンにシマゾウリ、真っ黒に日焼けしていました。なぜか立ちつくし、直射日光から隠れるようにして、上空を仰いでいました。
「暑いですね」
ボクは軽く会釈し、ハンカチで汗を拭き拭き言いました。
男はじっと黙ったままで、上空を仰いでいます。
橋下の日陰は海風もあって、涼しく、ボクは汗の引くのを待っていました。ちょっと気まずい空気が漂っていました。
と、唐突に男が話掛けてきました。
「ほら、あれ、見える?」
男は、上空を右手で指差し、左手は日差しを遮るように額の上に乗せたまま、頭だけ振り向いて言います。
上空には、群青の空と白い雲しか見えません。
「橋の三つめの欄干の横から、あの雪だるまみたいな雲・・・ちょうど耳みたいになっているところ?見える?耳のすぐ脇の青空のとこ」
ボクは、男に言われるまま目をこらして、雪だるま雲の耳あたりを凝視しました。
「ね、見えるでしょ?銀色のまぁるい玉。小さいけど」
えっ!と思いつつ、ボクは雲の耳あたりをさらに凝視しました。
驚いたことに、確かに小さいのですが銀色の球体が目視できました。青空にぽつんと銀色の一点が静止しているのです。
「見えます。見えます。何ですか、あれは?まさかUFO?」
ボクは男に聞き返しました。
「ずっと一時間以上動かないから人工衛星だと思うよ。人工衛星だよ。昼間でも結構見つけることできるんだよね」
男は左手で敬礼するように陽を遮りながら見続けています。
「でもさ、アイツらそうやって、いつも監視しているんだよ。俺もそうだけど、みんなをだよ。軍事用のスパイ衛星っていっているけどさ、あんなもの何機も配置して・・・監視されているんだよ、沖縄は。俺が朝から見つけただけで、5機はいるよ5機。ここの上空だけでさ。昨日は7機見つけた。見張られているんだよ。だから俺は、監視の目が届かない橋の下から探すんだよ。見張られるのってイヤだよな・・・」
男がとつとつと語る話は、信ぴょう性があるようで無いようで・・・具体性があるようで無いようで・・・科学的であるようで、無いようで・・・ボクには判断がつきませんでした。
人工衛星ウォッチャーは、那覇から国頭まで移動しながら衛星をチェックし、発見した日時場所を詳細にノートに記して持ち歩いているそうで、ちょっとだけそのノートを見せてもらいました。ボクには読み取れない記号がたくさん記載されていました。ただ、ボクには彼の行動を笑うことができませんでした。
最近は便利さの反面、目に見えない監視社会に不安や疑問が大きくなっていく感じさえします。
・・・・今でも、男は、沖縄の、どこか橋の下、人工衛星の監視の網をくぐりながら、ウォッチしているのでしょうか・・・・・
2011年09月16日 19:23
火魂 -- ヒダマ --
ボクは別段、怪奇物やオカルト、幽霊といった非現実的なものに興味はありません。
興味はないのですが、ボクが体験したり、遭遇した事象の中でどうしても理屈では説明のつかないことがあります。
以前、遭遇した火魂も、そんな説明のつかないモノのひとつです。
当時、ボクは田舎の県立高校に通っていました。
学校が終わるとそのまま帰宅する、いわゆる「帰宅部」の学生で、決まって下校時に合わせた定時のバスに乗って帰る、という毎日を送っていました。
・・・夏休みが始まったある年の夏。
ボクは、夏期講習でうんざりしながらも、いつもより一時間ほど早い帰宅バスで帰路につき、終点のバスターミナルから自宅まで15分ほどの道のりを歩いていました。青空に夕焼の橙色がほんの少し滲みはじめた時刻ですから、18時前後だと思います。まだ十分に明るく、空気は澄んでいました。
ターミナルから、長い坂道を歩き、坂を上り切ったところにボクの家はあります。田舎では珍しく、坂の途中や坂の上に家々が密集した集落で、細い路地沿いに数百軒が寄り添うように建っていました。
坂道を登り切り、自宅の屋根が百メートルほど前方に見えたとき、いつもと違う光景にボクは違和感を覚えました。
屋根の上に人が立っているのです。一軒だけではなく、数十軒ほどの屋根の上に人々が立ち、手に手に竿や棒きれを持って、空に向かって振り回しているのです。赤瓦屋根の人などは、かなり危険な体勢で踏ん張り長い竿を振り回しているのです。
「なんで?」
ボクは、傍らで腕組みして傍観している近所の老人に訊ねました。
「火魂・・・人魂が飛んでる」
老人は眉をひそめて言い、西の空を指差しました。
指し示す方角に視線を移したボクは唖然としました。陽が少し傾き、茜がかった西の空にぼんやりと火の球が浮かんでは、ふわふわと屋根すれすれを移動していました。目測で直径1メートルたらずの球形が、燃えながらゆっくりと移動しているのです。色は、ちょうど枯れススキを燃やしたほどの色で、煙は見えなかったと思います。燃えているのですが、形が小さくなりませんでした。
ボクの田舎では、火魂(人魂)が落ちた、あるいは入った家には不幸が訪れたり死人が出る、という言い伝えがあることは知っていました。ただそれは迷信だと信じていました。高校生にもなれば、燐の自然発火や昆虫の集団飛行、プラズマ現象、集団催眠なども知識としては知っていました。ただ、目の前の「火の玉」は、そのどれでもなく、まぎれもないホントの「火魂」なのです。集落の人が集団で催眠状態に陥って、同じ幻覚を見ていることなど絶対にありえません。
映画やテレビで見る「人魂」は、青白い炎が尾を引きながら、ゆらゆらと飛ぶのですが、目前の火魂は球形(完全な球形に見えました)で、燃やした鉄球を空中に放り投げた感じでした。しかもゆっくりと風に流されるようにランダムに飛んでいるのです。
そして、火魂は屋根に人の登っていないある家に吸い込まれるように消えました。偶然かもしれませんが、その家の方(かなりのご高齢でした)が、その日亡くなりました。
驚いたことに、翌日の同時刻ごろにも火魂は現れましたが、どの家にも落ちることなく、東の畑の広がる方向にゆらゆらと去って行きました。そのあとは、一度として現れたことがありません。
後日、シマのおじぃに「火魂(人魂)」の話をきいたところ、
「昔は、もっと当たり前のように現れ、人が連れていかれた(死んだ)。だから家族を守るため、みなん必死に屋根に登り、火魂を近づけないように竿を振った」そうだ。
・・・あの火魂は、今もどこか彷徨っているのだろうか・・・
2011年09月14日 17:17
渡り
寒露の節句が近付くと、思い出すことがあります。
あれは、昭和も終わりのころでした。
ボクらは、沖縄本島南部の大里のサトウキビ畑の中にいました。
時刻は、深夜の一時半を回ったころでした。
・・・事の発端は、その二日前に遡ります。
昭和の中ごろまで、沖縄では寒露の季節になると、自然の風物詩・・・とでもいいましょうか・・・サシバ(沖縄では「タカ」と呼ぶ地域も多いようです)の渡りが毎年見られました。しかし、昭和の終わりごろにはめっきりその数が減って、寒露の季節になってもサシバの姿はなかなか目にする機会がありませんでした。
そんな折、友人の一人が、大里あたりを車で走行中、サシバの渡りを上空で見た、という情報を持ってきました。
それが二日前でした。その翌日の夕刻、ボクは仕事帰りに大里へ向かいました。もちろん、友人が目撃したというサシバの渡りを確認しにです。
いました。数にして4、50羽ほどのサシバの群れが、大里の山林のはるか上空をゆっくりと滑空し、スパイラルな渦を描くように舞っているのが見えました。渦のように舞うのは、その下を俯瞰しつつ、その日のねぐらを探しているのに違いありません。
案の定、その日サシバは一羽、一羽と大里の山に墜落するように落ちていきました。
・・・・・・ そして翌日の夕刻。
ボクは、友人三人と大里の山林が望める農道に車を停め、陽が落ちるのを待っていました。
目的は、渡りの途中のサシバの姿をカメラにおさめること。できれば、夜間、集団で休んでいる(眠っている)様子を撮影できれば・・・というものでした。
その日の夕方、北西の空からサシバの群れが現れ、大里の上空で大きな円を描き飛び、そして、螺旋状に旋回したと思ったら、次々に山中に吸い込まれるように落ちていきました。
サシバが落ちたばかりの山で人の気配や物音をたてると、敏感なサシバは一斉に飛び立ち、二度と戻らないことが多いため、ボクらはサシバが完全に寝静まる夜半までサトウキビのあぜ道で待機していました。山は見えますが、山に落ちたサシバの姿は遠くて確認できませんでした。
・・・・ そして、冒頭の時間。ボクらは意を決して山に向かいました。
山林は、北側が崖、ほかの三方がサトウキビに囲まれていました。ほとんど雑木林の山までは道などありませんでした。サトウキビ畑を一直線に突っ切り、山に向かいました。月明かりも、星もない曇天の空でした。あたりに街灯などあるわけがなく、真っ暗。手元の懐中電灯だけが頼りでした。前方にぼんやりと浮かぶ山林の影が重々しく、サトウキビ畑の中は息苦しい湿気が充満していました。
「ハブには気をつけようなぁ」と傍らの友人が言います。
「ああ」と応えたっきり、みんな押し黙って深夜のサトウキビ畑を進みます。
収穫前のサトウキビは、背丈も高く、粗めの籠を織り込んだように入り乱れて前方をふさいでいました。しかも足元は湿気と入り組んだサトウキビの根っこで滑りやすく、かなり歩きづらい状況でした。足をとられては転び、何度か手をついては転び・・・とボクらは進んで行きました。
サシバの宿営地までは、おもいのほか遠く、なかなかたどり着けませんでした。
と、いきなり前方の闇から人影が現れました。音もなく、突然現れたのでした。制服をきちんと着た警官でした。
あまりの突然の出現にボクらは驚き、言葉を失い、立ちすくみました。
「何をしているのですか?」
警官はボクらに尋ねました。いたって冷静な優しい口調でした。帽子を眼深にかぶっているので、表情は伺い知れません。
ボクらは事情を説明し、身分証を提示しました。
「そうですか・・・。山の入り口は少し右手に行った突き当たりです。お気をつけて・・・」
そう言って、口元に少し笑みをたたえ、敬礼して警官はサトウキビ畑の闇へ去って行きました。
「警官?・・・今時分なあ? どこから来たんだろう? ここらに道なんかないよな」
「パトカーなんかいたか? いや、車の音もしなかった・・・はず・・・」
「制服ぜんぜん濡れていなかったよね。こんなウージ畑(サトウキビ畑)で。靴も革靴で、キチンとしすぎじゃないか?」
「懐中電灯も持っていなかったよ? なんで一人なんだ・・・」
ボクたちは口々に言葉を発した。
そして、それまで押し黙っていた友人Zが、警官の消えた闇を懐中電灯で照らしながらポツリと言った。
「俺には警官の制服には見えなかった。あれは軍服だよ。おじいの遺影の軍服と同じだった」
その夜、サシバの撮影どころではなく、ボクたちは一目散にサトウキビ畑を後にした。
・・・・あの、サトウキビ畑の男はいったい・・・・
あれは、昭和も終わりのころでした。
ボクらは、沖縄本島南部の大里のサトウキビ畑の中にいました。
時刻は、深夜の一時半を回ったころでした。
・・・事の発端は、その二日前に遡ります。
昭和の中ごろまで、沖縄では寒露の季節になると、自然の風物詩・・・とでもいいましょうか・・・サシバ(沖縄では「タカ」と呼ぶ地域も多いようです)の渡りが毎年見られました。しかし、昭和の終わりごろにはめっきりその数が減って、寒露の季節になってもサシバの姿はなかなか目にする機会がありませんでした。
そんな折、友人の一人が、大里あたりを車で走行中、サシバの渡りを上空で見た、という情報を持ってきました。
それが二日前でした。その翌日の夕刻、ボクは仕事帰りに大里へ向かいました。もちろん、友人が目撃したというサシバの渡りを確認しにです。
いました。数にして4、50羽ほどのサシバの群れが、大里の山林のはるか上空をゆっくりと滑空し、スパイラルな渦を描くように舞っているのが見えました。渦のように舞うのは、その下を俯瞰しつつ、その日のねぐらを探しているのに違いありません。
案の定、その日サシバは一羽、一羽と大里の山に墜落するように落ちていきました。
・・・・・・ そして翌日の夕刻。
ボクは、友人三人と大里の山林が望める農道に車を停め、陽が落ちるのを待っていました。
目的は、渡りの途中のサシバの姿をカメラにおさめること。できれば、夜間、集団で休んでいる(眠っている)様子を撮影できれば・・・というものでした。
その日の夕方、北西の空からサシバの群れが現れ、大里の上空で大きな円を描き飛び、そして、螺旋状に旋回したと思ったら、次々に山中に吸い込まれるように落ちていきました。
サシバが落ちたばかりの山で人の気配や物音をたてると、敏感なサシバは一斉に飛び立ち、二度と戻らないことが多いため、ボクらはサシバが完全に寝静まる夜半までサトウキビのあぜ道で待機していました。山は見えますが、山に落ちたサシバの姿は遠くて確認できませんでした。
・・・・ そして、冒頭の時間。ボクらは意を決して山に向かいました。
山林は、北側が崖、ほかの三方がサトウキビに囲まれていました。ほとんど雑木林の山までは道などありませんでした。サトウキビ畑を一直線に突っ切り、山に向かいました。月明かりも、星もない曇天の空でした。あたりに街灯などあるわけがなく、真っ暗。手元の懐中電灯だけが頼りでした。前方にぼんやりと浮かぶ山林の影が重々しく、サトウキビ畑の中は息苦しい湿気が充満していました。
「ハブには気をつけようなぁ」と傍らの友人が言います。
「ああ」と応えたっきり、みんな押し黙って深夜のサトウキビ畑を進みます。
収穫前のサトウキビは、背丈も高く、粗めの籠を織り込んだように入り乱れて前方をふさいでいました。しかも足元は湿気と入り組んだサトウキビの根っこで滑りやすく、かなり歩きづらい状況でした。足をとられては転び、何度か手をついては転び・・・とボクらは進んで行きました。
サシバの宿営地までは、おもいのほか遠く、なかなかたどり着けませんでした。
と、いきなり前方の闇から人影が現れました。音もなく、突然現れたのでした。制服をきちんと着た警官でした。
あまりの突然の出現にボクらは驚き、言葉を失い、立ちすくみました。
「何をしているのですか?」
警官はボクらに尋ねました。いたって冷静な優しい口調でした。帽子を眼深にかぶっているので、表情は伺い知れません。
ボクらは事情を説明し、身分証を提示しました。
「そうですか・・・。山の入り口は少し右手に行った突き当たりです。お気をつけて・・・」
そう言って、口元に少し笑みをたたえ、敬礼して警官はサトウキビ畑の闇へ去って行きました。
「警官?・・・今時分なあ? どこから来たんだろう? ここらに道なんかないよな」
「パトカーなんかいたか? いや、車の音もしなかった・・・はず・・・」
「制服ぜんぜん濡れていなかったよね。こんなウージ畑(サトウキビ畑)で。靴も革靴で、キチンとしすぎじゃないか?」
「懐中電灯も持っていなかったよ? なんで一人なんだ・・・」
ボクたちは口々に言葉を発した。
そして、それまで押し黙っていた友人Zが、警官の消えた闇を懐中電灯で照らしながらポツリと言った。
「俺には警官の制服には見えなかった。あれは軍服だよ。おじいの遺影の軍服と同じだった」
その夜、サシバの撮影どころではなく、ボクたちは一目散にサトウキビ畑を後にした。
・・・・あの、サトウキビ畑の男はいったい・・・・
2011年09月12日 14:57
光る海
ウミホタルと関係があるのかどうか分かりませんが、神秘的な現象に遭遇したことがあります。
夜釣りや、ナイトダイビングが好きな方ならご存じだと思いますが、夜の海ではキラキラと光るモノがたまにいます。
たとえば、釣り糸を手繰り寄せるとき餌に付いたナニかが光ったり、水面を揺らすテグスやウキの刺激で細い光の線が見えたり、夜の海上を疾走する船のしぶきの中で光るものが見えたりします。
そのほとんどは夜光虫やウミホタルなどの水生生物だと思われますが、光は弱く、それほど広範囲に光ることはありません。
・・・強い台風がデイゴの季節に襲来した年の夏。
その年の夏は、台風が去ってからというもの、雨が一向に降らず、ラジオでは渇水化対策や計画断水、干ばつ・・・といった話題が毎日流れ、サトウキビの立ち枯れも深刻になっていました。何十年振りかに雨乞いの儀式をどこかの集落がやる、といったニュースが取り上げられるほどの乾き切った夏でした。
乾いた陸に呼応するように、海ではベタ凪が続き、海水温もいつもの年よりずっと高かった気がします。水温があまりに高くなると魚が沖や海底深く逃げるのか、磯釣りでは魚がまったく釣れなくなっていました。
そんなこともあって、ボクらは知人のサバニを借りて、夜釣りに出掛けました。いつもはわざわざ行くことのない深場の離れ瀬。その瀬に投錨し、潮の流れに合わせてアンカーのロープを流しながら釣ることにしました。
五時間は粘ったでしょうか、時間は深夜の二時を回っていました。釣果は、雑魚が三匹という散々な結果で、ボクらは港に引き返すことにしました。
うっすらとした星明りに島影がぼんやりと浮かんでいました。遠く港のブイの赤い光がゆらゆら見えます。距離にして五キロは離れていたと思います。
ブイの赤い光を目印に、帰港の船を走らせました。深夜のベタ凪はコールタールのように黒く、それを切り裂くようにサバニの舳先が進んでいきました。ときどき、漆黒の水面に跳ねたしぶきの中の夜光虫が青く光ってはじけていました。
夜光虫の光は、ちょうど舳先の波をかき分けるしぶきの付近に多く、船が水面を切るたびに新しい光を生み出しているようでした。
ぼんやりしていた黒い島影の輪郭が、はっきり確認できるまで近づいたとき、前方の黒い海面が淡く光っているのが見えました。さらに船を進めると、青白い光は思いのほか広い範囲で光っています。
船のエンジンのスロットを絞り、減速させましたが船はすーっと光の中に滑り込むように入っていきました。驚いたことに、水面だけではなく、水中数メートル先まで光っているではありませんか。光の正体は分かりません。見えないのです。いや、光は見えるのですが、光っているモノが見えないのです。夜光虫の大群かもしれませんが、船上からは確認することはできませんでした。魚の姿はありませんでした。
一面漆黒の海のただ中、船の周り直径30メートルほどの海面だけが「光の海」になっているのです。
その後、光は周囲の闇に溶けるように徐々に薄くなり、ついにはまったく消えてなくなりました。
不思議と得体の知れない怖さより、その幻想的な美しさに驚いたことを今でもはっきりと覚えています。
あれから、一度として光る海をボクは見たことがありません。
あの「光る海」はいったい・・・・
夜釣りや、ナイトダイビングが好きな方ならご存じだと思いますが、夜の海ではキラキラと光るモノがたまにいます。
たとえば、釣り糸を手繰り寄せるとき餌に付いたナニかが光ったり、水面を揺らすテグスやウキの刺激で細い光の線が見えたり、夜の海上を疾走する船のしぶきの中で光るものが見えたりします。
そのほとんどは夜光虫やウミホタルなどの水生生物だと思われますが、光は弱く、それほど広範囲に光ることはありません。
・・・強い台風がデイゴの季節に襲来した年の夏。
その年の夏は、台風が去ってからというもの、雨が一向に降らず、ラジオでは渇水化対策や計画断水、干ばつ・・・といった話題が毎日流れ、サトウキビの立ち枯れも深刻になっていました。何十年振りかに雨乞いの儀式をどこかの集落がやる、といったニュースが取り上げられるほどの乾き切った夏でした。
乾いた陸に呼応するように、海ではベタ凪が続き、海水温もいつもの年よりずっと高かった気がします。水温があまりに高くなると魚が沖や海底深く逃げるのか、磯釣りでは魚がまったく釣れなくなっていました。
そんなこともあって、ボクらは知人のサバニを借りて、夜釣りに出掛けました。いつもはわざわざ行くことのない深場の離れ瀬。その瀬に投錨し、潮の流れに合わせてアンカーのロープを流しながら釣ることにしました。
五時間は粘ったでしょうか、時間は深夜の二時を回っていました。釣果は、雑魚が三匹という散々な結果で、ボクらは港に引き返すことにしました。
うっすらとした星明りに島影がぼんやりと浮かんでいました。遠く港のブイの赤い光がゆらゆら見えます。距離にして五キロは離れていたと思います。
ブイの赤い光を目印に、帰港の船を走らせました。深夜のベタ凪はコールタールのように黒く、それを切り裂くようにサバニの舳先が進んでいきました。ときどき、漆黒の水面に跳ねたしぶきの中の夜光虫が青く光ってはじけていました。
夜光虫の光は、ちょうど舳先の波をかき分けるしぶきの付近に多く、船が水面を切るたびに新しい光を生み出しているようでした。
ぼんやりしていた黒い島影の輪郭が、はっきり確認できるまで近づいたとき、前方の黒い海面が淡く光っているのが見えました。さらに船を進めると、青白い光は思いのほか広い範囲で光っています。
船のエンジンのスロットを絞り、減速させましたが船はすーっと光の中に滑り込むように入っていきました。驚いたことに、水面だけではなく、水中数メートル先まで光っているではありませんか。光の正体は分かりません。見えないのです。いや、光は見えるのですが、光っているモノが見えないのです。夜光虫の大群かもしれませんが、船上からは確認することはできませんでした。魚の姿はありませんでした。
一面漆黒の海のただ中、船の周り直径30メートルほどの海面だけが「光の海」になっているのです。
その後、光は周囲の闇に溶けるように徐々に薄くなり、ついにはまったく消えてなくなりました。
不思議と得体の知れない怖さより、その幻想的な美しさに驚いたことを今でもはっきりと覚えています。
あれから、一度として光る海をボクは見たことがありません。
あの「光る海」はいったい・・・・
2011年09月09日 15:13
虹の端
レインボー・ウォッチャーさんという方がボクのブログを訪れてくれたようです。
どうもありがとう。「月虹」についてのコメントが寄せられていて、素直な文章の端々に優しそうなお人柄が感じられました。
虹について、実はちょっと不思議な体験を二度ほどしています。
一度は、5、6年前だと思います。
ちょうど豊見城市の与根大橋が開通したばかりのころで、ボクは那覇の瀬長島方面から糸満向けに大橋を車で渡ろうとしていました。平日の昼下がり、走行する車はさほど多くはありません。
うりずんの頃で、車窓からは初夏の柔らかい海風が吹き込んでいました。
与根大橋は、最上部あたりまでゆるやかな傾斜になっていて、上部からゆったりとカーブし豊崎へと下っています。
橋に差し掛かると、右手のゴルフ場のグリーンにモクマオウの影がくっきり落ちているのが見えました。
「もう、夏の日差しなのだな」とボクは思いました。
グリーンから橋の前方に目を移すと、大きな虹が橋の上空に架かっていました。初夏の青空に、くっきりと虹が架かっているのです。フロントガラスに水滴がついていないので、上空に細かい雨のカタブイがあったのだと思います。
真っ青な空に鮮やかな虹です。ちょっと得したようで、うれしくなりました。
橋の頂上に向かうにつけ、虹が徐々に大きく、よりはっきりと見えるようになっていきました。虹は近づけるものだと感心しつつ、ゆるやかなカーブに差し掛かりました。上空の七色のカーテンは益々接近し、ついには目前まで迫ってきているではありませんか。
うれしい、というより不思議な感じがし、そのまま虹の端に車ごと入って、一瞬白っぽく見えたかと思ったら、虹を突き抜けていました。
-----そう、ボクは虹の端に入ったことがあるのです。
虹の端には金の壺(宝物)を見つけることができる、という言い伝えがあるそうですが、ボクは金の壺を見つけることは出来ませんでした。でも、虹を突き抜けた豊崎で見つけた小さな公園が「虹公園」という名前であることを知り、ちょっとラッキーになった気はしましたけどね。
ちなみに、もう一つの「虹」の話は、いつかまた。
どうもありがとう。「月虹」についてのコメントが寄せられていて、素直な文章の端々に優しそうなお人柄が感じられました。
虹について、実はちょっと不思議な体験を二度ほどしています。
一度は、5、6年前だと思います。
ちょうど豊見城市の与根大橋が開通したばかりのころで、ボクは那覇の瀬長島方面から糸満向けに大橋を車で渡ろうとしていました。平日の昼下がり、走行する車はさほど多くはありません。
うりずんの頃で、車窓からは初夏の柔らかい海風が吹き込んでいました。
与根大橋は、最上部あたりまでゆるやかな傾斜になっていて、上部からゆったりとカーブし豊崎へと下っています。
橋に差し掛かると、右手のゴルフ場のグリーンにモクマオウの影がくっきり落ちているのが見えました。
「もう、夏の日差しなのだな」とボクは思いました。
グリーンから橋の前方に目を移すと、大きな虹が橋の上空に架かっていました。初夏の青空に、くっきりと虹が架かっているのです。フロントガラスに水滴がついていないので、上空に細かい雨のカタブイがあったのだと思います。
真っ青な空に鮮やかな虹です。ちょっと得したようで、うれしくなりました。
橋の頂上に向かうにつけ、虹が徐々に大きく、よりはっきりと見えるようになっていきました。虹は近づけるものだと感心しつつ、ゆるやかなカーブに差し掛かりました。上空の七色のカーテンは益々接近し、ついには目前まで迫ってきているではありませんか。
うれしい、というより不思議な感じがし、そのまま虹の端に車ごと入って、一瞬白っぽく見えたかと思ったら、虹を突き抜けていました。
-----そう、ボクは虹の端に入ったことがあるのです。
虹の端には金の壺(宝物)を見つけることができる、という言い伝えがあるそうですが、ボクは金の壺を見つけることは出来ませんでした。でも、虹を突き抜けた豊崎で見つけた小さな公園が「虹公園」という名前であることを知り、ちょっとラッキーになった気はしましたけどね。
ちなみに、もう一つの「虹」の話は、いつかまた。
2011年09月08日 16:46
光るメシ
ウミホタルをご存じでしょうか?
東京湾アクアラインの施設ではなく、海に棲息する甲殻類の仲間の方のウミホタルです。
学名は、Vargula hilgendorfii となにやら物々しい名前ですが、ミジンコにそっくりな海洋微生物でたいていの海にはいます。沖縄でも海中道路周辺や漁港など、あまりきれいではない砂地や泥地の海底で多く見られます。
ウミホタルは、雑食・・・というか、ほとんど肉食で貪欲。生きたゴカイなどを襲って食べることもあるそうです。ですから、捕獲するときは、血のしたたるレバー(鳥とか豚など)や脂身のついた肉などを餌に捕まえます。捕まえるといっても、口の広い空き瓶に餌を入れ、海底に放り投げておけば勝手にワラワラと肉片に食いついてきます。
汚い泥地に悪食・・・こう書くと何やら獰猛なエイリアンのようですが、ウミホタルにはそれらを超越する美しさが秘められているのです。
ウミホタルを集め、刺激を与えると・・・それはそれは、信じられないくらい美しいコバルトブルーの光を発するのです。しかも数分もの間。また、ウミホタルを集めて乾燥させ(甲殻類ですから可能なのです)、それを砕いて水をかけると、ボワーっとものすごい勢いでブルーに発光します。
無毒で人体には影響ないようですが、ボクはまだ食べたことはありません。
いつかは、ご飯のフリカケにして、光る銀シャリで食べようと思っています。
食後に口の中がコバルトブルーに輝いているヤツを見かけたら、それはきっとボクですね。
東京湾アクアラインの施設ではなく、海に棲息する甲殻類の仲間の方のウミホタルです。
学名は、Vargula hilgendorfii となにやら物々しい名前ですが、ミジンコにそっくりな海洋微生物でたいていの海にはいます。沖縄でも海中道路周辺や漁港など、あまりきれいではない砂地や泥地の海底で多く見られます。
ウミホタルは、雑食・・・というか、ほとんど肉食で貪欲。生きたゴカイなどを襲って食べることもあるそうです。ですから、捕獲するときは、血のしたたるレバー(鳥とか豚など)や脂身のついた肉などを餌に捕まえます。捕まえるといっても、口の広い空き瓶に餌を入れ、海底に放り投げておけば勝手にワラワラと肉片に食いついてきます。
汚い泥地に悪食・・・こう書くと何やら獰猛なエイリアンのようですが、ウミホタルにはそれらを超越する美しさが秘められているのです。
ウミホタルを集め、刺激を与えると・・・それはそれは、信じられないくらい美しいコバルトブルーの光を発するのです。しかも数分もの間。また、ウミホタルを集めて乾燥させ(甲殻類ですから可能なのです)、それを砕いて水をかけると、ボワーっとものすごい勢いでブルーに発光します。
無毒で人体には影響ないようですが、ボクはまだ食べたことはありません。
いつかは、ご飯のフリカケにして、光る銀シャリで食べようと思っています。
食後に口の中がコバルトブルーに輝いているヤツを見かけたら、それはきっとボクですね。
2011年09月07日 17:32
月虹--げっこう
地球温暖化が着実に進んでいるのだろうか、夏の暑さが年毎に厳しさを増している気がします。
今年の沖縄は亜熱帯どころか、もはや熱帯の気候にさえ思えますね。はい。
ちょっと前なら夏の風物詩のような「片降り(カタブイ)」も、もはや赤道直下の「スコール」の様相で、打ちつける雨粒の大きさや勢いは半端じゃない。痛いくらい。
カタブイがスコールに変わったからでしょうか、虹がくっきりと鮮やかになったように感じます。ぼやっとした淡い虹色がビビッドカラーになった感じ。日光が強くなったのかな?
虹は太陽の光が雨粒などの中空のスクリーンに反射してできる自然現象ですが、実は太陽の沈んだ夜でも虹が架かることがあります。太陽光にかわりに、月の光で出来る夜の虹----------月虹(げっこう)というそうです。
光の少ない夜中に架かる虹なので、めったに見ることはできない上、気象条件や地域に大きく左右されるようです。目撃するための条件を強いて言えば、南海の島・満月・快晴のカタブイが必須条件かな。
ハワイのマウイ島などが、「月虹がよく観測される場所」らしいのだが、そこでも目にするのは珍しく、運よく月虹を見た者は「幸せが訪れる」とのジンクスもあるそうです。
で、なんとなんと沖縄では意外に月虹が見えます。
夜釣りの好きなボクは、3回も目撃したことがあります。ええ。
もっとも「幸せ」は、まだ訪れていませんがね。
今年の沖縄は亜熱帯どころか、もはや熱帯の気候にさえ思えますね。はい。
ちょっと前なら夏の風物詩のような「片降り(カタブイ)」も、もはや赤道直下の「スコール」の様相で、打ちつける雨粒の大きさや勢いは半端じゃない。痛いくらい。
カタブイがスコールに変わったからでしょうか、虹がくっきりと鮮やかになったように感じます。ぼやっとした淡い虹色がビビッドカラーになった感じ。日光が強くなったのかな?
虹は太陽の光が雨粒などの中空のスクリーンに反射してできる自然現象ですが、実は太陽の沈んだ夜でも虹が架かることがあります。太陽光にかわりに、月の光で出来る夜の虹----------月虹(げっこう)というそうです。
光の少ない夜中に架かる虹なので、めったに見ることはできない上、気象条件や地域に大きく左右されるようです。目撃するための条件を強いて言えば、南海の島・満月・快晴のカタブイが必須条件かな。
ハワイのマウイ島などが、「月虹がよく観測される場所」らしいのだが、そこでも目にするのは珍しく、運よく月虹を見た者は「幸せが訪れる」とのジンクスもあるそうです。
で、なんとなんと沖縄では意外に月虹が見えます。
夜釣りの好きなボクは、3回も目撃したことがあります。ええ。
もっとも「幸せ」は、まだ訪れていませんがね。
2011年07月27日 14:38
足跡
メタボ対策にウォーキングをはじめて半年になる。
ウォーキングのコースは、近所の公園からスタートし、港沿いの歩道を防波堤までまっすぐ歩き、突き当たった防波堤を海をチラチラ眺めながら進む、というお決まりのコースだ。時間にして一時間。直射日光の厳しい今どきは、陽が傾き、ほんの少し日差しが和らいだ時間帯に歩いている。
珍しく、ザーッと夕立が走った木曜日の翌日・・・・・
その日は、朝からピーカンで、昨夕の夕立がなかったかのように道路は干上がっていた。夕方の公園では花壇の土も木々の葉も強烈な日差しで萎れ、乾ききっていた。
いつものように軽いストレッチを済ませ、ウォーキングを開始した。
と、公園を出発し10メートルほど歩いたところで、歩道に足跡があるのに気付いた。
赤土の足跡で、足裏の形から素足であることが推察された。22センチほどのサイズの足跡は幅が細く、どうやら子供ではなく女性のようだ。
「べっちょり赤土を付けちゃったようだな。昨日の夕立だな。公園の運動場かな・・・」
ボクは勝手に推測しながら歩いた。
足跡は、ボクのウォーキングコースと並走して進んでいた。
「よほど土にハマったのかな・・・まだ足跡続いているもん・・・」
50メートルほど歩いたが、赤土の足跡は、まだくっきりと見える。歩幅も狭いので、小柄の女性かもしれない・・・どうして裸足なのかな・・・どこまで行くのかな・・・などと想像しながらボクは歩を進めた。
歩きはじめて4分ほど経過した。距離で300メートルは歩いたかな。赤い足跡はまだ続いていた。かすかに赤土は薄れているものの300メートルも足跡が残るものなのか・・・ボクはちょっと気になった。
もうすぐ突き当たりの防波堤だ。公園から防波堤までは優に1キロメートルはあるはずだ。
・・・まだ赤い足跡は続いていた。正確にいうと、ボクはもう「赤い足跡を追っていた」。明らかに「ヘン」だ。赤土の痕跡がそんな長距離残るとは思えないし、素足で熱いコンクリートの歩道を何キロも歩くことも考えにくい。
足跡は防波堤で突き当たり、ボクのいつものコースを並走するように、防波堤沿いを北に向かっている。もう2キロ以上は進んだはずだ。
ボクの頭は、いつの間にか赤い足跡の興味と得体の知れない不安と足跡のゴールの確認でいっぱいになっていた。
いつも、チラチラ眺める海もその日は目もくれず、足跡に集中し歩いた。
・・・と、防波堤の、なんの変哲もない場所で足跡は忽然と無くなっていた。進行方向を変えたでもなく、踵を返すのでもなく、休むのでもなく・・・歩行中に消えた・・・感じなのだ。
あれれ・・・・ボクはストレッチをするふりして歩を止め、足跡の消えた一帯をそれとなく観察した。が、やっぱりなんにもない。鑑識風にいうと、現場に痕跡も物証もない、のだ。
翌日の土曜日。もちろん歩いた。足跡はしっかり残っていた。そして、あくる日の日曜日、赤い足跡は、なぜかすっかり無くなっていた。
・・・・あの足跡は、いったい・・・・
ウォーキングのコースは、近所の公園からスタートし、港沿いの歩道を防波堤までまっすぐ歩き、突き当たった防波堤を海をチラチラ眺めながら進む、というお決まりのコースだ。時間にして一時間。直射日光の厳しい今どきは、陽が傾き、ほんの少し日差しが和らいだ時間帯に歩いている。
珍しく、ザーッと夕立が走った木曜日の翌日・・・・・
その日は、朝からピーカンで、昨夕の夕立がなかったかのように道路は干上がっていた。夕方の公園では花壇の土も木々の葉も強烈な日差しで萎れ、乾ききっていた。
いつものように軽いストレッチを済ませ、ウォーキングを開始した。
と、公園を出発し10メートルほど歩いたところで、歩道に足跡があるのに気付いた。
赤土の足跡で、足裏の形から素足であることが推察された。22センチほどのサイズの足跡は幅が細く、どうやら子供ではなく女性のようだ。
「べっちょり赤土を付けちゃったようだな。昨日の夕立だな。公園の運動場かな・・・」
ボクは勝手に推測しながら歩いた。
足跡は、ボクのウォーキングコースと並走して進んでいた。
「よほど土にハマったのかな・・・まだ足跡続いているもん・・・」
50メートルほど歩いたが、赤土の足跡は、まだくっきりと見える。歩幅も狭いので、小柄の女性かもしれない・・・どうして裸足なのかな・・・どこまで行くのかな・・・などと想像しながらボクは歩を進めた。
歩きはじめて4分ほど経過した。距離で300メートルは歩いたかな。赤い足跡はまだ続いていた。かすかに赤土は薄れているものの300メートルも足跡が残るものなのか・・・ボクはちょっと気になった。
もうすぐ突き当たりの防波堤だ。公園から防波堤までは優に1キロメートルはあるはずだ。
・・・まだ赤い足跡は続いていた。正確にいうと、ボクはもう「赤い足跡を追っていた」。明らかに「ヘン」だ。赤土の痕跡がそんな長距離残るとは思えないし、素足で熱いコンクリートの歩道を何キロも歩くことも考えにくい。
足跡は防波堤で突き当たり、ボクのいつものコースを並走するように、防波堤沿いを北に向かっている。もう2キロ以上は進んだはずだ。
ボクの頭は、いつの間にか赤い足跡の興味と得体の知れない不安と足跡のゴールの確認でいっぱいになっていた。
いつも、チラチラ眺める海もその日は目もくれず、足跡に集中し歩いた。
・・・と、防波堤の、なんの変哲もない場所で足跡は忽然と無くなっていた。進行方向を変えたでもなく、踵を返すのでもなく、休むのでもなく・・・歩行中に消えた・・・感じなのだ。
あれれ・・・・ボクはストレッチをするふりして歩を止め、足跡の消えた一帯をそれとなく観察した。が、やっぱりなんにもない。鑑識風にいうと、現場に痕跡も物証もない、のだ。
翌日の土曜日。もちろん歩いた。足跡はしっかり残っていた。そして、あくる日の日曜日、赤い足跡は、なぜかすっかり無くなっていた。
・・・・あの足跡は、いったい・・・・
2011年07月06日 18:26
幻 -- まぼろし ---
友人のMさんと久しぶりに午後のお茶をご一緒した。
日ごろ健康管理に厳しいMさんが珍しく風邪気味のような鼻声だった。
「いやなにね、このところ暑くて寝苦しいんでクーラーを点けて寝たんですよ。そしたらヒドイ目に遭って・・・」
翌朝、クーラーで寝冷えしたせいかMさんは身体のダルさと熱っぽさを感じ、車で10分ほどのかかりつけ医のクリニックに向かったという。
平日の午後、天気もよくMさんは自分で運転して出かけた。
「ただの寝冷えでしょう。解熱剤の注射と・・・あと風邪薬を処方しときますので・・・」
と、医者は診断し注射の処置をした。
最近の医療機関では、風邪やインフルエンザなどの薬を処方した後、しばらくは病院内など目の届く範囲で安静にして様子をみるのが常のようで、Mさんも診察室隣のベッドで横になった。
40分ほど休み、体調も少し良くなった感じがしたのでMさんは帰宅することにした。
--------- 午後の、ちょうど車の波が途絶える時間帯の国道 -----------
片側二車線の幹線道路で、見通しのよい直線である。車の流れも少なく、Mさんはスムーズに車を走らせていた。
しばらく走ると前方に信号機が見えた。信号が黄色から赤に変わる瞬間だったので、Mさんはブレーキを踏み減速し、停止線に止まった。普段の運転と何も変わらない「あたりまえ」の動作だった。
前方の信号を見ながらボンヤリしていると、後ろの車がやたらとクラクションを鳴らす。信号はまだ「赤」のはずである。Mさんは舌打ちして、バックミラー越しに後続の運転手をにらんだが、またクラクションを鳴らしている。
・・・・と、バックミラーから視線をずらし信号機に目をやった途端、Mさんは氷ついた。
信号機が無いのである。信号機の影も形もない。交差点だと思った場所は直線道路の真ん中で、激しい車の往来の中、Mさんは停車していたのだ。
一瞬、頭の中が真っ白になったが、慌てて車を発進させ「落ち着け、落ち着け・・・」と自分に言い聞かせ、より慎重に運転しながら走ってきた病院からの道筋を反芻した。途中から信号までの記憶がほとんど無いことに気づき、愕然としながら、今度は家までの道筋を慎重に確実に思い出しながら走った。
「あれはなんだったんだろう?」
Mさんは、不安と恐怖に包まれながら頭をひねった。
国道の交差点を曲がり、県道に入ると、もう家は近い。
交差点を右折して、県道の直線を走行していた。上下二車線の県道だ。さっきの信号機のことが頭から離れなかったので、Mさんは慎重に運転していた。だいぶ落ち着いてきていた。
いきなり、無謀な運転の車が一台、正面からMさんの車に突っ込んできた。すんでのところで避け、「今日はなんて日だ」と思った途端、無謀な車は3台も4台も突っ込んできた。動揺し、車を減速させたMさんは再び愕然とした。無謀な運転だと思っていたら、自分がいつの間にか反対車線を逆走していた。
さすがに「危ない」と感じ、Mさんは県道わきに停車させ、身内に連絡し運転を代わってもらって帰った。車で10分ほどの病院からの帰りが、気づけば3時間かかっていた。
Mさんの名誉のために付け加えれば、Mさんは頭脳明晰で体力もある。アルツハイマーや脳の疾患もない。ボケるような高齢でもない。日ごろの健康管理や体力強化には人一倍気をつけているし、健診も欠かさない。これは断言できる。
その後、Mさんと何度かあったが、あれ以来「幻」を見たり、聴いたりすることは一度もないそうだが、「小さなトラウマ」になっている、そうだ。
・・・あの幻覚はいったい・・・・・
日ごろ健康管理に厳しいMさんが珍しく風邪気味のような鼻声だった。
「いやなにね、このところ暑くて寝苦しいんでクーラーを点けて寝たんですよ。そしたらヒドイ目に遭って・・・」
翌朝、クーラーで寝冷えしたせいかMさんは身体のダルさと熱っぽさを感じ、車で10分ほどのかかりつけ医のクリニックに向かったという。
平日の午後、天気もよくMさんは自分で運転して出かけた。
「ただの寝冷えでしょう。解熱剤の注射と・・・あと風邪薬を処方しときますので・・・」
と、医者は診断し注射の処置をした。
最近の医療機関では、風邪やインフルエンザなどの薬を処方した後、しばらくは病院内など目の届く範囲で安静にして様子をみるのが常のようで、Mさんも診察室隣のベッドで横になった。
40分ほど休み、体調も少し良くなった感じがしたのでMさんは帰宅することにした。
--------- 午後の、ちょうど車の波が途絶える時間帯の国道 -----------
片側二車線の幹線道路で、見通しのよい直線である。車の流れも少なく、Mさんはスムーズに車を走らせていた。
しばらく走ると前方に信号機が見えた。信号が黄色から赤に変わる瞬間だったので、Mさんはブレーキを踏み減速し、停止線に止まった。普段の運転と何も変わらない「あたりまえ」の動作だった。
前方の信号を見ながらボンヤリしていると、後ろの車がやたらとクラクションを鳴らす。信号はまだ「赤」のはずである。Mさんは舌打ちして、バックミラー越しに後続の運転手をにらんだが、またクラクションを鳴らしている。
・・・・と、バックミラーから視線をずらし信号機に目をやった途端、Mさんは氷ついた。
信号機が無いのである。信号機の影も形もない。交差点だと思った場所は直線道路の真ん中で、激しい車の往来の中、Mさんは停車していたのだ。
一瞬、頭の中が真っ白になったが、慌てて車を発進させ「落ち着け、落ち着け・・・」と自分に言い聞かせ、より慎重に運転しながら走ってきた病院からの道筋を反芻した。途中から信号までの記憶がほとんど無いことに気づき、愕然としながら、今度は家までの道筋を慎重に確実に思い出しながら走った。
「あれはなんだったんだろう?」
Mさんは、不安と恐怖に包まれながら頭をひねった。
国道の交差点を曲がり、県道に入ると、もう家は近い。
交差点を右折して、県道の直線を走行していた。上下二車線の県道だ。さっきの信号機のことが頭から離れなかったので、Mさんは慎重に運転していた。だいぶ落ち着いてきていた。
いきなり、無謀な運転の車が一台、正面からMさんの車に突っ込んできた。すんでのところで避け、「今日はなんて日だ」と思った途端、無謀な車は3台も4台も突っ込んできた。動揺し、車を減速させたMさんは再び愕然とした。無謀な運転だと思っていたら、自分がいつの間にか反対車線を逆走していた。
さすがに「危ない」と感じ、Mさんは県道わきに停車させ、身内に連絡し運転を代わってもらって帰った。車で10分ほどの病院からの帰りが、気づけば3時間かかっていた。
Mさんの名誉のために付け加えれば、Mさんは頭脳明晰で体力もある。アルツハイマーや脳の疾患もない。ボケるような高齢でもない。日ごろの健康管理や体力強化には人一倍気をつけているし、健診も欠かさない。これは断言できる。
その後、Mさんと何度かあったが、あれ以来「幻」を見たり、聴いたりすることは一度もないそうだが、「小さなトラウマ」になっている、そうだ。
・・・あの幻覚はいったい・・・・・
2011年06月29日 17:29
赤い蝶
オオゴマダラという蝶をご存知だろうか?
白地に黒い斑点を散らしたような大きな蝶で、ゆったりと低空を舞う様は優雅だ。
その大きさと模様から新聞蝶とも呼ばれるそうだ。
羽を広げた大きさが13センチほどにもなる日本最大級の蝶で、最近では沖縄県内の学校や植物園などで飼育されているためか、街中でもよく見かける。
一昔前のオオゴマダラは、ちょっと珍しく、夏休みの昆虫採集では結構自慢できる昆虫だった。
だから、オオゴマダラをよく目撃するポイントは自分だけの秘密の場所として友人にも教えなかった。
・・・ある夏休み。
小学校裏山の「秘密の場所」へ向かった。夏休みの自由研究の昆虫採集で、オオゴマダラを捕獲するのが目的だった。もちろん友達にも内緒にし、独りで向かった。
夏休み午前中の学校に人気はなく、僕は運動場を横切り、校庭を突っ切って、校舎裏の柵を乗り越えて裏山に向かった。
「秘密の場所」は、アダンにつる草がネットのように覆いかぶさった藪で、そのつる草の細かい花弁が集まった花冠にオオゴマダラが訪れた。
その日は三匹ものオオゴマダラが花弁から花弁へとゆったりと移動しながら飛びまわっていた。
オオゴマダラ自体珍しいのに、三羽である。僕は興奮した。
急いで虫網を持ち直し、慎重に近づいた。低い位置に止まっていたオオゴマダラをすばやく捕獲し、次いでやや高い場所で蜜を吸っている一匹に網を寄せた。と、ふわりと舞い、上空に逃げた。
もう一匹いるはずだ、とアダンの裏に回り込んだとき、僕の目は一点に吸い寄せられた。
網がやっと届きそうな白い花冠に赤い蝶が一匹止まっているのだ。
太陽の逆光を透かした羽は真っ赤で、ちょうど赤いインクを水に流し込んだような透明な赤なのだ。
斑点や模様もない、透明な赤一色の蝶が羽をゆっくり閉じ開いて蜜を吸っている。
初めて目にする蝶で、昆虫図鑑でも見たことがなかった。赤い蝶なんて聞いたこともなかった。
あまりの綺麗さと衝撃で立ちすくんでいると、蝶はふわりと浮き、風に乗るように飛び去った。
もちろん追いかけたがほどなく見失い、それっきり二度と「赤い蝶」を目撃したことはない。
あの透明な赤い蝶は、いったい・・・・・
白地に黒い斑点を散らしたような大きな蝶で、ゆったりと低空を舞う様は優雅だ。
その大きさと模様から新聞蝶とも呼ばれるそうだ。
羽を広げた大きさが13センチほどにもなる日本最大級の蝶で、最近では沖縄県内の学校や植物園などで飼育されているためか、街中でもよく見かける。
一昔前のオオゴマダラは、ちょっと珍しく、夏休みの昆虫採集では結構自慢できる昆虫だった。
だから、オオゴマダラをよく目撃するポイントは自分だけの秘密の場所として友人にも教えなかった。
・・・ある夏休み。
小学校裏山の「秘密の場所」へ向かった。夏休みの自由研究の昆虫採集で、オオゴマダラを捕獲するのが目的だった。もちろん友達にも内緒にし、独りで向かった。
夏休み午前中の学校に人気はなく、僕は運動場を横切り、校庭を突っ切って、校舎裏の柵を乗り越えて裏山に向かった。
「秘密の場所」は、アダンにつる草がネットのように覆いかぶさった藪で、そのつる草の細かい花弁が集まった花冠にオオゴマダラが訪れた。
その日は三匹ものオオゴマダラが花弁から花弁へとゆったりと移動しながら飛びまわっていた。
オオゴマダラ自体珍しいのに、三羽である。僕は興奮した。
急いで虫網を持ち直し、慎重に近づいた。低い位置に止まっていたオオゴマダラをすばやく捕獲し、次いでやや高い場所で蜜を吸っている一匹に網を寄せた。と、ふわりと舞い、上空に逃げた。
もう一匹いるはずだ、とアダンの裏に回り込んだとき、僕の目は一点に吸い寄せられた。
網がやっと届きそうな白い花冠に赤い蝶が一匹止まっているのだ。
太陽の逆光を透かした羽は真っ赤で、ちょうど赤いインクを水に流し込んだような透明な赤なのだ。
斑点や模様もない、透明な赤一色の蝶が羽をゆっくり閉じ開いて蜜を吸っている。
初めて目にする蝶で、昆虫図鑑でも見たことがなかった。赤い蝶なんて聞いたこともなかった。
あまりの綺麗さと衝撃で立ちすくんでいると、蝶はふわりと浮き、風に乗るように飛び去った。
もちろん追いかけたがほどなく見失い、それっきり二度と「赤い蝶」を目撃したことはない。
あの透明な赤い蝶は、いったい・・・・・
2011年06月21日 10:47
掴む手
今時分、ウォーキングがてら防波堤から海を見ると潮目をよく目にする。
潮目は海水温や塩分濃度、海流などの影響で海面の色が若干周囲と異なる現象のこと。
夏の海で、海面に細い川のような筋で現れたりする、あれだ。
・・・中学校の時。ちょうど慰霊の日の前の週末、近くの海岸に泳ぎに行った。
その日も、今日のようなうだるような暑い日で、海面には幾筋かの潮目がくっきりと現れていた。
「潮の変わり目のところは、水温が急に冷たくなっていたり、流れが早いから近づくな」と、漁師の父親に以前からちょくちょく注意はされていたが、海水浴に夢中になっていて、いつの間にか潮目の真ん中で泳いでいた。
潮目では、水面近くは温かいのに腰から下の水温は冷たかった。はっきり分かるほどの水温差があった。
好奇心旺盛の中学生のこと、その足の冷たさが不思議で心地よく、僕は意識して潮目の川に沿って泳いでいた。潮の流れはなかったと思う。
浮いたり、潜ったりしながら泳ぎ、遊んでいるうち、あることに気づいた。
潮目の決まった位置で立ち泳ぎすると、だれかの手で足を掴まれている気がした。五本の指の手でなぞられ、掴まれたような感覚があったのだ。正確に言うと、冷たい透明なスライムのような大きな手でゆっくりとなぞられ、徐々に掴まれ、また緩めた手で再びなぞられる、という感じがしたのだ。
もちろん、水面から覗き込んでも、潜って確かめても誰もいない。
人が隠れることができるような岩場も周囲にはなかった。
ちょっと恐かったが、大きな透明な手でゆっくりとなでられ、掴まれる感覚は面白く、僕はその場所で立ち泳ぎを繰り返した。
しばらくして・・・・いきなり、大きな手の握る力が強くなったかと思ったら、すごい力で僕は海中に引きずり込まれていた。たしかに、ぐいっと引っ張られたのだ。必死に抗った。なんとかサンゴ礁の岩場にしがみつき、海面に顔を出して助かった。
その後、僕は素潜りやスキューバダイビングで幾度となく潮目や海流の中でも泳いだが「水に掴まれる」という感覚や経験は一度としてない。
あの大きな透明な手は、なんだったんだろう・・・・
潮目は海水温や塩分濃度、海流などの影響で海面の色が若干周囲と異なる現象のこと。
夏の海で、海面に細い川のような筋で現れたりする、あれだ。
・・・中学校の時。ちょうど慰霊の日の前の週末、近くの海岸に泳ぎに行った。
その日も、今日のようなうだるような暑い日で、海面には幾筋かの潮目がくっきりと現れていた。
「潮の変わり目のところは、水温が急に冷たくなっていたり、流れが早いから近づくな」と、漁師の父親に以前からちょくちょく注意はされていたが、海水浴に夢中になっていて、いつの間にか潮目の真ん中で泳いでいた。
潮目では、水面近くは温かいのに腰から下の水温は冷たかった。はっきり分かるほどの水温差があった。
好奇心旺盛の中学生のこと、その足の冷たさが不思議で心地よく、僕は意識して潮目の川に沿って泳いでいた。潮の流れはなかったと思う。
浮いたり、潜ったりしながら泳ぎ、遊んでいるうち、あることに気づいた。
潮目の決まった位置で立ち泳ぎすると、だれかの手で足を掴まれている気がした。五本の指の手でなぞられ、掴まれたような感覚があったのだ。正確に言うと、冷たい透明なスライムのような大きな手でゆっくりとなぞられ、徐々に掴まれ、また緩めた手で再びなぞられる、という感じがしたのだ。
もちろん、水面から覗き込んでも、潜って確かめても誰もいない。
人が隠れることができるような岩場も周囲にはなかった。
ちょっと恐かったが、大きな透明な手でゆっくりとなでられ、掴まれる感覚は面白く、僕はその場所で立ち泳ぎを繰り返した。
しばらくして・・・・いきなり、大きな手の握る力が強くなったかと思ったら、すごい力で僕は海中に引きずり込まれていた。たしかに、ぐいっと引っ張られたのだ。必死に抗った。なんとかサンゴ礁の岩場にしがみつき、海面に顔を出して助かった。
その後、僕は素潜りやスキューバダイビングで幾度となく潮目や海流の中でも泳いだが「水に掴まれる」という感覚や経験は一度としてない。
あの大きな透明な手は、なんだったんだろう・・・・
2011年06月20日 10:48
夢の結末
20フィートの小舟を10隻も係留すればいっぱいになりそうな小さな港に僕はいました。
周りに船影はなく、僕の乗っている小さな木造船が一隻、炎天下の桟橋に係留されています。
まだ午前中のようでした。
友人たちが島に渡る、というので、船舶免許を持っていた僕が船頭の役をかってでた感じでした。
島に着くや、友人たちはそそくさと上陸し、「探険だ」とか言って島内に入っていきました。
帰りの心配と船の留守番もあるので、僕は独り船上に取り残されています。
港は、かなり長い時間つかわれいないのか、係船柱は厚い錆が松皮のようにへばり付いています。
波に洗われた桟橋には、大きな岩ガキと海藻がびっしり繁殖しているのですが、桟橋上部は風と雨と紫外線にさらされ、無機質に白っぽくなっています。
タポタポと波が押し寄せるたびに、丸みを帯びた波頭が太陽の鈍い光を反射しています。
上空でミサゴが一羽、ヒュルルーと鳴き、旋回しているのが見えます。
頂が平らな円錐状の島のようで、坂道が網目のように島を覆っています。
何軒かの廃墟が、海に向けられた戦跡のトーチカのように点在しているのが見えます。
一本の坂道を友人たちが登って行くのが見えました。
時々、振り返っては島の景色に感嘆し、坂の上を確認しては口々にしゃべりながら登っていきます。
腕を広げて何か盛んに説明をしている友人もいますが、声は遠く、はっきりとは聞こえません。
坂を登りきった廃屋の一軒に友人たちは入って行きました。
いや、頭が見え隠れしているので家屋の中ではなく、庭で何かしているようです。
上空のミサゴからは見えそうですが、港から伺い知ることはできません。
船上で少しウトウトし、さっきの坂上を見上げると、ちょうど友人たちが下りてくるのが見えました。
ちょっとウトウトしたつもりでしたが、正午をまわっているようです。
島を後にしなければならない時間だと気づきます。
坂を下る友人たちが港近く来たとき、誰かが忘れ物をしたようなジェスチャーで坂上を指さしています。
と、また坂を上り、戻って行くのが見えました。
チッ! 僕は短く舌打ちをし時計を見ます。時刻は二時半を少し回っています。
友人の一人が、さっきの廃屋の前で大きく両手を振ってこちらに合図を送っています。
僕はオーバーに腕時計を指さし、急かします。
僕の合図が届いたのか、今度は、大急ぎで友人たちが坂を下ってきました。
もう少しで船に駆け込むだろうと、上陸時に友人たちが集落へ入っていった垣根の先に視線を落とします。
入り口の先は薄暗く、ウタキのような静寂が漂っています。
ゆるい風が集落入口の垣根を揺らしています。一瞬、友人たちかと思いましたが、風で揺れただけだと気づきます。
遅い。僕はそう感じました。
空でミサゴがヒュルルーと鳴いています。
見上げた上空の強い日差しで、眩暈のように、一瞬目の前が暗くなりました。
薄目で島を仰ぎ見ると坂の途中で、何かが蠢き、走り落ちるように見えました。
友人たちだ!と理解します。
「まだ下っているの?」
一瞬不思議な感覚に包まれます。
慌てて坂を下ってくる姿は、可笑しくさえありました。
可笑しい感情が、一転、僕はすべてを理解し次の瞬間恐怖に襲われます。
いつのまにか島の時空に捕らわれ、出られなくなったと確信します。
急いで小船から桟橋に飛び降り、友人たちを導き寄せようと炎天下の護岸を走ります。
コンクリートの反射光で足元はくらむほどの真っ白な空間に変わり、空中に放り出された錯覚を覚えます。
一瞬、躊躇し立ち止まり、小船を振り返ります。
桟橋の係船柱の脇に、赤錆びたドラム缶のトーテンポールが崩れかけ詰まれています。
そして、トーテンポールの向こう側に係留した船のロープが自然にスルリとほどけ、
船が港の外へゆっくりと流れ出ていくのを立ち尽くして見送っているのです。
------- というのが、僕の見た夢でした --------
周りに船影はなく、僕の乗っている小さな木造船が一隻、炎天下の桟橋に係留されています。
まだ午前中のようでした。
友人たちが島に渡る、というので、船舶免許を持っていた僕が船頭の役をかってでた感じでした。
島に着くや、友人たちはそそくさと上陸し、「探険だ」とか言って島内に入っていきました。
帰りの心配と船の留守番もあるので、僕は独り船上に取り残されています。
港は、かなり長い時間つかわれいないのか、係船柱は厚い錆が松皮のようにへばり付いています。
波に洗われた桟橋には、大きな岩ガキと海藻がびっしり繁殖しているのですが、桟橋上部は風と雨と紫外線にさらされ、無機質に白っぽくなっています。
タポタポと波が押し寄せるたびに、丸みを帯びた波頭が太陽の鈍い光を反射しています。
上空でミサゴが一羽、ヒュルルーと鳴き、旋回しているのが見えます。
頂が平らな円錐状の島のようで、坂道が網目のように島を覆っています。
何軒かの廃墟が、海に向けられた戦跡のトーチカのように点在しているのが見えます。
一本の坂道を友人たちが登って行くのが見えました。
時々、振り返っては島の景色に感嘆し、坂の上を確認しては口々にしゃべりながら登っていきます。
腕を広げて何か盛んに説明をしている友人もいますが、声は遠く、はっきりとは聞こえません。
坂を登りきった廃屋の一軒に友人たちは入って行きました。
いや、頭が見え隠れしているので家屋の中ではなく、庭で何かしているようです。
上空のミサゴからは見えそうですが、港から伺い知ることはできません。
船上で少しウトウトし、さっきの坂上を見上げると、ちょうど友人たちが下りてくるのが見えました。
ちょっとウトウトしたつもりでしたが、正午をまわっているようです。
島を後にしなければならない時間だと気づきます。
坂を下る友人たちが港近く来たとき、誰かが忘れ物をしたようなジェスチャーで坂上を指さしています。
と、また坂を上り、戻って行くのが見えました。
チッ! 僕は短く舌打ちをし時計を見ます。時刻は二時半を少し回っています。
友人の一人が、さっきの廃屋の前で大きく両手を振ってこちらに合図を送っています。
僕はオーバーに腕時計を指さし、急かします。
僕の合図が届いたのか、今度は、大急ぎで友人たちが坂を下ってきました。
もう少しで船に駆け込むだろうと、上陸時に友人たちが集落へ入っていった垣根の先に視線を落とします。
入り口の先は薄暗く、ウタキのような静寂が漂っています。
ゆるい風が集落入口の垣根を揺らしています。一瞬、友人たちかと思いましたが、風で揺れただけだと気づきます。
遅い。僕はそう感じました。
空でミサゴがヒュルルーと鳴いています。
見上げた上空の強い日差しで、眩暈のように、一瞬目の前が暗くなりました。
薄目で島を仰ぎ見ると坂の途中で、何かが蠢き、走り落ちるように見えました。
友人たちだ!と理解します。
「まだ下っているの?」
一瞬不思議な感覚に包まれます。
慌てて坂を下ってくる姿は、可笑しくさえありました。
可笑しい感情が、一転、僕はすべてを理解し次の瞬間恐怖に襲われます。
いつのまにか島の時空に捕らわれ、出られなくなったと確信します。
急いで小船から桟橋に飛び降り、友人たちを導き寄せようと炎天下の護岸を走ります。
コンクリートの反射光で足元はくらむほどの真っ白な空間に変わり、空中に放り出された錯覚を覚えます。
一瞬、躊躇し立ち止まり、小船を振り返ります。
桟橋の係船柱の脇に、赤錆びたドラム缶のトーテンポールが崩れかけ詰まれています。
そして、トーテンポールの向こう側に係留した船のロープが自然にスルリとほどけ、
船が港の外へゆっくりと流れ出ていくのを立ち尽くして見送っているのです。
------- というのが、僕の見た夢でした --------
2011年06月17日 11:33
夢のつづき
錆びたトーテンポールのサインを見つけ、僕らは唖然とし、戸惑い、畏れの空気に包まれます。
殺風景の白い庭の記憶を咀嚼しながら周りを見ます。
低い石垣のつる草が伸び、太い幹が石垣の石を抱き込んでいますが、確かに見覚えがある、あの庭です。
ほんの数十分前に、炎天下でドラム缶を切り、ペンキを塗り、トーテンポールを創った庭です。
それが、数十年も時間が経ったような風景になっています。
高い空にミサゴがヒュルルーと一声鳴くのが風に乗って聞こえます。
庭先から、坂道の先を見下ろすと小さな港が見えます。木造のポンポン船が一隻係留されています。
太陽は真上から、ちょっと傾き、濃い影がコンクリートの庭に投影されています。
僕らは、大急ぎで坂を下り、港に向かいました。
細い坂道を下りきったところで、垣根のような雑木林が行く手をふさいでいます。
背の高いススキと仏葬花が織り込まれたような垣根で、隙間から港と、僕らの乗って来た船が見えます。
声を掛ければ、船上で坂道を見上げている誰かに声が届きそうですが、気づいてくれません。
無理に垣根を押し開いて進もうとするのですが、ぎっちりと織り込まれた仏葬花とススキは隙間さえ開ける事ができないのです。
目前の垣根を諦め、垣根を右手の掌で確認するように押しながら進みます。
垣根の向こう側に開けた桟橋と船が、走馬灯のように見え隠れしています。
このままだと、いつまで経っても船にたどり着けないような焦燥感で汗が吹き出ています。
垣根から掌を離さないようにしながら、慎重に歩きながら港への道を探します。
高い空にミサゴがヒュルルーと一声鳴くのが風に乗って聞こえます。
垣根に掌を添えたまま天空を仰ぎ、ミサゴの姿を目で追いました。
群青の空にミサゴを見つけることはできません。
視線を落とし、掌を添えていたはずの垣根を見直すと、ススキと仏葬花だったはずの垣根が風化した石灰石の石垣と石を抱き込むように伸びたつる草になっています。
背の低い石垣で、石垣の向こうに白く風化した庭、そして錆びて崩れかけたドラム缶の残骸が見えるのです。
・・・・夢のシーンは変わり、僕は木造の小さな船の上にいました・・・・
つづく。
殺風景の白い庭の記憶を咀嚼しながら周りを見ます。
低い石垣のつる草が伸び、太い幹が石垣の石を抱き込んでいますが、確かに見覚えがある、あの庭です。
ほんの数十分前に、炎天下でドラム缶を切り、ペンキを塗り、トーテンポールを創った庭です。
それが、数十年も時間が経ったような風景になっています。
高い空にミサゴがヒュルルーと一声鳴くのが風に乗って聞こえます。
庭先から、坂道の先を見下ろすと小さな港が見えます。木造のポンポン船が一隻係留されています。
太陽は真上から、ちょっと傾き、濃い影がコンクリートの庭に投影されています。
僕らは、大急ぎで坂を下り、港に向かいました。
細い坂道を下りきったところで、垣根のような雑木林が行く手をふさいでいます。
背の高いススキと仏葬花が織り込まれたような垣根で、隙間から港と、僕らの乗って来た船が見えます。
声を掛ければ、船上で坂道を見上げている誰かに声が届きそうですが、気づいてくれません。
無理に垣根を押し開いて進もうとするのですが、ぎっちりと織り込まれた仏葬花とススキは隙間さえ開ける事ができないのです。
目前の垣根を諦め、垣根を右手の掌で確認するように押しながら進みます。
垣根の向こう側に開けた桟橋と船が、走馬灯のように見え隠れしています。
このままだと、いつまで経っても船にたどり着けないような焦燥感で汗が吹き出ています。
垣根から掌を離さないようにしながら、慎重に歩きながら港への道を探します。
高い空にミサゴがヒュルルーと一声鳴くのが風に乗って聞こえます。
垣根に掌を添えたまま天空を仰ぎ、ミサゴの姿を目で追いました。
群青の空にミサゴを見つけることはできません。
視線を落とし、掌を添えていたはずの垣根を見直すと、ススキと仏葬花だったはずの垣根が風化した石灰石の石垣と石を抱き込むように伸びたつる草になっています。
背の低い石垣で、石垣の向こうに白く風化した庭、そして錆びて崩れかけたドラム缶の残骸が見えるのです。
・・・・夢のシーンは変わり、僕は木造の小さな船の上にいました・・・・
つづく。
2011年06月17日 11:13
奇妙な夢
カメちゃんの話題ではないのですが、今朝見た夢がちょいリアルで不思議だったんで記載しときます。
なぜか、夏休み・・・・
僕と友人数人で、小さな島にキャンプしに渡りました。
九州の島原あたりか、沖縄の離島のようでした。
ちょっと亜熱帯を感じさせる湿気のあるひなびた感じの島で、ススキなどの青草が茂っていました。
とても静かです。
小さな島ですが、以前は数百人は住んでいたようで、廃屋が島のあちらこちらに点在しています。
坂の多い島で、コンクリートの小道が網目のように島に張り付いています。とても車では通れそうにない細い坂道です。
廃屋は、坂の小道に沿うように建っていて、低い石垣で囲まれていました。ほとんどの家屋が、砂粒の荒いコンクリートでつくられた古い洋式家屋で、昭和の景気のいい時代に建てられたようです。
人気はまったくありません。
僕らは、島の全景を確認するために坂道を登り、上りきった先の、ある廃屋の庭にいます。
庭といっても、コンクリートを流し込んだ屋敷前の空間で、白く殺風景なほど清潔な感じの庭でした。
脱色した石肌は、島の紫外線の強さを想像できました。
高い空にミサゴがヒュルルーと一声鳴くのが風に乗って聞こえます。
庭先から、坂道の先を見下ろすと小さな港が見えます。木造のポンポン船が一隻係留されています。
「ああ、あそこから来たんだ」と分かりました。
太陽は真上から、ちょっと傾き、濃い影がコンクリートの庭に投影されています。
二時過ぎだと思いました。
そろそろ戻る時間だと、誰かが言っています。
島にきた記念に、何か残そうと考え、なぜかトーテンポールを作りはじめました。
片隅にあったドラム缶を輪切りにし、大きな「だるま落とし」のようなトーテンポールです。
だるま落としのパーツ一個一個は、ちゃんと缶詰のような円柱になっていて僕らは、それぞれに違う色を塗りました。
一番上は、マフィンのように頭部を盛り上げ、目立つように赤い色を塗りました。
赤いマフィンの底に、今日の日付とキャンプにきた連中のサインを記すことも忘れません。
船の操縦席の窓ガラスにギラリとした日差しが反射し、一瞬眩しくなりました。
と、汽笛が鳴り、そろそろ帰る時刻だと急かしています。
五分もあれば、坂を下り、船まで行けそうな距離です。
点在する廃屋を左右に見ながら、細い坂道を下り、港に向かいました。
もう少しで、視界が開けて港が見えるところで、生い茂った雑草が道をふさいでいます。
やむなく左にそれ、道なりに雑草の隙間を探すのですが、なかなか抜けられません。
いったん、雑草より少し高台に上り、俯瞰しながら雑草の壁の通り道を探そうと、別の坂道を上がりました。
抜け道をなかなか見つけることができません。
と、見晴らしのよさそうな廃屋の庭を見つけます。
「ああ、ここからなら見えそうだ」と安心します。
白っぽく日焼けした庭に、褐色のサビが大理石の模様のように、這っています。
模様の中心を目で追うと、崩れかけたドラム缶が詰まれていました。
背の低いドラム缶で、誰かが輪切りにして積んだようです。
赤錆が酷いのですが、朽ちかけたドラム缶にはそれぞれ色が塗られていた形跡があります。
その輪切りドラム缶のひとつに赤いペンキがかすかにこびりついています。
裏には、今日の日付と僕らのサインが剥がれかけて残っていました。
そして・・・夢は続きます・・・・
なぜか、夏休み・・・・
僕と友人数人で、小さな島にキャンプしに渡りました。
九州の島原あたりか、沖縄の離島のようでした。
ちょっと亜熱帯を感じさせる湿気のあるひなびた感じの島で、ススキなどの青草が茂っていました。
とても静かです。
小さな島ですが、以前は数百人は住んでいたようで、廃屋が島のあちらこちらに点在しています。
坂の多い島で、コンクリートの小道が網目のように島に張り付いています。とても車では通れそうにない細い坂道です。
廃屋は、坂の小道に沿うように建っていて、低い石垣で囲まれていました。ほとんどの家屋が、砂粒の荒いコンクリートでつくられた古い洋式家屋で、昭和の景気のいい時代に建てられたようです。
人気はまったくありません。
僕らは、島の全景を確認するために坂道を登り、上りきった先の、ある廃屋の庭にいます。
庭といっても、コンクリートを流し込んだ屋敷前の空間で、白く殺風景なほど清潔な感じの庭でした。
脱色した石肌は、島の紫外線の強さを想像できました。
高い空にミサゴがヒュルルーと一声鳴くのが風に乗って聞こえます。
庭先から、坂道の先を見下ろすと小さな港が見えます。木造のポンポン船が一隻係留されています。
「ああ、あそこから来たんだ」と分かりました。
太陽は真上から、ちょっと傾き、濃い影がコンクリートの庭に投影されています。
二時過ぎだと思いました。
そろそろ戻る時間だと、誰かが言っています。
島にきた記念に、何か残そうと考え、なぜかトーテンポールを作りはじめました。
片隅にあったドラム缶を輪切りにし、大きな「だるま落とし」のようなトーテンポールです。
だるま落としのパーツ一個一個は、ちゃんと缶詰のような円柱になっていて僕らは、それぞれに違う色を塗りました。
一番上は、マフィンのように頭部を盛り上げ、目立つように赤い色を塗りました。
赤いマフィンの底に、今日の日付とキャンプにきた連中のサインを記すことも忘れません。
船の操縦席の窓ガラスにギラリとした日差しが反射し、一瞬眩しくなりました。
と、汽笛が鳴り、そろそろ帰る時刻だと急かしています。
五分もあれば、坂を下り、船まで行けそうな距離です。
点在する廃屋を左右に見ながら、細い坂道を下り、港に向かいました。
もう少しで、視界が開けて港が見えるところで、生い茂った雑草が道をふさいでいます。
やむなく左にそれ、道なりに雑草の隙間を探すのですが、なかなか抜けられません。
いったん、雑草より少し高台に上り、俯瞰しながら雑草の壁の通り道を探そうと、別の坂道を上がりました。
抜け道をなかなか見つけることができません。
と、見晴らしのよさそうな廃屋の庭を見つけます。
「ああ、ここからなら見えそうだ」と安心します。
白っぽく日焼けした庭に、褐色のサビが大理石の模様のように、這っています。
模様の中心を目で追うと、崩れかけたドラム缶が詰まれていました。
背の低いドラム缶で、誰かが輪切りにして積んだようです。
赤錆が酷いのですが、朽ちかけたドラム缶にはそれぞれ色が塗られていた形跡があります。
その輪切りドラム缶のひとつに赤いペンキがかすかにこびりついています。
裏には、今日の日付と僕らのサインが剥がれかけて残っていました。
そして・・・夢は続きます・・・・
2011年06月17日 11:12
・ハブが出た
春のうららに誘われてヒョッコりってわけでもないでしょうが、実家近くの高校でハブが捕獲されたって。
新聞に大きく掲載されていたのでご覧になった方もいるかもね。なんでも校舎のエントランスにとぐろ巻いていたって。ハブを取り押さえた警察官がちょっと自慢気に写っていたわけさ。体長150cmくらいのハブって。
実家はたしかに畑の真ん中だけど、あたしゃ「生きたハブ」はみたことありません。見たことあるのは、車に轢かれて干からびたハブ公(言い方がちょっと古いですね)や玉泉洞で泡盛の中に漬けられているヤツぐらだわけ。
 あ、アカマターは何回か見たことあるよぉ、生きているもの。
あ、アカマターは何回か見たことあるよぉ、生きているもの。
家の中に来たのもいたよお。あんときは、隣のおばさん大活躍だったさぁ。庭に出して、いきなり棒でタッピラカすんだもん。メッタ打ちぃ!ピクリともしないのに「ヤナ、アカマターぐゎひゃー」って、ちゃー殴りー。はーもぉ、とっくに死んでいるってば、おばさんよぉ。正直、おばさんのパワーの方が怖かったってば。

ヘビ(ハブも)は暖かくなっていい天気になると涼しいとこ探して出てくるって、誰か言っていた。だから、「いい天気」を「ハブ ア ナイスデー」って言うって。まるユクシだわけ・・・・中学校1年まで信じていたわけ・・・恥ずかしい・・・・

新聞に大きく掲載されていたのでご覧になった方もいるかもね。なんでも校舎のエントランスにとぐろ巻いていたって。ハブを取り押さえた警察官がちょっと自慢気に写っていたわけさ。体長150cmくらいのハブって。

実家はたしかに畑の真ん中だけど、あたしゃ「生きたハブ」はみたことありません。見たことあるのは、車に轢かれて干からびたハブ公(言い方がちょっと古いですね)や玉泉洞で泡盛の中に漬けられているヤツぐらだわけ。

 あ、アカマターは何回か見たことあるよぉ、生きているもの。
あ、アカマターは何回か見たことあるよぉ、生きているもの。家の中に来たのもいたよお。あんときは、隣のおばさん大活躍だったさぁ。庭に出して、いきなり棒でタッピラカすんだもん。メッタ打ちぃ!ピクリともしないのに「ヤナ、アカマターぐゎひゃー」って、ちゃー殴りー。はーもぉ、とっくに死んでいるってば、おばさんよぉ。正直、おばさんのパワーの方が怖かったってば。


ヘビ(ハブも)は暖かくなっていい天気になると涼しいとこ探して出てくるって、誰か言っていた。だから、「いい天気」を「ハブ ア ナイスデー」って言うって。まるユクシだわけ・・・・中学校1年まで信じていたわけ・・・恥ずかしい・・・・

2009年03月30日 18:03
・ゴッキーの季節到来
寒の戻りのようで、今朝はちょっと冷えましたね。
昨晩は、ちょい肌寒だったんで、まったく警戒していなかったんですが、出たわけさ、ゴッキーちゃん。はい、ゴキブリが。
あたしん家で今年初めての出現です。はーーーーっ、ついに来たかーって感じっす。
自慢じゃないですが、あたしゃゴキブリは嫌い!
小さいころはそうでもなかったんですが、中学校のころ、ブーンって飛び回るゴキブリに追っかけられ、挙句、頭にポンって乗られて、背中はいずり回られて以来、大嫌い!!です。・・・思い出しただけで、身の毛もよだつぅぅぅぅぅぅぅ
そのゴキちゃんが、遂に昨夜出没したんですよ、ええ。ガサゴソと。・・・どっかへ逃げてしまっちゃったけど・・・・
お陰様で、今朝は睡眠不足です。
朝から、メキシコ民謡「ラ・クカラーチャ」が、頭の中、ぐるんぐるんエンドレスで流れています。
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー ・・・誰か止めてぇーーーーー
・・・誰か止めてぇーーーーー
昨晩は、ちょい肌寒だったんで、まったく警戒していなかったんですが、出たわけさ、ゴッキーちゃん。はい、ゴキブリが。
あたしん家で今年初めての出現です。はーーーーっ、ついに来たかーって感じっす。
自慢じゃないですが、あたしゃゴキブリは嫌い!

小さいころはそうでもなかったんですが、中学校のころ、ブーンって飛び回るゴキブリに追っかけられ、挙句、頭にポンって乗られて、背中はいずり回られて以来、大嫌い!!です。・・・思い出しただけで、身の毛もよだつぅぅぅぅぅぅぅ

そのゴキちゃんが、遂に昨夜出没したんですよ、ええ。ガサゴソと。・・・どっかへ逃げてしまっちゃったけど・・・・
お陰様で、今朝は睡眠不足です。

朝から、メキシコ民謡「ラ・クカラーチャ」が、頭の中、ぐるんぐるんエンドレスで流れています。

 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
 ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー
ラ・クカラーチャ ラ・クカラーチャ フンフフフフフー ・・・誰か止めてぇーーーーー
・・・誰か止めてぇーーーーー2009年03月26日 10:31