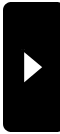5年ぶりのブログ
ブログを更新をしなくなって5年経ちました。
5年前 -----
ボクはユニクロの試着室にいました。
久しぶりに、ジーンズの一着でも買おうと意気込んで行ったのです。
店員さんに何着かのジーンズを選んでもらって、気に入ったデザインのサイズ違い3本をもって試着室に入りました。
1本目(以前買ったサイズはこれだったよな) -------
あれれ? 履く以前に脚が入らないんですけど??
2本目(ま、太ったからしょうがない。ややサイズアップも念のため持ってきているって) ------
脚はなんとは入ったな。よしよし。あれれ?前のチャックどころかボタンが閉まらないんですけど??
腹を思いっきり引っ込めても無理。ウエスト部分が10センチは開いてるし!
3本目(保険用に一番デカイやつ持ってきてよかったぁ) ------
これでダメだったら試着室から出れねーぜ。、もうここで、この場所で腹搔っ捌いてやる(という意気込み)でトライ。
脚は余裕ね。余裕どころか裾詰め分でもう1本はジーンズができそうだぜ。
腰回りは・・・あれれ? 閉まらない! 腹に力入れて・・・あと5センチ・・・・んんー・・・・3センチ・・・・ムリー!!!
と、いう悲しい経験を経て、5年前ボクはダイエットを決意したのでした。
もうブログどころではない。痩せなきゃ。この屈辱は倍返しだ(誰に?)。
苦節5年。ボクのダイエットの結果はいかに・・・・次回につづく。
5年前 -----
ボクはユニクロの試着室にいました。
久しぶりに、ジーンズの一着でも買おうと意気込んで行ったのです。
店員さんに何着かのジーンズを選んでもらって、気に入ったデザインのサイズ違い3本をもって試着室に入りました。
1本目(以前買ったサイズはこれだったよな) -------
あれれ? 履く以前に脚が入らないんですけど??
2本目(ま、太ったからしょうがない。ややサイズアップも念のため持ってきているって) ------
脚はなんとは入ったな。よしよし。あれれ?前のチャックどころかボタンが閉まらないんですけど??
腹を思いっきり引っ込めても無理。ウエスト部分が10センチは開いてるし!
3本目(保険用に一番デカイやつ持ってきてよかったぁ) ------
これでダメだったら試着室から出れねーぜ。、もうここで、この場所で腹搔っ捌いてやる(という意気込み)でトライ。
脚は余裕ね。余裕どころか裾詰め分でもう1本はジーンズができそうだぜ。
腰回りは・・・あれれ? 閉まらない! 腹に力入れて・・・あと5センチ・・・・んんー・・・・3センチ・・・・ムリー!!!
と、いう悲しい経験を経て、5年前ボクはダイエットを決意したのでした。
もうブログどころではない。痩せなきゃ。この屈辱は倍返しだ(誰に?)。
苦節5年。ボクのダイエットの結果はいかに・・・・次回につづく。
2020年01月14日 12:01
成り済まし
知人の訃報が届いたのは、底冷えのする師走の深夜のことでした。
時計は深夜一時を回り、就寝前に開いたメールでした。
>> ご無沙汰しています。緊急連絡です。
突然で驚くかもしれませんが、Sさんが亡くなりました。
今朝配達の途中で倒れ、そのままだったそうです。
明日の夕方、告別式があるそうですので、ぜひご参列ください。<<<
メールは、以前の職場の同僚だったUからでした。
亡くなったSさんも元同僚の一人で、仕事の傍ら少年サッカーのコーチを長い間やっていて、
真っ黒に日焼けしたがっしりした体格の方でした。「コーチは体力勝負だから」と職場の行き帰りをジョギングで通うほどのスポーツ好きで、健康には人一倍気をつかうようなストイックな人でした。
いつものように早朝の配達業務の途中、くも膜下出血で倒れ、救急病院に運ばれたようですが、
一度も意識を取り戻すことなくそのまま息をひきとったそうです。まだ四十台半ばの突然の死でした。
---------------------------------
翌日の告別式を終え、式場から帰宅したボクはしばらく喪服のまま椅子に腰かけボンヤリしていました。
どのくらい時間が経ったのでしょうか、早い冬の宵闇が窓辺に忍び寄り、気づいたら室内は薄暗くなっていました。
部屋の蛍光灯を点け、喪服を脱ぎながらパソコンのスイッチを入れました。
そういえば、ボクが参加しているSNSグループのメンバーにSさんもいたことを思い出したのでした。
SNSにログインするのは、大分久しぶりでした。ボクが最後に書き込んだのは夏の終わりだったようです。
ずいぶんと溜まった投稿ログをスクロールしながら辿りました。
Sさんはこまめに投稿していたようで、少年サッカーの話題やら家族でキャンプ行った写真やらをたくさん載せていました。
ゆっくりスクロールしながら、他の投稿を確認していると、彼が亡くなる一週間前の投稿が目に留まりました。
「緊急なお知らせ!」とタイトルが打ってありました。
>>みなさんに緊急なお知らせです。
どうやら、自分のメールアドレスが乗っ取られたようです。
自分のメルアドからのメールは削除するか無視してください。
あちこちで身に覚えのない自分からのメールが送られていると友人から電話がありました。
ですので、しばらくはこのSNSからも消えます<<<
「そうだったんだ。いろいろ大変だったんだな」
ボクは独りごとをつぶやきながら、画面上を移動する投稿を何気なく読みながら、さらにスクロールを続けました。
と、ある一文でボクのマウスのスクロールボタンの指は止まりました。
Sさんのハンドルネームがもう一個あったのです。投稿日時は亡くなった当日の明け方でした。
>>なんか、もうみんなイヤになっちゃったな。なんでかな。も、どこか遠くへ行きたい。<<<
という短い文でした。
この投稿がSさん本人なのか、乗っ取ったヤツなのかは分かりません。
-----------------------------------------
SNSからアクセスできるSさんのフェイスブックには、彼が亡くなった日も含め、現在もたまにアップされます。
どうやら、「乗っ取った誰か」はSさんが亡くなったことをまだ知らないようで、成り済まして投稿しています。
ただ、「乗っ取った誰か」の投稿はSさんと錯覚するほど内容も文章も似ています。
葬式の日の投稿は
>>
今日は、子供たちがたくさん来てくれてうれしかった。また次の試合も頑張ろうな<<<
でした。
2015年01月29日 17:29
群青 ---- マリンブルー ----
人の感情は、時として「色彩」から影響をうけることがあるそうです。
たとえば、アメリカンフットボールなどの激しいスポーツのロッカールームは赤が基調となっていて、試合前の選手の闘志をかきたてるといいます。逆にピンクは心を落ち着かせるそうで、刑務所の壁などに塗られているそうです。
以前、ボクはある無人島に渡りました。
無人島といっても陸地から50メートルほどしか離れていなく、しかも周囲100メートル足らずの島で、島というより「離れ岩」といったほうが近い感じでした。その島は1970年代の海洋博ブームを当て込んで当時レジャー施設が造られましたが、海洋博が不発に終わり、結局一度もオープンすることなく放置された島でした。
ボクの目的は、その取り残された島の残骸を撮影することでした。
地元の漁師さんに船外機付きの小さな船で島に渡してもらい、二時間後に迎えにきてくれるようお願いし上陸しました。
真っ青な空に痛いほどの太陽が照りつける真夏でした。島の周辺は真っ白な砂地の浅瀬で、真夏の太陽を倍増して反射しているようでした。
突貫工事で造ったであろう当時の島の桟橋は半分から折れ、手前に大きく傾いていました。赤さびた鉄筋がようやくコンクリートの塊をつなぎとめているようで、長い間波の浸食をもろに受けているようでした。
崩れかけた桟橋に気をつけながら島の内部へ歩を進めました。
島全体がコンクリートの建物で覆われている感じでしたが、近づいて観ると島に元々あったらしい洞窟を利用した一階と、その上部に建てられた二階部分になっていました。
恐る恐る一階に入ってみました。
内部は洞窟の地形を巧みに利用した水槽がいくつか並んでいて、どうやらミニ水族館を造ろうとしたようでした。
外の、ホワイトアウトするほどの明るさと対比するように洞窟内は暗く、不気味でした。
水槽のガラスはすべて割れ、潮がこびりついた内部に魚や生き物は当然いません。生き物の気配はまったくせず、そのことが一層の不気味さを醸し出しているようでした。生き物の代わりに、何か得体の知れない「モノ」がすべての水槽に詰め込まれているようでした。
洞窟水族館を抜け、二階に上がりました。
二階部分は、和風レストランをモチーフにしたような感じの造りでした。
壁は崩れ落ち、床も所々抜けていました。わずかに残った赤いカーペットがどす黒く床に貼りついていました。
レストランには大きな窓が四方にあり、座敷から海を眺められるようになっていました。窓のガラスは割れはて、窓枠が外の景色を切り取っていました。
西側の窓から外を眺めたボクは、次の瞬間、記憶が飛んだような錯覚に陥りました。
景色が「青色」の洪水なのです。見たこともない強烈な「青」が広がっているのです。
青に飲み込まれ、溺れてしまう感覚なのです。
そして、視覚が、その青に絡みとられたように身動きができないのです。
自分の思考や存在が「青」の中に吸収され、溶け込んでしまうほどなのです。
息の詰まる、畏ろしい「青」なのです。逃げなきゃいけないのに、逃れられない「青」なのです。
一面の青に張り付けられてしまって身動きがとれないのです。
色に、足がすくんでしまって動けないのです。
どれほどの時間が経ったのでしょうか・・・
背後で呼び掛ける声にボクはようやく我に返りました。後ろには送ってもらった漁師の方が立っていました。
二時間後、という約束だったが、気になって一時間で迎えにきた、と心配そうな顔で言っています。
気が付けば、ボクは一時間も「青」に魅入られて動けない状態だったのです。
帰路の船の中、漁師の方が独りごとのように言うのでした。
「・・・実は、一日だけこの島、オープンしたんですよ。部落(シマ)の人招待してね。みんなで船で渡って。・・・ご馳走食べていたら・・・なんでか、いる子供がみんな、魂(マブイ)落としたようにトゥルバッテよ。外見て、『海怖いって』、『青色が来るって』・・・なんでかねぇ・・・こんな暑い日だったさぁ、自分には分からないけど・・・」
たとえば、アメリカンフットボールなどの激しいスポーツのロッカールームは赤が基調となっていて、試合前の選手の闘志をかきたてるといいます。逆にピンクは心を落ち着かせるそうで、刑務所の壁などに塗られているそうです。
以前、ボクはある無人島に渡りました。
無人島といっても陸地から50メートルほどしか離れていなく、しかも周囲100メートル足らずの島で、島というより「離れ岩」といったほうが近い感じでした。その島は1970年代の海洋博ブームを当て込んで当時レジャー施設が造られましたが、海洋博が不発に終わり、結局一度もオープンすることなく放置された島でした。
ボクの目的は、その取り残された島の残骸を撮影することでした。
地元の漁師さんに船外機付きの小さな船で島に渡してもらい、二時間後に迎えにきてくれるようお願いし上陸しました。
真っ青な空に痛いほどの太陽が照りつける真夏でした。島の周辺は真っ白な砂地の浅瀬で、真夏の太陽を倍増して反射しているようでした。
突貫工事で造ったであろう当時の島の桟橋は半分から折れ、手前に大きく傾いていました。赤さびた鉄筋がようやくコンクリートの塊をつなぎとめているようで、長い間波の浸食をもろに受けているようでした。
崩れかけた桟橋に気をつけながら島の内部へ歩を進めました。
島全体がコンクリートの建物で覆われている感じでしたが、近づいて観ると島に元々あったらしい洞窟を利用した一階と、その上部に建てられた二階部分になっていました。
恐る恐る一階に入ってみました。
内部は洞窟の地形を巧みに利用した水槽がいくつか並んでいて、どうやらミニ水族館を造ろうとしたようでした。
外の、ホワイトアウトするほどの明るさと対比するように洞窟内は暗く、不気味でした。
水槽のガラスはすべて割れ、潮がこびりついた内部に魚や生き物は当然いません。生き物の気配はまったくせず、そのことが一層の不気味さを醸し出しているようでした。生き物の代わりに、何か得体の知れない「モノ」がすべての水槽に詰め込まれているようでした。
洞窟水族館を抜け、二階に上がりました。
二階部分は、和風レストランをモチーフにしたような感じの造りでした。
壁は崩れ落ち、床も所々抜けていました。わずかに残った赤いカーペットがどす黒く床に貼りついていました。
レストランには大きな窓が四方にあり、座敷から海を眺められるようになっていました。窓のガラスは割れはて、窓枠が外の景色を切り取っていました。
西側の窓から外を眺めたボクは、次の瞬間、記憶が飛んだような錯覚に陥りました。
景色が「青色」の洪水なのです。見たこともない強烈な「青」が広がっているのです。
青に飲み込まれ、溺れてしまう感覚なのです。
そして、視覚が、その青に絡みとられたように身動きができないのです。
自分の思考や存在が「青」の中に吸収され、溶け込んでしまうほどなのです。
息の詰まる、畏ろしい「青」なのです。逃げなきゃいけないのに、逃れられない「青」なのです。
一面の青に張り付けられてしまって身動きがとれないのです。
色に、足がすくんでしまって動けないのです。
どれほどの時間が経ったのでしょうか・・・
背後で呼び掛ける声にボクはようやく我に返りました。後ろには送ってもらった漁師の方が立っていました。
二時間後、という約束だったが、気になって一時間で迎えにきた、と心配そうな顔で言っています。
気が付けば、ボクは一時間も「青」に魅入られて動けない状態だったのです。
帰路の船の中、漁師の方が独りごとのように言うのでした。
「・・・実は、一日だけこの島、オープンしたんですよ。部落(シマ)の人招待してね。みんなで船で渡って。・・・ご馳走食べていたら・・・なんでか、いる子供がみんな、魂(マブイ)落としたようにトゥルバッテよ。外見て、『海怖いって』、『青色が来るって』・・・なんでかねぇ・・・こんな暑い日だったさぁ、自分には分からないけど・・・」
2013年06月19日 18:13
手
趣味、というほどではありませんが考古学にはちょっと興味があります。
特に白亜紀やジュラ紀といった恐竜が闊歩していそうな時代の古生物の化石には心魅かれるものがあります。
「○○ザウルスの足の骨」とか「翼竜の羽の先端の骨」「古代サメの歯の化石」等々、現代では絶滅してしまった生物を化石の一部から想像するのは楽しいし、ロマンがあると思うのです。絶滅した生物や希少な生き物は、その「一部」でも貴重だし、なにかしらのロマンを掻きたてるものを孕んでいると思うのです。
ただ一方で、それがありきたりのもの、当たり前に存在するものの「一部」には、なにかしらの恐怖や違和感が潜んでいるように思えてなりません。
・・・・こういう体験をしました。
今年三月、ボクは久しぶりに沖縄本島北部の水族館に向かいました。数日間の雨模様の晴れ間で蒸し暑い日でした。
週末や休日の混雑を避け、水族館の展示をじっくり見て回る予定で平日の木曜日を選んで行ったのですが、あてが外れました。当日は修学旅行の一団や海外からの団体、ツアー旅行客など大変な人出でした。
エントランスから入館した途端、すでにすし詰め状態です。最初こそ渋滞の列に並んでナマコやらヒトデやらの展示物を触り、順序よく小さな水槽の魚など眺めていたのですが、なかなか前に進みません。蒸し暑い日に加え、人いきれで管内はいっそう不快指数MAX状態でした。
そのうち、込んでいる展示コーナーは避けて、比較的人の少ない(おそらく人気がないのでしょう)コーナーに移動しました。
向かったコーナーは仄暗く、ブルーのバックライトに「深海の小さな生き物」と記されています。
たぶん深海の高水圧仕様なのでしょうか、小さなキューブ型の水槽が上下二層に20個ほどあり深海の小型生物が個別に展示されています。下の方の水槽は腰をかがまないと見えないほど低い位置にありました。
「ふむふむ・・・」
ボクは、展示された生き物の説明プレートを一個一個読みながら、じっくり観察し、ゆっくりと移動しました。このコーナーだけほとんど足を止める人がいなく、スムーズに見学できました。
・・・と、中ほどの水槽のひとつにボクの足は止まり、目が釘付けになりました。
手、人間の手が水槽の中にあるのです。正確に言うと、10センチくらいの赤いエビ(深海に生息するエビだそうです)を掌に乗せた手が水槽の中にあるのです。
「えっ!」
ボクは目を見開き、見返しました。
確かに水槽の中に手首から先の手があるのです。掌のエビも手も身じろぎひとつしません。手のオブジェにしてはリアルすぎます。肌の色も指紋も毛も爪も毛穴も・・・どう見ても「本物」の人間の手なのです。小さめの男性の手のようです。水の満たされた30センチ四方の水槽の向こう側から手がニョキっと生え、エビをやさしく握っているのです。水槽はアクリル板だと思うので、腕を貫通させられるとは、とても思えません。長時間水に浸かっていたようで白っぽくふやけています。生身の人間の腕を切り落として展示している様なのです。もちろん説明板に「手」のことなど一切触れられていませんでした。
「・・・俺だけ?」
ボクの後ろで、観光客らしき若い男性が覗き込んで呟いています。
「・・・見えるの俺だけじゃないよな?お前も見えるよな?」
若い男性は、となりの男性に確認するように小声で質しています。
「んー・・・」
そう唸ったきり男性は黙っています。
ボクは一旦他の水槽に移動し、何もなかったそぶりで他の展示物を眺めました。もちろん、他の展示物の内容が頭に入るわけがありません。どうしてもさっきの「手」が気になって仕方がありませんでした。ボクは意識して呼吸を整え、さりげなく進路を戻り、極力何気ないそぶりでさっきの水槽を覗き込みました。
・・・やっぱり「手」は存在し、微動だにしていません。深海エビもピクリとも動きません。死んだようにも弱っているようにも見えます。
「・・・弱ったエビを介抱でもしているのかな。・・・それとも人間の手とエビの大きさの比較・・・」
ボクは無理やり自分を納得させるように考えを巡らせましたが、どうも腑に落ちません。
仄暗い「深海の小さな生き物」コーナーの水槽から距離を取り、壁際に寄り掛かってしばらく見学者をぼんやり眺めました。
ほとんどの人が「手の水槽」を一瞥して通り過ぎて行きます。「手」が見えているのか、見えていないのかボクにはわかりません。尋ねる勇気もありませんでした。
その日、もやもやした気分を抱えたまま帰宅しましたが、床についてもあの「手」が頭から離れませんでした。
・・・・翌朝もとうとう、あの「手」が頭から離れませんでした。どうしても「手」のことが気になったボクは、仕事を早めに切り上げ、二時間半かけて水族館に車を飛ばしました。チケットを購入し、他の展示コーナーには見向きもせず、仄暗い「深海の小さな生き物」コーナーへとまっすぐ向かいました。
はやる気持ちを抑えつつ、あの水槽を覗き込みました。
薄暗いアクリルキューブの水槽には、「手」はなく、赤い深海エビが一匹、時折短い触角をゆっくり揺らしながら、ブラックライトに照らされた白い目でただこっちを見ているのでした。
2013年06月17日 17:08
ヤギの報い
ぐずついた天気がしばらく続いた木曜日の午後でした。
その日も夜明け前からしょうしょうと細かい雨が降っていましたが、正午を過ぎたころから雨は上がり、薄曇りに陽光が射すようになっていました。空のところどころに細い青空ものぞいていました。
南城市のとある病院の機械室で早朝から作業をしていたボクが機械室を出たのは、ちょうど空に光が戻りはじめた正午すぎでした。
ボクは別の仕事の移動ため、その病院を後にし、車に乗り込みました。車に置いた傘はまだ乾ききっていませんでしたが、日当たりのいい道路は乾いていました。
暗い機械室からの解放と久しぶりの明るい空で気分は高揚していました。
那覇空港自動車道・南風原南IC高架下の県道を南下し、勾配のきつい坂を登り切ったところで信号に引っ掛かりました。
隣の車線には、一台の白い軽トラックが並んで止まっています。
強い視線というか・・・なにかすごい違和感を感じたボクは、左を振り向き軽トラックの荷台を見ました。ギョッとしました。ボクの視線のほんの70センチほど先に大きな白い顔がこっちを覗き見ているのです。体高1メートル以上はありそうな真っ白な大きなヤギでした。
「おい、脅かすなよ・・・」
ボクは小さく独りごとを云い、ヤギを見つめました。
立派な真っ直ぐな角のあるヤギで、ブルーがかった横長の瞳孔は身じろぎもせずボクを見つめています。何かボクに言いたげでした。
「なんだよぉ」
しばらくにらめっこしましたが、もちろんヤギがしゃべるわけがなく、テレパシーが聞こえるワケもないので意味など分かりません。ただ横に止まった車の荷台にヤギがいただけだと思いました。そのときは。
-------- 80分後 ---------
用事を終え、ボクは那覇市内での仕事の打ち合わせのため国道331号を那覇向け車を走らせていました。
赤嶺駅を右折し、近道をするために裏通りの市道に入りました。
前方の信号が青から黄色に変わったので減速し、信号手前で停車しました。
2車線ですが右車線は右折専用の車線で、ボクは右折車線に止まっています。後続の車がゆっくりと直進車線にすべりこんできました。
なにげに左側に視線を振ったぼくはギョッとしました。
直進車線に止まったのは白の軽トラック。しかも荷台に大きな白いヤギが積まれています。
「うそだろ!?」
「デジャヴ?」
ボクは小さく独りごとを云い、苦笑気味にヤギを見つめました。
すっかりさっきのヤギのことは忘れていましたが、瞬時に思い返しました。
ヤギもボクを見つめています。
さっきのヤギと大きさも白さも同じくらいですが、明らかに違うヤギです。
曲がった角の形と長いあごひげのヤギです。軽トラックを運転している人も車両も違っていました。
でも、ブルーがかった横長の瞳孔は身じろぎもせずボクを見つめています。何か言いたげでした。口をモゴモゴ横に反芻しているのですが、もちろん意味などわかりません。
何かに憑かれたような、複雑な感情を覚えたボクでしたが、約束の打ち合わせの時間がせまっているので急ぎ、その場を去りました。
----- それから80分後 ------
打ち合わせはスムーズに済み、ボクは帰社するために国道331号を走っていました。
携帯が鳴ったので、路肩に車を停め出ました。
与那原の取引先からでした。サーバ機の動きがおかしいので急ぎチェックしてほしい、との電話でした。
国道からそのまま那覇空港自動車道に乗り、南風原北ICで降りて取引先に向かいました。
サーバ機はちょっとしたトラブルで、難なく解決出来たので30分ほどで取引先を後にしました。来た道順をそのまま引き返し、与那原街道を南風原北ICに向かいました。
夕方のラッシュに捕まったらしく、与那原十字路あたりからひどい渋滞でノロノロと走行しています。どうやら南風原北IC入口あたりまで車列は繋がっているようです。まいったな、ボクは小さく独り言を云いました。
難所の与那原十字路をようやく抜けた車列は、蠢くムカデのようにだらだら坂をゆっくりのぼっては止まるを繰り返しています。
30メートル先の信号が3回目の青でようやく進んだかと思ったら、信号機手前で赤に変わり車列の一番前で信号待ち停車しました。
正面の渋滞の遥か先に濃い色の夕焼け空が一層暗い色を重ねています。
イライラしながら、ふと、信号待ちの隣の車線に目をやり、ボクは凍りつきました。
白い軽トラック。荷台にヤギ。しかも間違いなくボクを見つめているのです。今日の二匹とも違うヤギです。大きく白いのですが、角のないヤギでした。
ブルーがかった横長の瞳孔は身じろぎもせずボクを見つめています。何か言いたげでした。ボクに意味などわかりません。
得体の知れない恐怖と深淵のモヤモヤと渋滞のイライラと・・・おまけにポツポツ雨まで落ちてきやがった・・・
なんなんだよ、これは
2013年05月22日 18:39
理不尽
ひょんなことでアメリカの理不尽さに遭遇してきました。
---- 出来事 上巻 -------
先月、急な所用でカナダのトロントへ行くことになりました。アメリカではありません。
ボクはそんなに裕福ではありませんから、自分で格安の航空券を手配し、現地の安宿をネットで予約して沖縄を出発しました。
手配した国際便は成田発アメリカ経由トロント行きの便で、乗り継ぎ(トランジット)時間も含めると、21時間というハードなフライトでした。直行便の半額以下の料金でしたので、やむなく購入した、という次第です。もちろんエコノミークラスでした。
沖縄--→ 成田--→ ロサンゼルスと、ここまでは順調でしたが、問題は米国での乗り継ぎでした。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、米国での乗り継ぎは一旦アメリカの入国審査を受け空港に下り、出発地で預けた荷物を取って、また預け直し、異常なほど厳しい搭乗チェックを受け、ようやくカナダ行きの飛行機に乗れるのです。
アジア諸国やヨーロッパでの乗り継ぎは何度か経験があったので知っていましたが、アメリカのトランジットは初めて。理不尽この上ありません。
---- まず、入国審査のゲートに並ばされます。
これは想定内です。ただ、何度も列の途中から他のゲートの列の後尾へと移動させられ(ボクは二回で済みました)、ようやく自分の審査の番がきたかと思ったら、いきなりこのゲートは閉鎖され、また他のゲートへ移動です。
・・・ガマンガマン。
---- 並び直して、待つこと1時間半。
やっと、今度こそボクの番です。ボクの前のインド人(に見えました)と、その前の家族連れがなぜか大声で怒られ、最後尾に並び直されています。
・・・ちょっと不安
---- ここからは英語のやり取りでした。(ボクは英語はぜんぜん得意ではありません。念のため)
入国審査官:『どこ行くんだい?』
ボク:「カナダ。乗り継ぎ」
『どこから来たんだ?』
「日本」
『独り?』
「はい。観光」
・・・この時点でボクは怪しまれているようです。
『チケットは持っているのか?飛行機の』
「これだ」
『搭乗券じゃだめだ。予約した飛行機のチケット全部見せろ。帰りのやつも全部。eチケットも』
「だからこれだ」
『ちゃんと開いて見せろ』(腕を組んだまま)
『こっち向けろ』(腕を組んだまま)
『ESTAはあるな?』
「払った」
『出入国カードを出せ』
「これだ」
『どこから来たんだ?』
「日本。東京成田」
『アメリカはどこ行くんだ?』
「乗り継ぎ。カナダ・トロントへ行く」
『アメリカはどこに泊るんだ?』
「アメリカは泊らない」
『アメリカの連絡先を書け!』
「乗り継ぎだからない」
『書け!』
「は?」
『書け!!』
「はい?」
『書けい!!!』(腕を組んだままふん反り返る)
・・・も頭の中真っ白
『書けい!!!』(腕を組んだまま、さらにふん反り返る)
「トロントでいいか?」
『書けい!!!』
・・・えーいもぉ、トロントのホテル住所書いちまえ。あと乗り継ぎってことを。
----審査官は無言のまま、ボクの書類を投げ出して、次の人を呼んでいる。
これでよかったのか? 行っていいの? 釈放? よかったー!
帰国した後、アメリカによく行く知人に聞いたら。
「優しい審査官でよかったね。強制退去(帰国)させられる人も中にはいるみたいだから」
だそうです。団体と違って、年配の独り旅は「怪しい対象」だそうです。
---- 成田で預けたバッグを探すのも一苦労でした。入国審査で時間くっている間に、もうどこに行ったのかわかりません。香港から来たという女の子が自分のバッグがないって、ボクに訊いてきたけど、ボクのも捜索中なんだよね。
ラッキーなことに、空港内の荷物係のおっちゃんが気のいい人(ウィッキーさんにそっくり)だったんで、いっしょに探してもらって、なんとか自分のバッグを見つけました。サンキュー!ウィッキーさん。
で、また並んで、税関の申告品はないかしつこく訊かれ、ようやくカナダ行きに預け直しました。飛行機を降りてから、すでに3時間以上もかかっています。
ロサンゼルス空港はおもいのほか広く、建物もいくつかあります。カナダ行きのエアーカナダが就航するのは、どうやら別の建物のようです。国際線のビルからいったん外に出て、歩いて隣のエアーカナダ線の出発するビルへ移動するのです。
・・・親切なことに案内標識などはありません。
カンを頼りに、58号線の歩道みたいなところを何百メートルか歩いてようやく発見。どこか地方の商店街みたいなアーケードです。
---- で、ここからはチェックゲートの係員と英語のやり取りでした。(ボクは英語はぜんぜん得意ではありません。念のため)
係員:『どこ行くんだい?』
ボク:「カナダ。乗り継ぎ」
『脱いで』
「はい?」
『ベルト』
「ああ、はいはい」
『靴も脱いで』
「靴?靴下も取ろうか?靴下はいいの?OK」
・・・チェックゲートったって、アーケード二階の通路脇にゲートが置かれただけの質素さです。
通行人がみんな見ていくもん。
質素な割には最新機器らしく全身レントゲン式のスキャナーです。
隣の女性用のスキャナー隠せよ。見えてるぞ。ええー、いいのか?プライバシーはいいのか?
『はい、では腕上げて。足も』
・・・あれ、これどこかで見た・・・ああー、そうそう刑務所の映画でみた入所時のカンカン踊りだな。
・・・通行人見ているって。恥ずかしい・・・
などなど、屈辱的な乗り継ぎを経て、カナダへ無事辿り着きました。現地時間、深夜12時半でした。
---- 出来事 下巻 -------
カナダ--→サンフランシスコ--→成田と、帰りはまた米国での乗り継ぎでした。なぜか、カナダ(バンクーバー)の空港内に、アメリカの入国審査があるのです。カナダ国内でアメリカの入国審査なのです。
---- まず、入国審査のゲートに並ばされます。
これは想定内です。並んで待つこと30分、ようやく審査官がコーヒー片手にやってきました。来たと思ったら、同僚同士でおしゃべりしてなかなか業務を始めません。審査を待つ列は3列。かなりの数の人が並んでいます。3列の先に審査ボックスが8つ。一時間ほどしてやっと係員が8席に座って、審査開始のようです。
・・・ガマンガマン。
---- 待つこと1時間ちょい。
ボクの列の担当官はかなりの潔癖症らしく、除菌シートであらゆるところを拭き、ボックス内に霧ができるほど除菌スプレーを吹きつけています。
・・・ちょっと不安
---- 待つことさらに30分。
もうすぐボクの番です。ボクの前のカナダ人のおばちゃんがなぜか大声で怒られ、怒鳴られています。
車椅子の旦那さんを押してきて、二人分の入国審査を代わりにおばちゃんがしようとして怒鳴られているようです。書類に不備があったようで大声で注意されています。車椅子の旦那さんが心配そうに見ています。
結局書き直しを命じられ、列の横に並び直されて、待たされています。旦那さんが「ソーリー、ソーリー」と何度も言っています。
・・・カナダ人がカナダ国内でアメリカ人に怒鳴られているのです。もっと言い方があるんじゃないかな? いやだな・・・
---- ここからは英語のやり取りでした。(ボクは英語はぜんぜん得意ではありません。念のため)
入国審査官:『旅行の目的は?』
ボク:「帰国」
『どこ行くのか?』
「日本」
『どこ行ったのか?』
「カナダだけ。」
『どこ?』
「トロントやケベック、ナイアガラなど」
『なにしに?』
「バケーション」
『あちこち?』
「はい」
『ふーん・・・バケーションねえ・・・』
----で、OKでした。
入国審査のブースには、大きなポスターが貼ってあり「We are NATIONAL FACE」って書いてありました。
NATIONAL FACE ねぇ・・・んー・・・
2012年10月24日 19:08
赤子の泣き声
このところ沖縄に接近する台風が強大化しているように思います。
台風の過去・現在の数値的な比較はよくわかりませんが、ボクの幼かった昭和中ごろの台風は今より凄まじく、猛烈なものでした。
当時、ボクの近所は瓦屋の木造がほとんどで、実家もそうでした。
台風が近づくと、いっせいに戸袋から雨戸を出して閉め、さらに五寸釘や角材で堅く戸締りをしました。
散乱しそうな屋外の家財は床下や土間に収納し、飛ばされそうなモノはすべてロープでがっちりと固定していました。それがいつもの台風対策でした。
---- ある秋口に台風が襲来しました。
ラジオの台風情報では、「例年になく強い台風」と伝えていました。
暴風域に入るのが日暮れ前、という情報だったのでボクらは早々といつもの台風対策を終え、家に籠りました。
ほどなく停電し、じっとりと湿気を含んだ闇に変わりました。
そして早目の夕食をろうそくの明かりの下でを済ませました。
---- 風が徐々に強まっていました。
最初のうちはトランジスタラジオに耳を傾けたり、トランプや花札で時間をつぶすのですが、そのうちに飽きて、押し黙ってろうそくの炎をぼんやり見つめていました。
台風の夜の時間はなぜか遅く進む感じでした。
---- 古い柱時計が11時を鳴らしています。風はますます強まっていました。
床に入り、目を閉じるのですが眠れません。まとわりつくような湿気で寝苦しい夜でした。
ゴウッっと鳴った一陣の風で屋根の瓦が飛んだようで、パリンと砕け散る音が聞こえました。
---- 夜半に差しかかりましたが、風は一向におさまりません。
飛ばされた瓦の砕ける音が頻繁に聞こえます。
家の梁が強風でギシギシときしむ音がします。
電線のピューッという風切り音が一層甲高く響いていました。
---- 柱時計が深夜の2時を打っています。
ゴウッという風音が吹き、外が一瞬静かになった感じがしました。
と、電線のピューピューっという音にまぎれて、かすかに「ホギャー」っという赤子の声が聞こえたような気がしました。
耳を澄ませると、かすかですが、たしかに赤子の泣き声が風に乗って聞こえてきました。
夜泣きしているような泣き声でした。小さな泣き声でした。
「大変だな、台風の夜なのに・・・」
闇の中で、ボクはつぶやきました。
「・・・もう早く寝なさい」
そばで横になっていたおばあちゃんが、静かにたしなめるように言っています。
ホギャーホギャーホギャー、赤子の泣き声は、さっきよりはっきり聞こえてきました。
聞こえてきたというより、近づいて来ている感じでした。
「やっぱり泣いているよ、赤ちゃん」
ボクは、闇の中のおばあちゃんに言いました。
「いいから、早く寝なさい!」
おばあちゃんは、小声ですが怒っているような強い口調になっていました。
---- 台風の吹き返しになったのか、風向きが変わり猛烈な風雨になっていました。
外は暴風の吹き荒れれている様で、すべての音を巻き込んでいるような風の轟音でした。
そんな轟音を切り裂いて、赤ちゃんの泣き声は、さっきよりはっきり大きく聞こえます。
まるで、雨戸のすぐ外で泣いているかのようでした。
誰かに抱かれて泣いているようでした。
ボクは耳を塞ぎ、目を強くつぶって毛布の中に潜りこみ、息を殺しました。
時の過ぎるのが、ものすごく長く感じられました。
---- 台風一過の翌日 -----
昨夜の出来事を家族に話しました。
不思議なことに誰も赤ちゃんの泣き声を聞いていないようでした。
ただ、おばあちゃんだけは困ったような顔で唇を結んでいました。
あの赤子の泣き声はいったい・・・・・
台風の過去・現在の数値的な比較はよくわかりませんが、ボクの幼かった昭和中ごろの台風は今より凄まじく、猛烈なものでした。
当時、ボクの近所は瓦屋の木造がほとんどで、実家もそうでした。
台風が近づくと、いっせいに戸袋から雨戸を出して閉め、さらに五寸釘や角材で堅く戸締りをしました。
散乱しそうな屋外の家財は床下や土間に収納し、飛ばされそうなモノはすべてロープでがっちりと固定していました。それがいつもの台風対策でした。
---- ある秋口に台風が襲来しました。
ラジオの台風情報では、「例年になく強い台風」と伝えていました。
暴風域に入るのが日暮れ前、という情報だったのでボクらは早々といつもの台風対策を終え、家に籠りました。
ほどなく停電し、じっとりと湿気を含んだ闇に変わりました。
そして早目の夕食をろうそくの明かりの下でを済ませました。
---- 風が徐々に強まっていました。
最初のうちはトランジスタラジオに耳を傾けたり、トランプや花札で時間をつぶすのですが、そのうちに飽きて、押し黙ってろうそくの炎をぼんやり見つめていました。
台風の夜の時間はなぜか遅く進む感じでした。
---- 古い柱時計が11時を鳴らしています。風はますます強まっていました。
床に入り、目を閉じるのですが眠れません。まとわりつくような湿気で寝苦しい夜でした。
ゴウッっと鳴った一陣の風で屋根の瓦が飛んだようで、パリンと砕け散る音が聞こえました。
---- 夜半に差しかかりましたが、風は一向におさまりません。
飛ばされた瓦の砕ける音が頻繁に聞こえます。
家の梁が強風でギシギシときしむ音がします。
電線のピューッという風切り音が一層甲高く響いていました。
---- 柱時計が深夜の2時を打っています。
ゴウッという風音が吹き、外が一瞬静かになった感じがしました。
と、電線のピューピューっという音にまぎれて、かすかに「ホギャー」っという赤子の声が聞こえたような気がしました。
耳を澄ませると、かすかですが、たしかに赤子の泣き声が風に乗って聞こえてきました。
夜泣きしているような泣き声でした。小さな泣き声でした。
「大変だな、台風の夜なのに・・・」
闇の中で、ボクはつぶやきました。
「・・・もう早く寝なさい」
そばで横になっていたおばあちゃんが、静かにたしなめるように言っています。
ホギャーホギャーホギャー、赤子の泣き声は、さっきよりはっきり聞こえてきました。
聞こえてきたというより、近づいて来ている感じでした。
「やっぱり泣いているよ、赤ちゃん」
ボクは、闇の中のおばあちゃんに言いました。
「いいから、早く寝なさい!」
おばあちゃんは、小声ですが怒っているような強い口調になっていました。
---- 台風の吹き返しになったのか、風向きが変わり猛烈な風雨になっていました。
外は暴風の吹き荒れれている様で、すべての音を巻き込んでいるような風の轟音でした。
そんな轟音を切り裂いて、赤ちゃんの泣き声は、さっきよりはっきり大きく聞こえます。
まるで、雨戸のすぐ外で泣いているかのようでした。
誰かに抱かれて泣いているようでした。
ボクは耳を塞ぎ、目を強くつぶって毛布の中に潜りこみ、息を殺しました。
時の過ぎるのが、ものすごく長く感じられました。
---- 台風一過の翌日 -----
昨夜の出来事を家族に話しました。
不思議なことに誰も赤ちゃんの泣き声を聞いていないようでした。
ただ、おばあちゃんだけは困ったような顔で唇を結んでいました。
あの赤子の泣き声はいったい・・・・・
2012年09月12日 18:07
香り ---- パフューム ----
見る、聞く、味わう、嗅ぐ、触れるといった人間の五感の中で、最も強烈に記憶と結びついているものが嗅覚だそうです。
人は見たり聞いたりした記憶より、「におい」を伴う記憶を、より鮮明に深く心に刻みつけるそうです。
以前、こういう話を聴きました。
Gさんは大正生まれのご高齢の女性で那覇市に住んでいます。ご高齢にかかわらず、心身ともに健やかで、とくに記憶力の確かさは驚くほどの方でした。そのGさんに戦時中の話を聴かせていただいたときの話です。
----------------------------------
敗戦が濃厚となった昭和20年3月。
Gさんは、幼い子供ふたりを引き連れて戦禍激しい南部を逃げ惑っていました。
「昼はガマや岩陰に隠れて、夜・・・こう、這うように逃げるわけ。昼でも夜でも、艦砲パーラナイ。家も山も焼けて、みんな真っ黒。死体もたくさんあって、最初は怖かったけど、あとは、もう、慣れてしまって怖いともなんとも思わなくなって・・・」
でも・・・とGさんは、少し間をおいて続けました。
「でも・・・あの、なんていうかね、臭い・・・あの臭いだけは慣れないね、というか忘れられないね。ガマの中の臭いとか、死んだ人の臭いとか、血の溜まった泥水の臭いとか・・・」
戦後数十年が経った今でも時々、その時の「臭い」がふっとよみがえり、それに触発されるように、その時・その場所の記憶がはっきりとフラッシュバックするそうです。
「今でも、なんかの拍子に、その臭いがするときあるよぉ。戦争の臭いだねえ・・・いやだねぇ、なんでかねぇ・・・もお、はっきり思い出して、怖いやら悲しいやら悔しいやら・・・消えないねぇ・・・」
----------------------------------
ボクは、戦争を経験したことがないので、戦争当時の様子も「におい」も分かりません。
「におい」と記憶が、どうして結びつくのかも分かりません。ただ、最近、こんな経験をしました。
「慰霊の日」の翌日、ボクは糸満市摩文仁の「平和の礎」へ行きました。
「慰霊の日」当日の混雑を避け、戦没者とボクの祖先への慰霊のためでした。
---- その日深夜。
さほど寝苦しくも、悪夢を見たわけでもないのですが、いきなり目が覚めました。
なぜか「沈丁花」の香りがした、と感じて目が覚めたのです。身体を起こして周囲を嗅ぎましたが、もちろん、沈丁花などないし、香りもしませんでした。
---- さらにその翌日。
不思議なことに、昨日の夜とまったく同じ状況、時刻に・・・「沈丁花」の香りで目覚めました。
ボクは香水をつけないし、「沈丁花」に関わる心当たりもないし、ボクの記憶の中で「沈丁花」に関連するような想い出もないはずなのに。
・・・電話が鳴ったのは、その日の正午ごろでした。
ボクの叔母が亡くなったとの訃報でした。何十年も音信をとっていなかった叔母の突然の死でした。幼いころ、よく遊んでもらった叔母でした。
沈丁花の香水が好きな叔母でした。
人は見たり聞いたりした記憶より、「におい」を伴う記憶を、より鮮明に深く心に刻みつけるそうです。
以前、こういう話を聴きました。
Gさんは大正生まれのご高齢の女性で那覇市に住んでいます。ご高齢にかかわらず、心身ともに健やかで、とくに記憶力の確かさは驚くほどの方でした。そのGさんに戦時中の話を聴かせていただいたときの話です。
----------------------------------
敗戦が濃厚となった昭和20年3月。
Gさんは、幼い子供ふたりを引き連れて戦禍激しい南部を逃げ惑っていました。
「昼はガマや岩陰に隠れて、夜・・・こう、這うように逃げるわけ。昼でも夜でも、艦砲パーラナイ。家も山も焼けて、みんな真っ黒。死体もたくさんあって、最初は怖かったけど、あとは、もう、慣れてしまって怖いともなんとも思わなくなって・・・」
でも・・・とGさんは、少し間をおいて続けました。
「でも・・・あの、なんていうかね、臭い・・・あの臭いだけは慣れないね、というか忘れられないね。ガマの中の臭いとか、死んだ人の臭いとか、血の溜まった泥水の臭いとか・・・」
戦後数十年が経った今でも時々、その時の「臭い」がふっとよみがえり、それに触発されるように、その時・その場所の記憶がはっきりとフラッシュバックするそうです。
「今でも、なんかの拍子に、その臭いがするときあるよぉ。戦争の臭いだねえ・・・いやだねぇ、なんでかねぇ・・・もお、はっきり思い出して、怖いやら悲しいやら悔しいやら・・・消えないねぇ・・・」
----------------------------------
ボクは、戦争を経験したことがないので、戦争当時の様子も「におい」も分かりません。
「におい」と記憶が、どうして結びつくのかも分かりません。ただ、最近、こんな経験をしました。
「慰霊の日」の翌日、ボクは糸満市摩文仁の「平和の礎」へ行きました。
「慰霊の日」当日の混雑を避け、戦没者とボクの祖先への慰霊のためでした。
---- その日深夜。
さほど寝苦しくも、悪夢を見たわけでもないのですが、いきなり目が覚めました。
なぜか「沈丁花」の香りがした、と感じて目が覚めたのです。身体を起こして周囲を嗅ぎましたが、もちろん、沈丁花などないし、香りもしませんでした。
---- さらにその翌日。
不思議なことに、昨日の夜とまったく同じ状況、時刻に・・・「沈丁花」の香りで目覚めました。
ボクは香水をつけないし、「沈丁花」に関わる心当たりもないし、ボクの記憶の中で「沈丁花」に関連するような想い出もないはずなのに。
・・・電話が鳴ったのは、その日の正午ごろでした。
ボクの叔母が亡くなったとの訃報でした。何十年も音信をとっていなかった叔母の突然の死でした。幼いころ、よく遊んでもらった叔母でした。
沈丁花の香水が好きな叔母でした。
2012年08月01日 16:53
水滴 ---すいてき---
梅雨の季節になると、深い水の奥から蘇るような体験を思い出してしまいます。
その日、ボクは沖縄本島最北端の国頭村・奥集落に向けて車を走らせていました。
三日前から梅雨に入り、あいにくの空模様。今にも降り出しそうな雲が低く重く垂れこんでいました。
いつもなら紺碧の東シナ海を左手に臨みながらの58号線でしたが、その日は、どんよりとした空が海面ぎりぎりまで下がり、鉛色の海が陰鬱にかすんでいました。昼間のはずなのに夕刻のような薄暗さでした。時々、小雨がパラパラ降る程度で、まだ本降りにはなっていませんでした。
那覇を昼前に出発し、国頭村に差し掛かった午後の三時ごろ、あたりは一層暗くなり、垂れこめた低い雨雲をつつけば一気にザッときそうな様相でした。
-----------------------------------------------------------------
国頭村の佐手集落を過ぎ、宇嘉公民館を越え、宜名真集落に入るころには雷と稲光が激しく、ほどなく豪雨になることは、間違いない状況でした。
「まいったな・・・」
ボクは、うらめしげに空を見上げ、ハンドルを握りなおしました。
前方に宜名真トンネルが見えたとき、ひときわ強い閃光の稲光と同時に滝のような雨粒が一気に落ちてきました。車の屋根を叩く雨音で、激しい土砂降りだと分かりました。アスファルトに跳ね返った水しぶきが視界を遮るほどでした。
ボクは、減速し慎重にトンネルへと入っていきました。
トンネルの中は一層暗く、すぐにヘッドライトを灯しました。対向車も後続車もありませんでした。
「やれやれ・・・。ちょっとラッキーかな、トンネルで・・・」
ボクは独りごとを口にしました。
荒天のせいなのか時間帯のせいなのか、さっきから人の気配はもちろんのこと、すれ違う車の一台も通っていません。
トンネル内は、外の激しい雨音とは裏腹にボクの車の走行音以外聞こえませんでした。闇に伸びたヘッドライトの光だけが見えます。少し怖い圧迫感と湿った静寂がトンネル内の闇を包み込んでいるようでした。
と、『ポシャ』と車の屋根に水滴が落ちる音がふいに聞こえました。
「・・・トンネルでも雨漏りするのかな・・・」
ボクは上を見上げましたが、走行しているうえ、天井は暗くて確認できません。
相変わらず対向車も後続車もありません。
再び『ポシャ』と雨垂れの音がしたかと思うと、今度は規則的なゆっくりした間隔で『ポットン、ポットン、ポットン・・・』と水滴がボクの車の屋根に落ちる音が聞こえました。
前方のヘッドライトに照らされたトンネルの天井には水の滲みも染みも見えませんし、水滴が落ちてくる様子もありません。
でも、確かに、『ポットン、ポットン、ポットン・・・』と水滴がボクの車の屋根を叩いているのです。走行中なのにです。
周囲は真っ暗でした。
ボクは怖ろしくなり、スピードを上げ、バックミラー越しに後方を見ました。
深い闇が広がっているだけでなにも見えません。
それでも、相変わらず、絶え間なく『ポットン、ポットン、ポットン・・・』とリズムを刻みながらボクの車の屋根を叩いているのです。
-----------------------------------------------------------------
水滴は徐々にテンポを速め、『ポットン、ポットン、ポットン・・・』と・・・・まるで、得体の知れないナニかが迫ってくるように感じられました。
ボクは焦りました。
トンネルの出口が果てしなく遠く感じられ、ひょっとして迷宮に迷い込み、出口がないのでは、という錯覚さえ覚えました。
水滴はますますテンポを速め、車の屋根の後方から前方に移動しているようでした。
「なんなんだよ、これは」
ボクの焦りと恐怖はピークに達しました。
得体の知れないナニかが、すぐにでもフロントガラスから覗きだすほど水滴が真上から聞こえるのです。
「やばい!」、心底そう思った瞬間、前方にトンネル出口の光が見えました。
ボクは、意識的に上部もバックミラーも見ず、前方の出口のみを凝視し、飛ばしました。
すぐそこに、ほんの少し視線を上げれば「得体の知れないナニか」が貼りついているように感じられました。見てはいけない「得体の知れないナニか」の気配がするのです。
・・・一瞬、ザッと車全体を叩く雨音がしたかと思ったら、ボクはトンネルを抜け豪雨の中に突入していました。
激しい雨音にかき消され「雨垂れの音」は聞こえなくなっていました。
バックミラーに映ったトンネルの闇が徐々に雨に煙って見えなくなるまで、ボクは何度も後方を確認しました。
-----------------------------------------------------------------
偶然ですが、ボクが奥集落に向かったのは宜名真トンネル建設工事に従事した方への聞き取り調査が目的でした。当時は難工事のうえ、水脈にあたって大変だったと聞きました。トンネル内は換気が悪く、後々胸を患った人もいるとも聞きました。
あの「水音」と工事に関連性があるのかボクには分かりません。
ただ確かなのは、水滴の正体が未だに分からないのです。あの水滴はいったい・・・・
その日、ボクは沖縄本島最北端の国頭村・奥集落に向けて車を走らせていました。
三日前から梅雨に入り、あいにくの空模様。今にも降り出しそうな雲が低く重く垂れこんでいました。
いつもなら紺碧の東シナ海を左手に臨みながらの58号線でしたが、その日は、どんよりとした空が海面ぎりぎりまで下がり、鉛色の海が陰鬱にかすんでいました。昼間のはずなのに夕刻のような薄暗さでした。時々、小雨がパラパラ降る程度で、まだ本降りにはなっていませんでした。
那覇を昼前に出発し、国頭村に差し掛かった午後の三時ごろ、あたりは一層暗くなり、垂れこめた低い雨雲をつつけば一気にザッときそうな様相でした。
-----------------------------------------------------------------
国頭村の佐手集落を過ぎ、宇嘉公民館を越え、宜名真集落に入るころには雷と稲光が激しく、ほどなく豪雨になることは、間違いない状況でした。
「まいったな・・・」
ボクは、うらめしげに空を見上げ、ハンドルを握りなおしました。
前方に宜名真トンネルが見えたとき、ひときわ強い閃光の稲光と同時に滝のような雨粒が一気に落ちてきました。車の屋根を叩く雨音で、激しい土砂降りだと分かりました。アスファルトに跳ね返った水しぶきが視界を遮るほどでした。
ボクは、減速し慎重にトンネルへと入っていきました。
トンネルの中は一層暗く、すぐにヘッドライトを灯しました。対向車も後続車もありませんでした。
「やれやれ・・・。ちょっとラッキーかな、トンネルで・・・」
ボクは独りごとを口にしました。
荒天のせいなのか時間帯のせいなのか、さっきから人の気配はもちろんのこと、すれ違う車の一台も通っていません。
トンネル内は、外の激しい雨音とは裏腹にボクの車の走行音以外聞こえませんでした。闇に伸びたヘッドライトの光だけが見えます。少し怖い圧迫感と湿った静寂がトンネル内の闇を包み込んでいるようでした。
と、『ポシャ』と車の屋根に水滴が落ちる音がふいに聞こえました。
「・・・トンネルでも雨漏りするのかな・・・」
ボクは上を見上げましたが、走行しているうえ、天井は暗くて確認できません。
相変わらず対向車も後続車もありません。
再び『ポシャ』と雨垂れの音がしたかと思うと、今度は規則的なゆっくりした間隔で『ポットン、ポットン、ポットン・・・』と水滴がボクの車の屋根に落ちる音が聞こえました。
前方のヘッドライトに照らされたトンネルの天井には水の滲みも染みも見えませんし、水滴が落ちてくる様子もありません。
でも、確かに、『ポットン、ポットン、ポットン・・・』と水滴がボクの車の屋根を叩いているのです。走行中なのにです。
周囲は真っ暗でした。
ボクは怖ろしくなり、スピードを上げ、バックミラー越しに後方を見ました。
深い闇が広がっているだけでなにも見えません。
それでも、相変わらず、絶え間なく『ポットン、ポットン、ポットン・・・』とリズムを刻みながらボクの車の屋根を叩いているのです。
-----------------------------------------------------------------
水滴は徐々にテンポを速め、『ポットン、ポットン、ポットン・・・』と・・・・まるで、得体の知れないナニかが迫ってくるように感じられました。
ボクは焦りました。
トンネルの出口が果てしなく遠く感じられ、ひょっとして迷宮に迷い込み、出口がないのでは、という錯覚さえ覚えました。
水滴はますますテンポを速め、車の屋根の後方から前方に移動しているようでした。
「なんなんだよ、これは」
ボクの焦りと恐怖はピークに達しました。
得体の知れないナニかが、すぐにでもフロントガラスから覗きだすほど水滴が真上から聞こえるのです。
「やばい!」、心底そう思った瞬間、前方にトンネル出口の光が見えました。
ボクは、意識的に上部もバックミラーも見ず、前方の出口のみを凝視し、飛ばしました。
すぐそこに、ほんの少し視線を上げれば「得体の知れないナニか」が貼りついているように感じられました。見てはいけない「得体の知れないナニか」の気配がするのです。
・・・一瞬、ザッと車全体を叩く雨音がしたかと思ったら、ボクはトンネルを抜け豪雨の中に突入していました。
激しい雨音にかき消され「雨垂れの音」は聞こえなくなっていました。
バックミラーに映ったトンネルの闇が徐々に雨に煙って見えなくなるまで、ボクは何度も後方を確認しました。
-----------------------------------------------------------------
偶然ですが、ボクが奥集落に向かったのは宜名真トンネル建設工事に従事した方への聞き取り調査が目的でした。当時は難工事のうえ、水脈にあたって大変だったと聞きました。トンネル内は換気が悪く、後々胸を患った人もいるとも聞きました。
あの「水音」と工事に関連性があるのかボクには分かりません。
ただ確かなのは、水滴の正体が未だに分からないのです。あの水滴はいったい・・・・
2012年05月09日 18:47
義足
先週、ひょんなことから知人の整形外科医とこんな話題になりました。
人工の脚、つまり「義足」はどこまで速く走ることができるのか----------------
話題の発端は、昨年の八月、韓国・大邱で開催された陸上の世界選手権のことです。あのジャマイカのウサイン・ボルトの圧倒的な速さが注目されたのですが、一方で、南アフリカの義足のランナー、オスカー・ピストリウスが健常者のトップアスリートを抑え、爆発的なスピードで準決勝まで勝ち進んだのでした。
そのスピードは、「義足=遅い」というこれまでの常識を覆し、義足の方が速く走れ、フェアじゃない、と憤る選手もいるほどでした。
知人によると、「膝から下の切断の義足で、身体能力がトップアスリートクラスだったら義足の方が、はるかに速い。ボルトの記録も抜けると思いますよ。近い将来、必ずそうなるでしょうね」とのことでした。
-------------------------------------------------------
話は、いきなり変わりますが、スペインの小説家、ホセ・デ・エスプロンセダが百八十年以上も昔に書いた小説の中に「義足」というのがあります。
ストーリーをかいつまんで紹介しますと-------------------
昔、ロンドンに大金持ちの商人がいました。
商人は、事故で脚を骨折し切断してしまいます。
同じころ、義足作りでは右に出るものはいないといわれるほどの素晴らしい腕前を持つ義足職人がいました。金に糸目をつけない商人は、
「自分が義足を身につけているというよりも、義足が自分の体をひとりでに運んでくれるような、要するに、ひとりで勝手に歩きだすほどの脚がほしい」と職人に依頼します。
三日後、商人の要望通りの義足、つまり、ひとりで勝手に歩きだして止まらない義足を手に入れます。
望み通りの義足を手に入れた商人は大喜び。早速、義足を着け、あちこち見せびらかしに行くのですが、なにせ義足は勝手に歩き、走り出し、ついには永遠に世界中を駆け巡るようになります。
今でも、義足を着けたガイコツがピレネー山脈あたりをすごいスピードで駆けまわっているらしい。
----------------- といった内容です。
百八十年前の幻想と現在を比較するつもりはありませんが、未来の義足は、いったいどうなっているんでしょうねぇ・・・
2012年04月04日 16:38
犬環鎖 ----- インカンサ----
小学校のころ、犬を飼っていました。
『ジョン』という呼び名の雑種の中型犬でした。
その当時のボクの家は、木造のセメント瓦屋根の、いわゆる典型的な沖縄式瓦家屋(ウチナーカーラヤー)で、やや高めの床下がありました。大人が這って入れるほどの床下は、家屋の修理のための木材や使わなくなった日用品の物置になっていて、土の地面のためか夏場でもひんやりした空間でした。
その床下がジョンの住処で、餌の時間以外は、一日中、グータラ寝そべっている犬でした。
---------------------------------
そんなジョンが、深夜に床下から這い出て、どこかに出かけているのを知ったのは夏の満月の夜のことでした。
昼間にスイカを食べすぎたためか、その夜、ボクは何度かトイレに立ちました。当時、トイレは外にあり、夜でも母屋を出て、庭先を横切りトイレに通いました。
家族が寝静まった深夜の二時ごろだったと思います。満月が天空高く煌々と照っていました。ふと、門柱の脇を見るとジョンの出掛ける後ろ姿が見えました。あのグータラのジョンが、意気揚々と出掛けていくのです。軽い足取りで、小走りで駆けていくのです。
ボクはなぜだかジョンの出掛け先が気になり、後をつけることにしました。深夜でしたが、不思議と怖さは感じませんでした。月明かりと街灯の明かりで、思いのほか明るい夜だったせいかもしれません。
ジョンを見失わないよう、三十メートルほど間隔をあけて後を付けました。気付かれると、ちょっとした探偵ゴッコがふいになるような気がして、ボクは塀沿いの闇に隠れ、電柱に身を潜め、足音を殺しながら、後を追いました。
深夜の街は、すべて闇に溶けたように明かりの洩れている家さえなく、物音ひとつしませんでした。遠くの車の音はもちろん、深夜放送のラジオの音さえ流れていません。月明かりだけの静寂が漂っていました。
---------------------------
家から二百メートルほど後を追ったでしょうか。
ジョンが周囲をキョロキョロ窺いながら、歩を止めました。集落はずれの、街灯の切れかかった薄暗い交差点でした。
しばらくすると、交差点の四方の闇から、音もなく犬数匹が集まってきました。野犬の群ではなく、どの犬も飼い犬のようでした。首輪をしている犬も何頭かいました。
あっけにとられたボクは、やや離れた電柱の陰から息を殺して様子をうかがいました。
集まった犬は、全部で10匹。10匹が交差点の中央で環をつくり、伏せました。まるで、サーカスのよく調教された犬のように規律よく円をつくっているのです。吠えるでもなく、うなるでもなく、ただ黙って伏せているのです。
リーダーらしき黒い犬が、ときどき周囲を警戒するようなそぶりで首を上げる以外、どの犬も黙って伏せていました。なにか重要な会合をしているようにも見え、誰かの葬儀のような重々しい雰囲気にも感じられました。
長く、重い沈黙の後、黒い犬がいきなり天空に向かって遠吠えを始めました。
釣られるように、隣の犬も吠え、ついには10匹が一斉に遠吠えを始めました。
犬というより、獰猛な狼か山犬のような遠吠えに思えました。
ボクは、怖ろしくなり、電柱から後づさりし、全速で逃げました。すぐ後ろを得体の知れないモノに追いかけられている感じがしましたが、振り返ることなく家まで逃げ帰りました。
--------------------------
翌朝、おばぁちゃんに昨夜のことを話すと、ひどく叱られ、二度としないように諭されました。
おばぁちゃんの話だと、あれは『インカンサ(犬環鎖)』というもので、犬とあの世をつなぐ儀式みたいなものだから、人が詮索したり見たらいけない、とのことでした。また、その家の不幸や災難を犬が代わって厄払いしてくれる儀式でもあるから、深夜に犬が出掛けたら後を追ってはいけない、とも。
--------------------------
その後、ジョンは相変わらず床下でグータラな毎日を過ごしていましたが、ボクは月夜のジョンを詮索することを二度としませんでした。
生物学では、発見されていない中間形の化石を「失われた環鎖」(ミッシングリンク)というそうです。
もしかしたら、人間が失ったり、忘れた去った「環鎖(リンク)」を、ほかの生き物は、今でも、ちゃんと持っているのでは、と思うのです。
2012年03月14日 16:30
デジャヴ・・・・既視感
生来の放浪癖なのか旅好きなのか、あちこちの街を訪ねるのが好きです。
中学1年のときに小遣いを貯め、奈良の旧街道沿いを放浪したのを皮切りに、その後毎年のように近畿地方や北陸、日本海側の東北へと足をのばしていました。
旅、といっても、ほとんどがローカル線の電車やバスに乗り、何の変哲もない町で下車し街中を散策し、細い裏路地をウロウロするだけの、行き当たりばったりの行程でした。ただその旅の余韻が妙に心地よく、また次の彷徨へと出掛けるのでした。
幾度となく地方の路地裏を彷徨ううち、あるときフッと不思議な感覚に覚えるようになりました。
初めて訪れた町の、初めての路地なのに、妙に懐かしく見覚えのある風景に出くわすことが時たまあるのです。
それは、どこにでもありそうな街並みや路地なのに、以前訪れたことのあるような・・・昔住んでいたような・・・何か大事な「記憶」を思い出しそうな・・・哀しいくらい懐かしいような・・・そんな感覚なのです。
--------------------------------------------------------------
京都の産寧坂裏の路地を初めて歩いたとき、これまでに感じたことのないほどの強烈な、はっきりした既視感に襲われました。
産寧坂を下り切り、左の路地へと入ったときのことです。
入り組んだ細い路地は、曲がり角の多い迷路のような感じで、突き当たりの角から先はまったく見えない状況でした。道路ぎりぎりまでせり出した家屋の黒壁や屋根が、いっそうの圧迫感を感じさせていました。
路地の三つ目の角を曲がったとき、視界に入った風景が記憶の奥底からいきなり鮮明に蘇りました。以前映画で観たフラッシュバックのようでした。「見たことがあるような・・・」ではなく「知っている街」の風景なのです。はっきりした記憶でした。
ボクは記憶を試すように、頭の中で思い描きながら歩を進めました。
・・・次の角を曲がると三差路になっていて・・・
前方に板壁で仕切られた三差路が見えてきました。壁に貼られた町内会の連絡板も見覚えがあります。
・・・右の路地へ行くと三件目に瀬戸物屋さんがあり、その隣は漬物屋さんが・・・
当然のように、三件目の瀬戸物屋と漬物屋があります。思い描いた通りの店構えでした。
・・・その路地を抜けて、左に行くと銭湯の煙突が前方の空に・・・
見上げると、やっぱり高い煙突があります。休業中なのか煙は出ていません。
・・・そうそう、神塚ん家が銭湯の向かいだったな・・・
え? 神塚ってだれだ? 同級生だよな。あれ? 何で知っているんだ?
急いで煙突の下の銭湯に行き、向かいの表札を確認しました。家の狭い出入り口の脇に『神塚』という表札が掛かっています。
・・・神塚家から、角の駄菓子屋を曲がって六件目が俺の家で・・・
次の瞬間、ボクは得体の知れない恐怖に襲われ、全身の毛が総立ちました。足がすくみ、それ以上は進めませんでした。これ以上知ると後戻りできないような恐ろしい焦燥感のような感覚も感じました。
ボクは急いで踵を返し、今来た路地を、同じ順序で産寧坂に戻りました。
--------------------------------------------------------------
何年経っても、あのときの得体の知れない恐怖や焦燥感をはっきりと思い出すことがあります。
そして去年の秋、思い切って、再び京都・産寧坂を訪ねました。あの路地へ行ってみようと思ったのです。街並みはさほど変わった感じはしませんでしたが、なぜか、あの路地の入口が見つからないのです。
2012年02月22日 17:01
神隠し
Oさんは、ケアマネージャー(介護支援専門員)として医療福祉施設で働いています。
そのOさんが困惑気味に、こんな話を教えてくれました。
「最近、お年寄りが行方不明になるのが少なくないんですよ。なぜだか原因が分からない・・・」
Oさんの話によると、県内の福祉・介護施設はほぼ飽和状態だそうです。そのため、比較的元気で要介護度の低いお年寄りは自宅や近親者宅に帰され、そこでの生活や介護になるパターンが多いそうです。
そして、戻ったお年寄りの中には、以前の元気を取り戻し、趣味や散歩などで外出する機会が増える方もいるといいます。
「元気になった分、家を空けることがあるのはいいのですが、ある日突然、外出したっきり、ぷっつりと帰ってこなくなってしまうんですよ。痴呆があるわけでも徘徊の症状があるわけでもないんです。いつもの元気な姿で外出したっきり戻ってこないんです。『コンビニ行ってくる』って言っていなくなった人もいるんですよ」
もちろん家族や身内の方も心配し、立ち寄りそうな所をくまなく探すが見つかりません。その痕跡さえ残さず、消えてしまうそうです。
「事故や事件性を心配して捜索願い出す方もいらっしゃいますが、それでもまったく足取りが掴めないんです。分からない。手がかりもない、生死も分からない、いなくなった原因も、心当たりも、まったく分からないんです。先月も元教頭先生だった方が、『ちょっと月を見に』って出ていったっきり戻って来ないんですよ。そこの部落総出で探したけど見つかりませんでした。どうしてですかねぇ・・・」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本の行方不明者は、年間10万人以上いるといわれます。
10万人といえば、大きな町の住民すべてがいなくなるほどです。
古の沖縄では神隠しを『物隠し』と呼んでいたそうです。
物隠しに逢った者は、結界を越え、現世と神域の境に迷い込んでしまうそうです。
そして、物隠しに逢った者は、なぜか自分の櫛を持って帰ろうと戻ってきて、再び出て行ってしまいます。そのため、家族は、必死に当人の櫛を隠し、取られないようにします。
ただ、それでも、いつの間にか、持ち去られることもある、そうです。
そのOさんが困惑気味に、こんな話を教えてくれました。
「最近、お年寄りが行方不明になるのが少なくないんですよ。なぜだか原因が分からない・・・」
Oさんの話によると、県内の福祉・介護施設はほぼ飽和状態だそうです。そのため、比較的元気で要介護度の低いお年寄りは自宅や近親者宅に帰され、そこでの生活や介護になるパターンが多いそうです。
そして、戻ったお年寄りの中には、以前の元気を取り戻し、趣味や散歩などで外出する機会が増える方もいるといいます。
「元気になった分、家を空けることがあるのはいいのですが、ある日突然、外出したっきり、ぷっつりと帰ってこなくなってしまうんですよ。痴呆があるわけでも徘徊の症状があるわけでもないんです。いつもの元気な姿で外出したっきり戻ってこないんです。『コンビニ行ってくる』って言っていなくなった人もいるんですよ」
もちろん家族や身内の方も心配し、立ち寄りそうな所をくまなく探すが見つかりません。その痕跡さえ残さず、消えてしまうそうです。
「事故や事件性を心配して捜索願い出す方もいらっしゃいますが、それでもまったく足取りが掴めないんです。分からない。手がかりもない、生死も分からない、いなくなった原因も、心当たりも、まったく分からないんです。先月も元教頭先生だった方が、『ちょっと月を見に』って出ていったっきり戻って来ないんですよ。そこの部落総出で探したけど見つかりませんでした。どうしてですかねぇ・・・」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本の行方不明者は、年間10万人以上いるといわれます。
10万人といえば、大きな町の住民すべてがいなくなるほどです。
古の沖縄では神隠しを『物隠し』と呼んでいたそうです。
物隠しに逢った者は、結界を越え、現世と神域の境に迷い込んでしまうそうです。
そして、物隠しに逢った者は、なぜか自分の櫛を持って帰ろうと戻ってきて、再び出て行ってしまいます。そのため、家族は、必死に当人の櫛を隠し、取られないようにします。
ただ、それでも、いつの間にか、持ち去られることもある、そうです。
2012年02月08日 18:31
幸せを掴む手
友人のTは、海外協力機関の団体職員で、年間のほとんどを外国で過ごしています。
彼の仕事は「発展途上国」と呼ばれるアフリカ諸国や東南アジアの国々に経済援助や技術協力を行うための事前リサーチが主な業務で、現地の生活環境や経済状況などをつぶさに調査し報告書に纏める、ということをしています。
その調査のために、時として、その国の中でもかなりの僻地や内陸部の奥深くまで足を運ぶことも多いといいます。
・・・・カンボジア奥地のある村・・・
Tがその村を訪れたのは、カンボジアの長い内戦がようやく終わり、荒れ果てた国土に平穏な日常が戻りつつあった頃でした。
首都・プノンペンの調査を終え、現地の通訳兼案内人とともに、聞き取り調査のため、国内でも特に貧しいといわれる内陸部の小さな集落に向かいました。
村はプノンペンから車で六時間、さらに歩いて1時間。メコン川沿いの深い熱帯雨林の中にあり、数十世帯が寄り添うように暮らしていました。乾季の2月とはいえ、40度近い気温と湿気でうだるように暑い日だったそうです。
「草原の細い土道を歩いて集落に向っていたら、小さな男の子・・・五歳くらいかな・・・独りで遊んでいるんだよ。道端でね」
彼らに気付いた男の子は、ニコニコと満面の笑みで手を振り近づいてきました。案内人が訊ねると、これから訪ねる村の子で、石ころで遊んでいたということでした。
男の子は人懐っこい笑顔で「案内してあげる(現地語)」とTの手をひっぱり、先を歩み始めました。
「うれしいよね。ちっちゃな柔らかい手で、男の子が一生懸命引いてくれるんだもん」
しばらく男の子の手を握り、一緒に歩いていましたが、汗ばんだ手と噴出した額の汗をぬぐうため、いったん男の子の手を離しました。
手ぬぐいで汗を拭くTを男の子はニコニコと見上げていました。汗を拭き終え、男の子の手を再び握ったとき、ちょっと不思議な感触を覚えたそうです。
「なにかが違うだよね。なんだろう?って」
Tは握った手を緩め、男の子の左手を自分の掌(てのひら)で広げました。
「1、2、3・・・6本。指が6本あるんだよ。全然気付かなかったけど6本あるんだよ。数え直しても6本。左右両手ともだよ」
指は、親指や小指が追加されている感じではなく、違和感なく、きれいなバランスで6本揃っていました。「もともと、人間の手って6本かも」とTは思ったほどでした。
・・・・ 村の少年の家・・・・
男の子に導かれ、村に入ったTたちは、男の子の家を訪ねました。
細い木の柱と茅葺の屋根・壁。けっして裕福な生活をしているようには見えない家だったそうです。
「ようこそいらっしゃいました。どうぞどうぞ」(現地語)
突然の訪問にも関わらず、男の子の父親である家の主は笑顔で迎えてくれました。
男の子同様、人懐っこい笑顔で、差し出した手には6本の指がありました。
村のまとめ役でもある父親によると、この集落のほとんどの住民は6本指だそうで、5本の方が珍しいとのことでした。
「ずっとずっと昔、私のおじいちゃんのおじいちゃんのさらに昔から、この村では6本指が多く生まれてきました。私たちは『6本目の指は、神様からの特別な贈り物の指』だと思っています。この指のお陰でずっと幸せなんだと。もちろん、5本指の人も幸せですよ。私たち自身・・・あなたも、みんな神様からの贈り物です。生まれてきただけで幸せなんです」
国の幸福度を測る「地球幸福度指数」というものがあるそうですが、人間の幸せを決めていいのは神様だけではないのか、そうボクは思うのです。
2012年02月01日 17:43
窓
暮も押し迫った師走の雨の日、那覇市長田の古い雑居ビル・・・
ボクはビルの内装工事の打ち合わせのため業者のKさんと会っていました。
Kさんは七十歳を越したお年で、腰の低い穏やかな方でした。
雑居ビルは小さな高窓から少し光が差し込むだけの薄暗い室内で、
長い間空き室だったためか、どんよりした空気充満しているようでした。
打ち合わせを一通り済ませ、しばらく談笑をしていた時、Kさんがこんな話をしてくれました。
「・・・もう、四十年近くなるかな。ぼくはその頃、解体業もやっていて、あちこち行っていたんだよね。
・・・知念半島の・・・なんて部落だったかな・・・三月の暖かい日だったな・・・ある家の取り壊し作業に行ったんだ・・・」
斜面の中腹にあるその家は、年老いたおばあちゃんが独りで住んでいました。ご高齢のため施設に入居するので家を壊すとのことだったそうです。
屋敷は、西側の山を背に三方が開けていて、粟石のヒンプンとよく手入れされた小さな庭がありました。
Kさんは、壊す前に家の中と屋敷の周りを丹念にチェックしました。
「そんなに大きくない古い赤瓦屋だったけど、家中ほんとにきれいでね、どこもかも掃除がゆきとどいていて、壊すのもったいないくらいだった。特に東側の縁側からの景色は最高でね。低い石垣の向こうに海が一望できた。庭の芝生と石垣に這ったブーゲンビリアと山の稜線と光る海が連なってさ、毎日でも見ていたいくらい」
しばらく縁側に腰掛けて、景色を眺めていたKさんでしたが、ふと振り返って違和感を感じました。
「縁側の上に大きな・・・アルミサッシじゃなく、板枠のガラス窓があるんだが、なぜか板が打ちつけられているわけ。他にも窓はあるけど、なぜか東側のその窓だけ塞がれていて、外の景色が見えないようになっていた。窓ガラス一枚も割れてないのによ」
窓を塞いだ板は白っぽく変色し、打ちつけた釘は赤く錆びていて、直感で長い間閉じられていたと感じたそうです。
Kさんは家の主のおばあちゃんに理由を訊ねました。
おばあちゃんは、吶々とこう話してくれたそうです。
「この屋敷は、お父さん(旦那さん)と二人一生懸命働いてやっと建てたんです。もう、嬉しくて、嬉しくて、毎朝、お父さんと二人、この窓から景色を眺めながらお茶を飲むのが楽しみでした。毎日、朝の光る海を見て、幸せで、幸せで・・・」
ところが、家を建てた数ヵ月後、旦那さんは召集され戦争へとかり出されました。
「窓からの景色は、お父さんと二人だけの特等席。だから、おとうさんが帰って来るまで窓は閉じて、戻ってきたら、また一緒に見ようって。・・・ふふっ・・・可笑しいね、自分で釘打ってよ」
出征した翌年、夫の戦死通知がおばあちゃんの元へ届きました。でも、夫の死をどうしても信じることができないおばあちゃんは、夫がいつ帰ってきてもいいように、ずっと毎日掃除を続けていたそうです。
「一昨日の朝、その縁側にお父さんが腰掛けて光る海を眺めていたんですよ。振り返って『ありがとう。もういいよ』って。・・・夢だったのかねぇ」
ボクはビルの内装工事の打ち合わせのため業者のKさんと会っていました。
Kさんは七十歳を越したお年で、腰の低い穏やかな方でした。
雑居ビルは小さな高窓から少し光が差し込むだけの薄暗い室内で、
長い間空き室だったためか、どんよりした空気充満しているようでした。
打ち合わせを一通り済ませ、しばらく談笑をしていた時、Kさんがこんな話をしてくれました。
「・・・もう、四十年近くなるかな。ぼくはその頃、解体業もやっていて、あちこち行っていたんだよね。
・・・知念半島の・・・なんて部落だったかな・・・三月の暖かい日だったな・・・ある家の取り壊し作業に行ったんだ・・・」
斜面の中腹にあるその家は、年老いたおばあちゃんが独りで住んでいました。ご高齢のため施設に入居するので家を壊すとのことだったそうです。
屋敷は、西側の山を背に三方が開けていて、粟石のヒンプンとよく手入れされた小さな庭がありました。
Kさんは、壊す前に家の中と屋敷の周りを丹念にチェックしました。
「そんなに大きくない古い赤瓦屋だったけど、家中ほんとにきれいでね、どこもかも掃除がゆきとどいていて、壊すのもったいないくらいだった。特に東側の縁側からの景色は最高でね。低い石垣の向こうに海が一望できた。庭の芝生と石垣に這ったブーゲンビリアと山の稜線と光る海が連なってさ、毎日でも見ていたいくらい」
しばらく縁側に腰掛けて、景色を眺めていたKさんでしたが、ふと振り返って違和感を感じました。
「縁側の上に大きな・・・アルミサッシじゃなく、板枠のガラス窓があるんだが、なぜか板が打ちつけられているわけ。他にも窓はあるけど、なぜか東側のその窓だけ塞がれていて、外の景色が見えないようになっていた。窓ガラス一枚も割れてないのによ」
窓を塞いだ板は白っぽく変色し、打ちつけた釘は赤く錆びていて、直感で長い間閉じられていたと感じたそうです。
Kさんは家の主のおばあちゃんに理由を訊ねました。
おばあちゃんは、吶々とこう話してくれたそうです。
「この屋敷は、お父さん(旦那さん)と二人一生懸命働いてやっと建てたんです。もう、嬉しくて、嬉しくて、毎朝、お父さんと二人、この窓から景色を眺めながらお茶を飲むのが楽しみでした。毎日、朝の光る海を見て、幸せで、幸せで・・・」
ところが、家を建てた数ヵ月後、旦那さんは召集され戦争へとかり出されました。
「窓からの景色は、お父さんと二人だけの特等席。だから、おとうさんが帰って来るまで窓は閉じて、戻ってきたら、また一緒に見ようって。・・・ふふっ・・・可笑しいね、自分で釘打ってよ」
出征した翌年、夫の戦死通知がおばあちゃんの元へ届きました。でも、夫の死をどうしても信じることができないおばあちゃんは、夫がいつ帰ってきてもいいように、ずっと毎日掃除を続けていたそうです。
「一昨日の朝、その縁側にお父さんが腰掛けて光る海を眺めていたんですよ。振り返って『ありがとう。もういいよ』って。・・・夢だったのかねぇ」
2012年01月18日 19:04
音 ----- おと ----
北風がびゅーっ、と電線を揺らす季節になると思い起こすことがあります。
今より、ずいぶんと寒かった記憶のある小学校の冬の出来事です。
当時、沖縄でも年に数回霙(みぞれ)が降ることがあり、その出来事も珍しく霙の降った翌日のことでした。
ボクの通っていた小学校は、戦後間もなく建てられた古いコンクリート造りの校舎で、学年毎に二階建ての教室棟が建てられていました。
教室棟の中で最も古いのが三学年の校舎で、ところどころにコンクリートの剥離がおき、中の腐食した鉄筋がむき出しに見えるような状態で、かなり老朽化が進んでいました。校舎の周囲は、建てられた当時に植えられたという夾竹桃が高く生い茂り、紅の花を咲かせていました。
三学年の校舎がいつ建てられたのか、正確な年代は分かりませんが、ひとつだけ他の教室棟と違う造りになっていました。他の校舎は、どこの学校でも見られるような普通の横長二階建ての建物ですが、三学年の校舎だけ少し変わった設計で、幅広で急な階段に広い踊り場、狭い廊下、張り出した戸袋、そして、ぽつんと取ってつけたような小さな三階部分がありました。
三階部分は、急な階段の行き止まりにあり四畳半ほどの部屋になっていました。重厚な木製の引き戸と北側に明かり取りの小さな窓がひとつ付いていました。以前は「音楽準備室」に利用されていた、と聞いていましたが、当時すでに何年も使用されてなく、いわゆる「開かずの部屋」になっていてました。そのためか、入口の引き戸には錆びた太い鎖と錠前が三個、大げさなほど頑丈に施錠されていました。
--- 霙の降った翌日の放課後 ---
北風の吹きすさぶ寒い日でした。低く垂れさがった曇り空が陰鬱な気分にさせていました。
ひとりの一年生が校舎横から、あの「音楽準備室」の窓を見上げ、「誰かいる」と叫んだのが発端でした。
たまたま通りかかった四年生だったボクを含め、8人ほどの児童が窓を見上げました。しかし、窓の曇ガラスに当然ながら人影など見えません。
訝しげに、その一年生の男の子を振り返って見ると、
「いるよ。だって、ピアノの音と女の子の歌が聞こえるもん」と言うのです。
「ほんとかぁ?」
ボクは、半ば疑いながら訊ねると、男の子は真剣な顔でうなずき窓を見つめるのです。
冗談とは思えない表情に、ボクは再び窓を凝視し集中しながら耳を傾けました。
ぴゅぅぴゅぅ、と北風が電線を鳴らしているだけでした。
「ほら、何もいないし、聞こえないじゃないか。たぶん風の音が・・・」
と言いかけたとき、一陣の強い北風が一層高い音で電線を鳴らしたのと同時に、かすかにピアノの鍵盤を叩く音が「ポーン!」と聞こえたのでした。北風にかき消されて気付かなかったのですが、確かに耳をそばだてるとピアノの旋律が聞こえるのです。聞き覚えのない、かすかなメロディーでした。
風音とはまったく違う旋律が、風にかき消されては聞こえ、奏でては消え・・・を繰り返しているのです。あの「音楽準備室」から流れているのです。本物のピアノのある音楽室はグラウンドを挟んだ反対側なので、そこからの音漏れはありえませんでした。
周囲は騒然となり、児童が集まってきました。ボクには聞こえなかったのですが、「女の子の歌声」もピアノの音に乗って聞こえる、という子も何人かいました。
ボクと友人の三人が意を決して、音の正体を確認しに校舎の急な階段を恐る恐る上り、重厚な引き戸の曇りガラス越しに中を覗きました。
薄暗くなった「音楽準備室」の室内は古い書類や机、キャビネットなどが乱雑に置かれ、クモの巣とホコリだらけで何もいません。ピアノどころか楽器もありませんでした。
恐ろしいのを我慢して、耳を引き戸にあて、中の「音」を慎重に拾いました。ピアノの旋律と女の子の歌声はまったく聞こえなく、風の音だけが聞こえていました。
下校時間をとうに過ぎていたため、先生数人がやってきて、その日は怒られつつ、そこにいた児童全員はしぶしぶ下校しました。
---- 翌日 -----
昨日の出来事は、あっという間に学校中の噂になり、
「昔、当番で音楽準備室に楽器を取りにいった女の子があの部屋でいなくなった」とか「何かを閉じ込めるために頑丈に鍵をかけてある」とか、「異次元の入口だ」とか、いろいろなデマや怪しげな情報が飛び交い授業どころではなくなっていました。
先生方にも動揺があったようで、緊急の職員会議が開かれました。
そして。それから数日後、教員数名で「音楽準備室」の片づけが行われることになりました。部屋をきれいにし、内装をよくし、コミュニティールームにしよう、とのことだったそうです。
ところが、片づけの日、教員のひとりが原因の分からない自殺をしてしまったため、計画は中止になりました。
その後、「音楽準備室」からピアノの音が聞こえることはありませんでしたが、なぜか入口の引き戸には、真新しい頑丈な錠前が追加され、四個の重々しい錠前が大げさに施錠されていたのでした。
今より、ずいぶんと寒かった記憶のある小学校の冬の出来事です。
当時、沖縄でも年に数回霙(みぞれ)が降ることがあり、その出来事も珍しく霙の降った翌日のことでした。
ボクの通っていた小学校は、戦後間もなく建てられた古いコンクリート造りの校舎で、学年毎に二階建ての教室棟が建てられていました。
教室棟の中で最も古いのが三学年の校舎で、ところどころにコンクリートの剥離がおき、中の腐食した鉄筋がむき出しに見えるような状態で、かなり老朽化が進んでいました。校舎の周囲は、建てられた当時に植えられたという夾竹桃が高く生い茂り、紅の花を咲かせていました。
三学年の校舎がいつ建てられたのか、正確な年代は分かりませんが、ひとつだけ他の教室棟と違う造りになっていました。他の校舎は、どこの学校でも見られるような普通の横長二階建ての建物ですが、三学年の校舎だけ少し変わった設計で、幅広で急な階段に広い踊り場、狭い廊下、張り出した戸袋、そして、ぽつんと取ってつけたような小さな三階部分がありました。
三階部分は、急な階段の行き止まりにあり四畳半ほどの部屋になっていました。重厚な木製の引き戸と北側に明かり取りの小さな窓がひとつ付いていました。以前は「音楽準備室」に利用されていた、と聞いていましたが、当時すでに何年も使用されてなく、いわゆる「開かずの部屋」になっていてました。そのためか、入口の引き戸には錆びた太い鎖と錠前が三個、大げさなほど頑丈に施錠されていました。
--- 霙の降った翌日の放課後 ---
北風の吹きすさぶ寒い日でした。低く垂れさがった曇り空が陰鬱な気分にさせていました。
ひとりの一年生が校舎横から、あの「音楽準備室」の窓を見上げ、「誰かいる」と叫んだのが発端でした。
たまたま通りかかった四年生だったボクを含め、8人ほどの児童が窓を見上げました。しかし、窓の曇ガラスに当然ながら人影など見えません。
訝しげに、その一年生の男の子を振り返って見ると、
「いるよ。だって、ピアノの音と女の子の歌が聞こえるもん」と言うのです。
「ほんとかぁ?」
ボクは、半ば疑いながら訊ねると、男の子は真剣な顔でうなずき窓を見つめるのです。
冗談とは思えない表情に、ボクは再び窓を凝視し集中しながら耳を傾けました。
ぴゅぅぴゅぅ、と北風が電線を鳴らしているだけでした。
「ほら、何もいないし、聞こえないじゃないか。たぶん風の音が・・・」
と言いかけたとき、一陣の強い北風が一層高い音で電線を鳴らしたのと同時に、かすかにピアノの鍵盤を叩く音が「ポーン!」と聞こえたのでした。北風にかき消されて気付かなかったのですが、確かに耳をそばだてるとピアノの旋律が聞こえるのです。聞き覚えのない、かすかなメロディーでした。
風音とはまったく違う旋律が、風にかき消されては聞こえ、奏でては消え・・・を繰り返しているのです。あの「音楽準備室」から流れているのです。本物のピアノのある音楽室はグラウンドを挟んだ反対側なので、そこからの音漏れはありえませんでした。
周囲は騒然となり、児童が集まってきました。ボクには聞こえなかったのですが、「女の子の歌声」もピアノの音に乗って聞こえる、という子も何人かいました。
ボクと友人の三人が意を決して、音の正体を確認しに校舎の急な階段を恐る恐る上り、重厚な引き戸の曇りガラス越しに中を覗きました。
薄暗くなった「音楽準備室」の室内は古い書類や机、キャビネットなどが乱雑に置かれ、クモの巣とホコリだらけで何もいません。ピアノどころか楽器もありませんでした。
恐ろしいのを我慢して、耳を引き戸にあて、中の「音」を慎重に拾いました。ピアノの旋律と女の子の歌声はまったく聞こえなく、風の音だけが聞こえていました。
下校時間をとうに過ぎていたため、先生数人がやってきて、その日は怒られつつ、そこにいた児童全員はしぶしぶ下校しました。
---- 翌日 -----
昨日の出来事は、あっという間に学校中の噂になり、
「昔、当番で音楽準備室に楽器を取りにいった女の子があの部屋でいなくなった」とか「何かを閉じ込めるために頑丈に鍵をかけてある」とか、「異次元の入口だ」とか、いろいろなデマや怪しげな情報が飛び交い授業どころではなくなっていました。
先生方にも動揺があったようで、緊急の職員会議が開かれました。
そして。それから数日後、教員数名で「音楽準備室」の片づけが行われることになりました。部屋をきれいにし、内装をよくし、コミュニティールームにしよう、とのことだったそうです。
ところが、片づけの日、教員のひとりが原因の分からない自殺をしてしまったため、計画は中止になりました。
その後、「音楽準備室」からピアノの音が聞こえることはありませんでしたが、なぜか入口の引き戸には、真新しい頑丈な錠前が追加され、四個の重々しい錠前が大げさに施錠されていたのでした。
2011年12月07日 18:33
魂 ---- まぶい ----
海には人間が住む現世界とは異なる時空があるのでは、と思うことがあります。
幼い頃、近所の老漁師からこんな話を聞きました。
「人は、陸でしか死ねないように出来ている。だから海で死んだ死体は、必ず陸地に向かって流れて来るんだ」と。
ボクの勝手な思い込みや先入観かもしれませんが、水の事故などでの水死体は、海流や波の向き風の方向に限らず必ず海岸線や陸地近くに流れ着くように思います。死体が泳ぐわけがないのですから、なんかしらの強い力が引き寄せているか、押し出されているように思えてなりません。
話は少し変わりますが、ボクの友人にスキューバダイビングのインストラクターがいます。彼は沖縄屈指のダイビング歴があり、沖縄の海はすべてといっていいほど潜っています。海に関する知識も驚くほど豊富で、警察官や消防士に講習を行うこともあります。
そんな彼が、ボランティアで遺骨収集をしたときの話です。遺骨収集といっても、ダイビングのプロですから海中での探索でした。
----- 夏のある日・沖縄本島南部喜屋武岬沖 ------
喜屋武岬あたりは、戦争の激戦地で、戦後多くの遺骨が収集されました。
海岸沿いのガマ(洞窟)でもたくさんの遺骨が収集されたものの海中の骨はそのままのようでした。
快晴の青空が水中からもくっきりと仰ぎ見れた日でした。
岬沖は、サンゴ礁の地形が複雑なうえ海流も速く、ベテランダイバーでも苦戦していたそうです。
「初日は流れに押されながら、あっちこっちの岩の割れ目やサンゴ礁の下を覗いて探したんだが、なんにも見つけきれなかった。戦後何十年も経っているからね」
結局、海中遺骨収集一日目は、ひと欠片の骨も拾えなく帰路についたそうです。
そして、その日の夜、
「ウトウトしていると、ハタッと思い出したんだよ。何年か前に岬はずれの沖合を潜ったときに、サンゴ礁の切れ目に細長い洞窟があったことをね」
---- そして、翌日 ----
昨日のダイビングポイントから三百メートルほど西にずれた沖合にボートの錨を打ち、飛び込みました。そう、昨夜思い出した、あの洞窟が目標でした。
「あったよ、洞窟。水深20メートルくらいかな。海流が速いんでゆっくり近づいていったんだ」
と、洞窟に近づいたとき奥からカラカラコンコンと音が聞こえたそうです。緊張しながら、洞窟を覗きました。
「サンゴの欠片か石だと思っていたら、骨だわけ。頭蓋骨が四個くらいに、あと太い骨。薄暗い洞窟の中、真っ白な骨が流れに揺られて行ったり来たりしながらぶつかってカラカラ音を立てているわけさ。ここに居るって。早く引き上げてくれって」
骨は、戦後数十年もの間、薄暗い海の底の洞窟の中、カランコロンと音を立て行ったり来たりしていたのです。遺骨への怖さや哀れさより、戦争の虚しさを感じたといいます。
その年、四日間の海中遺骨収集が行われましたが、洞窟の骨のみが拾いあげられたそうです。
------- さらに一年後 -------
「翌年も気になったんで、潜りに行ったわけ。ボランティアじゃなく・・・・んー、なんとなくね。個人的に。骨? あったんだよ、これが!どうやって集まってきたんだろうね。海流だけでは説明がつかないなぁ。わからない!」
不思議なことに、それから数年の間、毎年、その洞窟で遺骨は収集されたそうです。
海には人間が住む現世界とは異なる時空があるのでは、と思うことがあります。
そして、人は陸でしか死ねないように出来ている、とボクは思うのです。
2011年11月30日 18:08
都はるみ --- エピソード2 ---
幼馴染のSは、マグロ船の船員です。
100トン足らずの船で外洋を駆け巡り、遠くインド洋までマグロを追って航海していました。
そのSの船がフィリピン沖500海里の洋上で火災に遭いました。
暮も押し迫った12月の深夜のことでした。時化模様の海に北風が容赦なく吹きすさんでいたといいます。
火は機関室から出火し、瞬く間に燃え広がったそうです。
「もちろん懸命に消化したさ。だけど全然ダメ。オイルの塊のエンジンが燃え、機関室からどんどん広がって、あっというまに船全部真っ黒な煙の中」
深夜の外洋のど真ん中。しかも大時化で波も高く視界も悪い状況でした。
「底(船底)に穴が開いたのか、浸水して沈みだしたわけ。燃えながら沈んでいくわけさ。もお、操舵室しか残っていないから、必死で屋根によじ登ってよ」
火災と浸水は急速で、遭難信号を打つのがやっと。救命ボートや浮輪は焼け落ちてしまったようでした。
「船長と俺と操舵室の上。波はもうドンドンくるし、周り真っ暗で見えないし、ゴンゴン揺れながら沈んでいくのに。もお死んだ、と思ったね」
死を覚悟し、操舵室屋根のアンテナに懸命にしがみつき、足元は海面に浸かりそうになっていました。
漆黒の闇の中で、時化の激しく打ち寄せる波の音と風の音だけが鳴り響いていました。
と、ゴゥという風の音に乗って「都はるみ」の「あんこ椿は恋の花」の歌声がかすかに聞こえたといいます。
「死ぬとき、幻聴やら幻覚やらが聞こえることがあるっていうけど、それだと思ったよ。もうダメだ、って思っていたからね」
意に反して、都はるみの歌声は徐々に、はっきりと響いてきました。そして、その歌声の方からボワッとした明かりが波間に見え隠れしながら近づいてきました。船でした。漆黒の波間に煌々とあかりを点した船が大音響を流して助けに来てくれたのでした。偶然にも近くを航行していた高知の漁船が救難信号を聞きつけ、駆けつけてくれたそうです。
洋上の救助の際、日本の船舶はありったけの電灯を点し、大音響の演歌を流して、遭難者に勇気と安心と信頼を伝えるのだと聞きました。たとえ荒れ狂う洋上でも、不安と恐怖が渦巻く夜の海でも、極寒の北の海でも、救助を求める声があれば必ず助けに向かうとも聞きました。それが海で働くものの流儀だとも。
そして、もっとも勇気と安心を与える日本の歌が「都はるみ」なのです。
100トン足らずの船で外洋を駆け巡り、遠くインド洋までマグロを追って航海していました。
そのSの船がフィリピン沖500海里の洋上で火災に遭いました。
暮も押し迫った12月の深夜のことでした。時化模様の海に北風が容赦なく吹きすさんでいたといいます。
火は機関室から出火し、瞬く間に燃え広がったそうです。
「もちろん懸命に消化したさ。だけど全然ダメ。オイルの塊のエンジンが燃え、機関室からどんどん広がって、あっというまに船全部真っ黒な煙の中」
深夜の外洋のど真ん中。しかも大時化で波も高く視界も悪い状況でした。
「底(船底)に穴が開いたのか、浸水して沈みだしたわけ。燃えながら沈んでいくわけさ。もお、操舵室しか残っていないから、必死で屋根によじ登ってよ」
火災と浸水は急速で、遭難信号を打つのがやっと。救命ボートや浮輪は焼け落ちてしまったようでした。
「船長と俺と操舵室の上。波はもうドンドンくるし、周り真っ暗で見えないし、ゴンゴン揺れながら沈んでいくのに。もお死んだ、と思ったね」
死を覚悟し、操舵室屋根のアンテナに懸命にしがみつき、足元は海面に浸かりそうになっていました。
漆黒の闇の中で、時化の激しく打ち寄せる波の音と風の音だけが鳴り響いていました。
と、ゴゥという風の音に乗って「都はるみ」の「あんこ椿は恋の花」の歌声がかすかに聞こえたといいます。
「死ぬとき、幻聴やら幻覚やらが聞こえることがあるっていうけど、それだと思ったよ。もうダメだ、って思っていたからね」
意に反して、都はるみの歌声は徐々に、はっきりと響いてきました。そして、その歌声の方からボワッとした明かりが波間に見え隠れしながら近づいてきました。船でした。漆黒の波間に煌々とあかりを点した船が大音響を流して助けに来てくれたのでした。偶然にも近くを航行していた高知の漁船が救難信号を聞きつけ、駆けつけてくれたそうです。
洋上の救助の際、日本の船舶はありったけの電灯を点し、大音響の演歌を流して、遭難者に勇気と安心と信頼を伝えるのだと聞きました。たとえ荒れ狂う洋上でも、不安と恐怖が渦巻く夜の海でも、極寒の北の海でも、救助を求める声があれば必ず助けに向かうとも聞きました。それが海で働くものの流儀だとも。
そして、もっとも勇気と安心を与える日本の歌が「都はるみ」なのです。
2011年11月03日 21:35
メトロノームの夢
学生のころ、海洋調査船に一カ月乗船したことがあります。
船は2000トン級で、全長88.8メートル。主に外洋の海底調査を任務としていました。
海底の調査は、決められた海域を正確な碁盤状に航行しながらポイントポイントで調査を行うもので、風向きや波の方向、潮流などに関係なく、ただひたすら船を直進させて行います。ですから、船の揺れは尋常ではありませんでした。
調査を開始して一週間目、船は調査地点を移動し、台風の余波が残る海域に差しかかりました。
船のすべてのハッチが閉じられ、船外への外出が規制されました。「波がちょっと高いから」との説明でした。好奇心旺盛なボクは、団長(調査団の)に頼み込み、デッキで波を見学することにしました。外洋の「高波」なんて、めったに体験できない、と思ったのでした。
恐る恐るハッチを開け、船外へ出たボクは唖然としました。船の周りにあるのは「波」ではなく「水の壁」でした。デッキから手を伸ばせば触れそうなところに水の壁が出来ているのです。巨大な水の壁が幾重もの山脈となっているのです。2000トンもある船が、まるでオモチャの船のようなスケールなのです。その真っ只中をひたすら直進しているのです。
船が山脈の頂上(波頭)に差しかかると、船尾のスクリューが宙に浮き、ギャンギャンギャンとすごい音を立て空気を切り裂きます。2000トン・88メートルの船が水の上で宙吊りになるのです。そのあと、ジェットコースターのように水の谷の奥底、奈落の底へと落ちるのです。谷底は、四方を水の壁に囲まれ薄暗くなり、空が狭く見えるのです。そして、船は再び山脈を駆け上り、またギャンギャンギャンと中空を切り裂き、ジェットコースターとなって迷宮に落ちてゆくのです。
荒れた海域では、就床にも、いつもと違う儀式があります。
乗組員の船室には二段ベッドがあり、なぜかベッドに幅広の皮ベルトが三本付いています。そう、荒れた日は自分自身をベッドにきつくくくりつけ、ベッドから振り落とされないように寝るのです。
そして決まって、巨大なメトロノームに縛り付けられ振り回される夢を見るのです。
2011年11月02日 12:03
都はるみ --- エピソード1 ---
映画「孤高のメス」をテレビ放映で観ました。
映画は敏腕の外科医・当麻が田舎の病院に赴任し、その卓越した技術と患者本位の考え方で、現代医療現場の問題点をあぶりだす、といった内容でした。
ボクが印象に残ったのは劇中の一場面。主人公が執刀する手術(オペ)の際、BGMとして都はるみを選曲して流したことでした。
実は、都はるみの「歌」には鮮烈な想い出が二つあります。
---- エピソード1 -------
ボクの父親は漁師でした。
沖縄で南洋景気といわれた昭和の中ごろまで、遠洋漁業の鰹船に乗っていました。
その頃の遠洋漁業は、年間300日以上が海の上。一旦出港すると一年近くも家に帰らない状態でした。
父親の船も同様で、毎年クリスマスの前後に帰港し、正月を迎え、三ガ日が明けるとまた次の航海へと出発する、といった繰り返しでした。一年のうち、年末年始のわずか十日前後しか陸に上がらず、再び長い漁へと出かけるのです。
鰹漁はハードで、常に危険と隣り合わせの仕事です。船上での病気や怪我は命を落とすことさえありました。そんな環境の中でも水揚げ(漁獲量・収益)を上げなければなりません。
そんなこともあって遠洋漁業の出港時は、龍神を祀る神社に大漁と航海安全を祈願するのです。
神社のある岬の沖を船団を組んで何周も回り、漁船にありったけの大漁旗を揚げ、大音響の「都はるみ」を流し、乗組員総出で手を合わせて船上から祈願するのです。祈願とともに、さよならの手を振るのです。
岬では、船員の家族はもちろん、島人総出で見送ります。手(ティ)サージを高く強く、さよならの手を振ります。ほとんどの人が泣いています。
船は岬の沖を何周かした後、一隻一隻と船団の輪を離れ、はるか水平線へと消えていくのです。
都はるみの大音響がいつしか薄れ、波の音にかき消されては、また風に乗ってかすかに聞こえ、そう繰り返しながら、船影が波間に見えなくなるのです。
・・・出港すると、船員も家族も、また長い一年が始まります。
・・・岬では、不安と淋しさと心配と悲しさと・・・ありったけの感情が取り残されるのです。
都はるみの歌は、胸を締め付けられる感情の渦を呼び起こすのです。
2011年10月26日 11:57